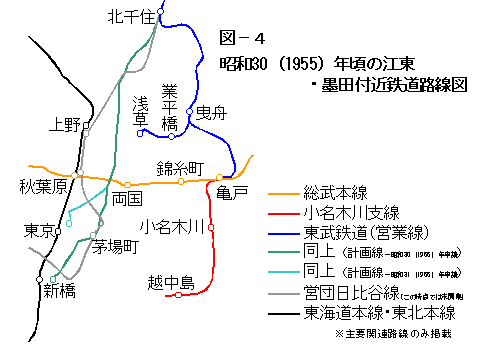
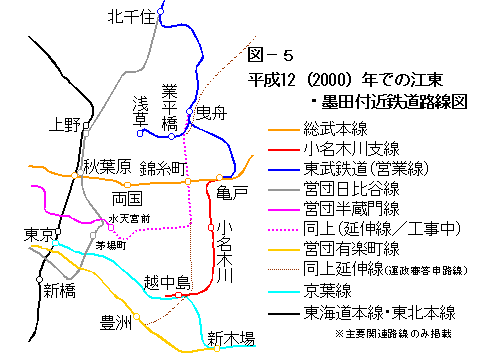
| このページは、2019年3月に保存されたアーカイブです。最新の内容ではない場合がありますのでご注意ください |
第3章 東武鉄道の都心乗入にかける努力
総武鉄道の国有化に伴い、浅草を伊勢崎線の起点と定めた東武鉄道であるが、この立地で満足しているわけではなかった。また、客観的に見ても十全の立地とはいえない状況でもあった。大正12(1923)年10月、東武鉄道は浅草−上野間の免許を申請した。この申請は、上野からさらに東京延伸の含みを持たせたものだという。
しかし、東京地下鉄道浅草−新橋間の計画と競願になったため、東武鉄道の免許は浅草(現在の業平橋)−花川戸(後の浅草雷門/現在の浅草)間のみとされた。しかも、関東大震災の復興計画に絡み、路線の建設には様々な制約条件を課せられた。
結果として、隅田川橋梁西詰にはR= 100mの急曲線が挿入され、ビル内に設けられた浅草駅ホームは6両編成対応の短いものとなった。
当時はこれでも充分画期的であったが、戦後の高度成長期においては、ターミナル立地の不便さと容量の小ささは覆いがたいものになっていた。
東武鉄道は、北千住から分岐、三ノ輪・田原町・浅草橋・人形町・茅場町などを経由し新橋に至る地下新線の建設を企図、昭和30(1955)年12月に免許申請を行った。さらには小田急と連携するなどの動きをも示した。都心への地下新線は結局認められなかったが、昭和37(1962)年 5月から開始された営団日比谷線との相互直通運転として結実した。
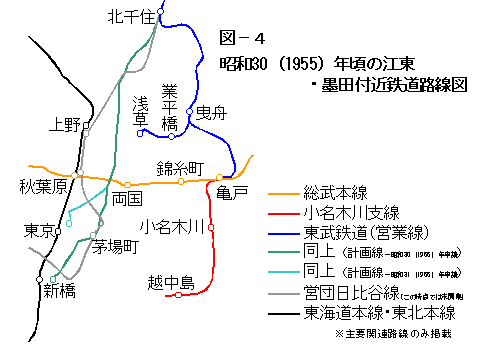
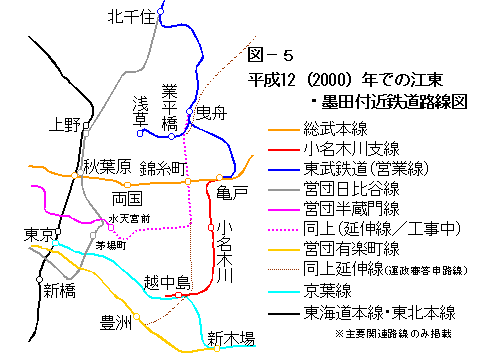
東武伊勢崎線は、営団日比谷線との相互直通運転により、全く違う路線に変貌を遂げたといってよい。参考文献(01)は「日比谷線直通運転開始後の変化は、まさに劇的」と率直な驚きを記している。特に利用者の伸びは想定をはるかに上回った。
日比谷線の北千住口は18m車 6連の運行を想定していた(中目黒口では18m車 8連)。ところが、この想定を凌駕する利用者が押し寄せたため、北千住口においてはホーム延伸の必要に迫られた。また、伊勢崎線内でも線路容量が逼迫し、複々線化を推進しなければならなくなった。
それでもなお、利用者は増加を続け、東武鉄道では新たな対応を求められた。その解決策のひとつが営団半蔵門線との相互直通運転である。営団半蔵門線を水天宮から押上まで延伸し、東武伊勢崎線業平橋−曳舟間を複々線化(実態は押上までのアプローチ線)し、相互直通運転を図る計画である。東武鉄道は、都心への直通ルートをふたつ確保することになる。
ここで、考えてみなければなるまい。小名木川支線が東武鉄道のものであったら、事態はどうであったかを。
新橋までの自力延伸は無理だったかもしれない。それでも、相互直通の相手を選択するにあたり、より豊富な選択肢を与えられたに違いない。現在の路線名でいえば、営団有楽町線・半蔵門線が最有力候補になるだろう。営団東西線や都営新宿線との連絡も、充分に想定可能であろう。しかし、小名木川支線は鉄道省→国鉄→JR東日本のものであって、これを東武鉄道が活用することはできなかった。
小名木川支線は、江東区の貨物輸送のゲートウエイとして、重要な役割を果たしてきたことは間違いない。ところが、その役目を終える時機が到達したとき、組織の枠を超えて線路を活用するという発想は今までなかった。おそらく、これからもないだろう。
これ以上のことは、あえて記さない。後知恵のむなしさもあるが、既存の線路を最大限に生かすという思想だけでは世の中は動かないし、動きようがないからだ。線路を生かしたいとの思いは鉄道が好きな者のみが持ちうる感情であって、世の中全体を動かす原動力にはなりえない。現実は、もっと複雑なものなのだ。
ここではただ、優良な線形を有する貨物線が廃れる一方で、それに並行して地下鉄新線が建設される不思議さのみを書きとめておこう。
元に戻る
| このページは、2019年3月に保存されたアーカイブです。最新の内容ではない場合がありますのでご注意ください |