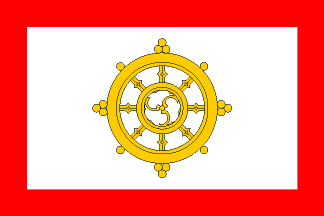1642年 建国
1890年 英国の保護領になる
1950年12月5日 インドの保護領となる
1975年5月16日 インドに併合されて消滅下の地図の「パキス タン」は、現在のバングラデシュです。その理由は こ ちら を参照シッ キムとはヒマラヤ山脈の麓、ネパールとブータンの間に存在した国で、インドからチベットへの玄関口にあたる戦略的に重要な場所だ。ネパールやブータンから もチベットへ行く道はあるが、交易のメインルートはシッキムだった。
シッキムにはもともとチベット系のレプチャ人が住んでいたが、17世紀にチベット人(ブディア人)がシッキム王国を建てた。日本の仏教 に天台宗や日蓮宗などいろいろな宗派があるように、チベット仏教にも多くの宗派があるが、政教一致のチベットでは宗教権力=政治権力だから、宗派間の抗争 は激しかった。既存のチベット仏教各宗派を堕落していると批判して台頭した新派(ゲルク派)の法王だったダライ・ラマが、モンゴルの介入でチベットの政権 を握ったのは1642年のことだが、同じ年に抗争に敗れた古派(ニンマ派)の3人の高僧がヒマラヤの南に逃げて来て、王を推戴したのがシッキム王国の始ま りだ(※)。
※同様に、ドゥクパ・カギュ派の法王が、ヒマラヤ山脈の南に逃れて建てた国が ブー タン 。こんな経緯から、チベットとシッキムの関係は複雑で、チベットはシッキムを属国と見なし、チベットを属国にしていた清朝もシッキムは属国の属国だと見なし ていた。しかし19世紀になるとインドを植民地にしたイギリスが進出し、1849年にシッキムの南半分にあたるダージリンを割譲させたのに続き、反発した チベットの軍勢を撃退して、1890年に清朝と条約を結び、シッキムを保護国にした(※)。※イギリスがシッキムに目をつけたのは、チベットへの玄関口と言う戦略的重要性の ほかに、インドに駐在するイギリス人の避暑地が欲しかったから。クーラーがなかった時代、夏のインドの暑さに耐え切れず病気になるイギリス人は多く、ダー ジリンのような涼しい高原の保養地は必要不可欠だった。さて戦後、1947年にインドが独立すると、それまでシッキムにおけるイギリスの地位はインドが引き継ぐことになり、50年に新たな条約が結ばれて、シッ キムは外交と防衛、通信をインドに委ねる保護国になったが、この時の条約でシッキム王国は民主化を進めるこ とが規定された。こうしてシッキムでは国会とそれに基づく内閣が作られることになった。しかし問題になったのが、シッキムの人口構成だった。シッキムの住民は王国を支えてきたレプチャ人とチベット人が合わせて25%だった のに対して、ネパール人が75%を占めていた。イギリスがシッキムから獲得したダージリンで 茶の生産を始めた時、働き者のネパール人を茶園労働者として大量に雇ったが、彼らはシッキムにも移住してせっせと農地を開拓し、気が付いたらシッキムの最 大民族になっていたという次第。民主化で国民の声がそのまま議会に反映されたら、「ヨソ者」のネパール人に政治の主導権を握られてしまうことになる (※)。
※チベット人や国王だって、数百年前まで遡れば「ヨソ者」なのだが、そういうこと はもちろん無視。そこで国会の議席を民族別に割り当て、全12議席のうちレプチャ人とチベット人が6議席、ネパール人が6議席としたうえに、5議席は選挙ではなく国王が任 命する仕組みにした。こうしてシッキム国会は、王制を支持する議員が多数派を占めるように工夫さ れたのだが、ネパール人たちは「せっかく民主化が実現したのに、自分たちの声が不当に抑圧されている」と反発を強め、61年には親インド派政党のシッキム 国民会議派(※)を結成して、王制の廃止を主張し始めた。※インドの政権与党だったインド国民会議派の友党で、後にシッキムがインドに併合 されると、シッキム国民会議派もインド国民会議派に吸収合併された。こうした批判をかわすために、選挙制度は徐々に手直しされて、シッキム国民会議派は最大勢力になったが、73年の選挙で王政維持を掲げるシッキム国民党が 過半数の議席を獲得すると、選挙に不正があったからだと暴動が発生。そこでインドが介入し、インド政府と国王、首相との間で「選挙制度は人口の構成比率を 反映できるものとする」という協定が結ばれた。こうして翌74年に再び実施された選挙では、全32議席のうちシッキム国民党はわずか1議席に転落し、シッ キム国民会議派が31議席を占め、首相に就任したドルジェは国王の権限を大幅に縮小する憲法を制定した。そして1975年4月9日、「国王退位を求めるデモ隊に宮廷親衛隊が発砲して混乱し収拾がつかないと、ドルジェ首相から派兵の要請が あった」ことを理由にインド軍が侵攻。宮廷親衛隊はたちまち武装解除され、国王はインド軍に保護(幽閉)されて、シッキム国会は翌日「民主主義発展の妨害 者である国王の廃止と、責任感の強い政府であるインドへの併合」を満場一致で決議した。そして14日に実施された国民投票でもインドへの併合が賛成多数で 承認され、5月16日にインドのシッキム州が成立。3世紀続いたヒマラヤの小国はあえなく消滅したのだった。

49年間王位にあったタシ王(左)、若いアメリカ娘を妃に迎 えてゴキゲンのパルデン王(右)
それにしてもまるで キョンシー 親子みたい・・・?インドが強引に併合を進めたのは、チベット動乱(1959年)や中印戦争(1962年)でシッキムが対中国の最前線になったためだっ た。実際に中印戦争ではシッキムとチベットとの国境で中国軍とインド軍の衝突が起きていた。そして71年に第三次印パ戦争が起きたが、当時パキスタンは中 国と友好関係を強化しており、将来再びパキスタンとの戦争になった場合、チベットから中国軍が南下してくることを恐れたこともあった。一方、シッキム国王 も中国の介入を恐れて、インドによる併合を国際社会へ訴えることを断念したようだ。
そして併合当時、国王はネパール人のみならずチベット人やレプチャ人からも信頼を失っていた。シッキムはタシ・ナムギャルが1963年 に死亡した後、息子のパルデン・トンドゥプ・ナムギャルが第12代国王に即位した。パルデン王は皇太子時代の57年に妻を亡くし、59年に来日した際「こ んどは日本人と結婚したい」と発言して話題を振りまいたことがあったが、結局63年にダージリンのホテルのバーで知り合った22歳年下のアメリカ女性ホー プ・クックにひと目惚れして、王妃に迎えた。このため保守的なチベット人の間で「よりによって異教徒の若い娘にたぶらかされるとは!」とすっかり顰蹙を かってしまったのだ。
インド政府も「国王は普段から酒に溺れている」「訪印した時にはガンジー首相との会談を断り、カルカッタの寺に逃げ込んでいた」と、パ ルデン王が統治能力に欠けていたことをアピールしていたが、国民投票では王制廃止の賛成票が97%に 達していた。
こうしてチベット人やレプチャ人からも見放されたパルデン王は、王国の存続を危んで一足先に国外脱出させた愛しきホープ妃が待つアメリ カへ渡ったが、国王でなくなればタダの田舎オヤジに過ぎないわけで、間もなく王妃からも見捨てられて78年に別居し、2年後には離婚。82年にニューヨー クで寂しく病死した。
ドルジェ首相
一 方、インド軍のシッキム侵攻を要請したというドルジェ首相は、チベットで僧侶をしていたこともあるチベット人で、インドとの併合後も79年までシッキム州 の首相を務めた後、「シッキム民主化の功労者」としてインド政府から勲章を授与された。その後はネパール人のバンダーリーが首相に就任し、15年間にわ たって政権を維持。ネパール語がシッキム州の公用語になるなど、ネパール化が公然と進んでいるようだ。
中国はもはやシッキムの宗主権は主張していないものの、インドによる併合をあくまで認めず、中国製の世界地図には錫金(シッキム)がずっと存在し続けていた。しかし21世紀に入って中国とインド は急速に関係改善が進んで、2003年には海軍の合同演習を実施。05年にはインドがチベットが中国領であることを改めて確認する代わりに、中国もインド のシッキム併合を認め、中印戦争以来閉鎖されていたシッキムとチベットとの国境貿易も06年から再開された。青海省からラサまで開通した鉄道を、シッキム 経由でコルカタ(カルカッタ)まで延長する計画もあるとかで、シッキムは再びチベットへの玄関口として脚光を浴びつつある。
ところで、シッキム併合の二の舞を恐れているのがブータンで、ブータンで もネパール人開拓民の移住が増えていた。そこで1989年に民族衣装の着用を義務付ける法律を制定。この民族衣装というのは「ゴ」という江戸時代の農民の 服みたいなものだが、ブータン人が住む北部の涼しい山間部ならともかく、ネパール人が多く住む南部のインド国境地帯では「暑いのにこんな服着ていられる か!」と多くのネパール人が難民となって逃げ出している。
1965年のシッキム王国と 国王
ネパール系インド人と社会運動 アジ研(ヤジ研ではない)の『アジアトレンド』に掲載された関口真理氏の論文
消えた王国 シッキム 2003年のシッキムの旅行記です
シッキム入国 2005年のシッキムの旅行記です
消 滅カントリーのQSLカード シッキム国王とアマチュア無線で交信した人に届いた手紙
「消 滅した国々」へ戻る