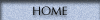 (目次に戻る)
(目次に戻る)
県歌—信濃の国<12.12.31記> 前回、群馬県の県民性を象徴する「
上毛かるた
」について紹介した。今回は長野県の県民性を象徴する「県歌・信濃の国」(以下「信濃の国」という)について紹介する。 僕は長野県の生まれだから、「信濃の国」はよく知っている。とはいっても歌えるという意味であって、「信濃の国」が作られた背景については最近になるまで全く知識がなかった。小学校の運動会などで歌い、県人会で必ず歌うものという程度の知識であった。
とにかく長野県人が集まると「信濃の国」をよく歌う。信濃の地理・産業・偉人などを詠み込んだ国自慢の歌だからである。県人会で歌えなければモグリではないかと疑われるほどだ。それほど県民に浸透している歌なのだ。 以下、信濃の国物語ともいうべく、長野県の分県騒動にまつわる伝説的な逸話を語る。 明治4年(1871)の廃藩置県で、信濃の国は筑摩県と長野県の二つが設置された。筑摩県とは松本・諏訪以南の南信地区、長野県とはそれより北の北信地区をいう。
明治9年(1876)、筑摩県庁が焼失した。これを機に明治政府は筑摩県を長野県に合併させてしまった。いわゆる吸収合併である。筑摩の県民は「何故だ」と叫んだに違いない。松本は地理的に信濃の国の中心である。ましてやシンボルの松本城がある…(もっとも長野には善光寺がある)。いずれにしても、このときから事あるごとに怨念の分県騒動が繰り返されることになった。 昭和23年(1948)、今度は県会議事堂が落成の翌日に焼け落ちた。この機を逃さずと南信側が決起した。分県問題は本会議に上程され決着をつけることになった。議場は南北対立の緊迫した空気に包まれる。当時、議員定数は北信・南信ともに30対30の同数であったが、このとき北信側の議長が病欠となり、南信側の副議長が議長席についた。このままでいけば分県成立と南信側は勝ちを確信したに違いない。29対29の可否同数であれば、議長裁決により可決となる筈だ。しかし議会事務局長から投票結果を聞いた副議長の顔色が変わった。北信側の3議員が白票を投じて29対26となり賛成が上回ったものの、可決には出席議員の過半数が必要であることを副議長は失念していたのである。結局は廃案となり、南信側はあえなく敗退した。 北信側には策士が多かったと思われる。傍聴席から溢れた反対派の県民に議場の外で信濃の国を歌わせたのである。それは採決とともに傍聴席にも伝染し大合唱になった。信濃一国主義への賛歌として利用され最後には同調して加わった南信側の議員もいたという。
このときの騒動の模様は、「信濃の国殺人事件−内田康夫」のプロローグに迫真の描写がなされているので、興味のある方はそちらも読んでいただきたい。 これ程の歌であれば、「信濃の国」は当然「県歌」だろうと思うのであるが、実はこの時点ではそうではなかった。「県歌」は別にあったのである。
最初に「長野県民歌」が制定されたのは昭和22年(1947)である。現憲法施行を記念して公募し制定されたのであるが、あまり歌われずに忘れ去られていた。
では、分県騒動にこれほど翻弄された「信濃の国」は、いったいどのようにして誕生したのであろうか。その経緯を語ろう。
明治31(1898)11月、教員団体である信濃教育会が、県民年を奮励するような唱歌を作ろうということになった。この委嘱を受けた委員の中の一人に、長野師範学校(現:信州大学教育学部)で音楽を教える教諭、依田弁之助がいた。依田は同じ教諭の浅井洌(きよし)に作詞を依頼した。
浅井は嘉永2年(1849)、松本藩士の子として生まれた。文武両道に優れ、国文を得意とする行動派だった。幕末に水戸浪士の信州通過を阻止する戦いや、長州征伐に出陣している。明治6年(1873)、松本の第一番小学校(後に開智学校)に教師として勤務、25歳の春である。この頃から和歌に勤しんでいる。その後自由民権運動が盛んになり、30歳前後は政治運動的な教育活動に身をおくことになる。政府を非難して70日の懲役刑を受けたこともあった。しかし、松本中学校(現深志高校)の教師になってからは国学研究に没頭する。このとき同僚の志賀重昂(しげたか)から地理学の影響を受けた。 明治19年(1886)、浅井は長野県尋常師範学校の教師として、漢学・国文・歴史を担当する。修学旅行などで生徒を引率し、各地をよく見聞したりもした。また、歌道に励み、七、五調の長歌を試作するようになった。教員学力試験の検定試験委員にもなって、歴史・地理の知識は更に深まる。「信濃名勝詞林」の編集に参画しことと、浅井の教え子、浜幸次郎の「信濃教育論」を読んで、地理・歴史がいかに郷土の固めになるかを痛感する。はからずも「信濃の国」作詞の下地が、このころに備わったのである。
話は元に戻る。浅井は、小学校唱歌を作りたいという依田の意を汲み取り、作詞に没頭した。 当時は明治27、28年の日清戦争のあとであり、学校の唱歌が軍歌を教材としていた時代である。これを憂いた師範学校長が、信濃教育界長でもあったので、いつまでも軍歌ばかり歌っているわけにはいかない。新たな唱歌を歌わせたいと考えたのである。同31年その意が依田から浅井に伝えられた。 作詞の要点は地理と歴史を取り入れた内容に重きを置いた。かつて長野県には十一藩の小藩と何百という峠により十州(8県)に接する地形であった。しかも全面積の76%が山林地帯で、林業と養蚕製糸業以外には産業に乏しい貧乏県だった。浅井は南信・北信の分裂を避けるために「信濃の国は一つ」という大原則に立って作詞に専念した。北信・南信のバランスを考慮したのはいうまでもない。そして長野県というフレーズを避け、一貫して信濃の国としたのである。 明治32年(1899)3月、作詞がほぼ出来たので依田に渡した。依田はあまりの長詩にあきれながらも作曲してみようといった。発表されたのは、6月。今でいうコンテスト方式と思われるが、6曲のうちの一つとして提出された。
しかし、結果は無残であった。師範の生徒に教えてみたが、その場限りで誰にも歌われなかった。それを聞いた浅井はがっかりした。 ところで依田弁之助は、かねてから青森師範学校の北村季晴(すえはる)に信州へ来ないかと声をかけていた。北村は東京音楽学校で2年後輩だった。北村は喜んだ。東京生まれの北村は、みちのくの暮らしが寂しかったのである。尊敬していた音楽学校初代校長の伊沢修二と、幹事の神津専三郎は共に信州の出身でもある。その信州にかねがね憧れを持っていたのである。
ここで北村の生い立ちについて語ろう。北村は明治5年(1872)、東京で生まれた。教育者の父がアメリカ人のヘボンと親交があった関係で、幼い頃からオルガンに接することができた。ヘボンの学校や教会に遊びに行って、いつでもオルガンを弾くことができたのである。やがてヘボンの勧めで明治学院に入る。ここでは島崎藤村とも仲良くなった。島崎がよく鹿鳴館のことを話すので見に行ったこともある。ここで、管弦楽や歌声を耳にした。一方、家の近くの田町では三味線や鼓の音と歌声を聞く。こうして、洋楽・邦楽・能楽など幅広く接する機会に恵まれたわけである。 明治20年(1887)、日本音楽会が設立された。これを機に従来の「音楽取調掛」を「東京音楽学校(現東京芸術大学)」と改称、北村にチャンスが到来する。父を説得し、恩あるヘボン校長に自分の思いを切々と打ち明けた。「音楽の道は、君のような天分のある人を望んでいる」とヘボンが励ましてくれた。受験は難なく合格し、明治22年9月から音楽学校の師範部に通学。北村18歳のときであった。
話を元に戻す。明治32年(1899)11月、北村は依田の後任として青森から長野師範に赴任した。依田は舎監でもあった浅井に、北村の下宿を探してくれるよう依頼した。それがきっかけで、北村は浅井と気が合い付き合いが始まる。 明治33年(1900)の正月、北村は「信濃の国」のことを知り、浅井に作曲を申し出た。そして郷土を歌いこんだ地理・歴史などの一つひとつを理解していく。理解するほどにこの詩に魅せられた。北村は作曲技法のすべてを駆使して、遂に歌曲として完成させた。
この年の4月、「信濃の国」を生徒に教えたところ、寄宿舎が俄然賑やかになった。どこでもこの歌を歌っているのである。浅井はびっくりした。自分の苦労した作詞が余すところなく生かされている。詩の七、五調が引き立って勇壮かつ軽快である。 この年の秋10月、師範学校の運動会で女子部生徒の遊戯用として発表された。郷土愛を掻き立てるのには格好の新曲だった。
やがて、学生達が教師として県下各地に散る。最新の“音楽教材”として「信濃の国」を赴任校に持込んだのである。「信濃の国」はたちまち県内に普及し、事実上の県歌として位置付けられた。
その後、昭和41年(1966)になって、県章やシンボルが制定されたときに、「信濃の国」も県歌にしようという気運が盛り上がった。そして、昭和43年(1968)5月20日県歌として公告された。
1998年2月、長野冬季オリンピックの開会式における、日本選手団の入場行進曲は「信濃の国」であった。テレビを見ていた「長野県人」の武者震いが見えるようだ。 (注釈):県外の人はあまり「信州人」とは言わない。あえて「長野県人」とした。 <参考文献> 「長野県史 通史編第7巻近代1」 編集者長野県 昭和63.3.31発行
(社)長野県史刊行会 | 「長野県史 近代資料編第2巻(1)政治・行政—県政」 編集者長野県
昭和56.10.31発行 (社)長野県史刊行会 | 「信州の教育と文化」 信州大学『信州の教育と文化』編集委員会編
1995.10.4発行 (株)郷土出版社 | | 「『信濃の国』物語」 著者 中村佐伝治 昭和53.10.10発行 信濃毎日新聞社 | | 「うたのいしぶみ」 著者 松尾健司 1977.5.25発行 (株)ゆまにて |
浅井洌はその後も一貫して信濃教育に専念し、功なり名遂げて昭和13年90歳で松本において永眠した。松本市の城山公園には次のような歌碑がある。 千々に身を 砕きて磨け ふたつなき
心の玉の 世をてらすまで
そして、松本市の信州スカイパーク陸上競技場入口には、巨大な「信濃の国」歌碑がある。昭和51年、長野県が100年を迎えるにあたり、県民毎戸10円・小中高の児童生徒ひとり1円づつの拠金により建てられたものである。

城山公園-歌碑 | 
信濃の国-歌碑 |
一方、北村季晴は明治34年2月、1年僅かの滞在の後、東京に戻り作曲活動に専念した。宝塚歌劇の「ドンブラコ」を作曲するなどの逸話も残し、59歳でこの世を去った。
<逸話>宣教医ヘボン博士James Curtis Hepburn(1815〜1911)
北村季晴の将来を決定づけたのは、安政6年(1859)に来日した宣教医ヘボン博士である。
ヘボンは日本語を勉強するため、お茶の水の学問所(現湯島聖堂)を訪ねて相談した。この相談に応じたのが、季晴の父で教育者の季林である。これが縁で二人は親しく交際した。季林は日本語を教える替わりに、英語を教えて欲しいと提案した。ヘボンも乗り気で、相互教授が始まる。二人とも30歳前後の研究熱心な年頃だったので、数年間でかなり上達した。
この勉強がきっかけで、ヘボンはローマ字を使用した日本で最初の本格的和英辞典『和英語林集成』を作り始め、慶応3年(1867)に上海で初版を印刷した。
一方、季林は向南学校という私塾を開いたが、専門の漢学よりも英語を希望する者が多くなった。そこで国学に加え、英学も教えることになった。 |
<関連サイト>
長野県公式オームページ
(目次に戻る)
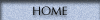
|