| 車両種類 | 内容 | 全通直後 | 茨城交通発足時 |
| 蒸気機関車 | 26トン級Cタンク | 2 | 1 |
| 蒸気機関車 | 30トン級Cタンク | - | 2 |
| 客車 | 2・3等客車(定員2等 8名/3等24名) | 2 | - |
| 客車 | 3等客車(定員50名) | - | 2 |
| 客車 | 3等客車(定員38名) | 4 | 4 |
| 貨車 | 有蓋・11トン | 12 | 12 |
| 貨車 | 有蓋緩急・11トン | 2 | 2 |
| 貨車 | 無蓋・12トン | 6 | 8 |
| 気動車 | 単車(定員40名) | - | 3 |
| 気動車 | 単車(定員50名) | - | 2 |
| 気動車 | 片ボギー車(定員60名) | - | 1 |
わずかこれだけ、と形容したくなるほど保有車両は少ない。茨城鉄道が需要をこの程度と想定していたことは重要である。また、全通後の増備は気動車以外ほとんどない。これは需要の伸びの鈍さを端的に示すものであり、さらに重要である。
もっとも、需要の小ささは、経営不振の原因とは必ずしもいえない。相応の運賃が設定できさえすれば、採算確保は可能である。従って、別の要因をも考えなければならない。
【仮説1’:価格転嫁力の過小】
茨城鉄道の開業した時点は、日本最初の鉄道開業以来、半世紀が経過していた。この時までに幹線鉄道網はほぼ完成されており、運賃設定には一定の「常識的水準」が存在していた。鉄道が各地で普及するにつれて、運賃水準は相対的に低廉なものになっていた。
需要旺盛な既存の幹線鉄道は、運賃設定をもリードしていた。そのため、需要が相対的に小さな後発のローカル鉄道は、不利な経営を強いられることになった。
茨城鉄道程度の需要であっても、明治の昔には高率の運賃水準を設定することで、充分な収入を確保できたはずである。しかし、昭和期においては「常識的水準」を大幅に逸脱する運賃設定は難しくなっていた。
さらにいえば、自動車業という有力な競合相手の出現により、運賃水準は抑制せざるをえなくなっていた。市場の独占性は失われ、高水準の運賃設定は利用者の逸走を招く懸念があった。茨城鉄道が競合自動車会社を買収したのは、市場の再独占を狙ったためと考えられる。もっとも、それでも経営が好転しなかった以上、根本的に需要過小であった可能性を指摘しなければならないが、千日手になるのでこれ以上の追求は避ける。
運賃設定に弾力性がない以上、昭和期のローカル鉄道は、収益的な路線からの内部補助を得られない限り、経営が成り立たない状況にあった。これは構造的な問題といえるが、この構造が明確に認識されていたとはいいにくい。しかし実態として、昭和期以降の新規の鉄道事業発起は激減する。たとえ構造が意識されなくとも、収入・支出ともある一定の精度で事前予測が可能になり、経営成立の見込みの薄い事業は具体化しにくくなっていたといえる。
【仮説1'':路線のロケーションの悪さ】
仮説1’は仮説1の是非に関わらない原因追究の深度化であるが、この仮説1''は仮説1を補強するものになる。
既に記したとおり、茨城鉄道は用地買収の困難に直面し、水戸市街への乗り入れを実現できなかった。この事実は、特に旅客需要の喚起において、ごく不利な要因であったことは争えない。同じように不利な線形を備える鉄道の例としては、越後交通長岡線がある。こちらは信濃川に架橋できず、長岡市街への乗り入れを果たせなかった。
合併により、茨城線と水浜線は上水戸での接続を果たした。しかし、乗換接続では必ずしも充分でなかったかもしれない。後年、茨城線と水浜線は直通運転を行うことになる。これは水浜線の延長運転という色彩が濃く、しかも直通区間はごく短かったため、茨城線の需要喚起につながらなかったものと考えられる。そもそも、上水戸接続にせよ直通運転にせよ、その実現が遅きに失した観もある。
上水戸接続をもっと早い時期に実現しておけば、さらには合併時点で石塚から水戸市街への直通列車を設定しておけば(これには直通用車両の確保という難問も残るが)、様相が大きく異なっていた可能性はある。
貨物輸送の面においても、上水戸が充分な立地であったかどうか。上水戸は水戸の中心部から 2kmほど離れている。現在でこそ市街地の一翼にとりこまれているものの、当時の感覚としてはかなり離れた場所といえるだろう。上水戸までのアクセスを考えるならば、最初から最後までトラックを雇った方がよい、と認識されていたかもしれない。
常磐線への接続は赤塚で行われていた。従って問題は、線内ローカル貨物の需要が充分に喚起できていたか、という点に絞られる。してみると、上水戸がターミナルであったという事実は、明らかに不利な要因である。砂利など大口荷主はともかくとして、小口荷主は茨城鉄道を利用する意志を持ちにくかった、と考えるのが妥当であろう。
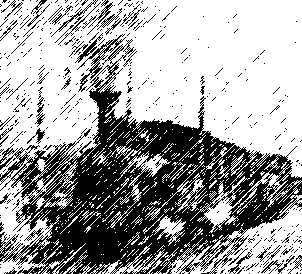
イラスト−3 上水戸駅を発車する貨物列車
【仮説2:過大な費用】
茨城鉄道は赤字決算を続けた。赤字累積のため、昭和15(1940)年に債務免除を受けたことは、既に記したとおりである。ここで注意が必要なのは、債務免除額が資本金の 8.4%でしかない点である。参考文献(01)に具体的な記述がないため推測になるが、債務免除額がこの水準ということは、茨城鉄道の建設に要した初期投資はほぼ全てが資本金により調達されていたと考えるべきであろう。
茨城鉄道沿線の資金力は、相応に豊富だったといえる。ただし、この観点からしても、茨城鉄道沿線の需要が過小であった可能性は残る。初期投資に借入金がないという前提を置いてもなお、充分な営業利益が出せなかった以上、よほど需要が少なかったと考えざるをえないからである。
鉄道事業の経営不振の現代的な典型は、総資本に占める債務比率過大、即ち利子が利子を呼ぶ財務構造に依拠する事例が多い。茨城鉄道は、これらとは様相が根本的に異なる。初期投資の償還に悩まされなかった分、幸せでもあったし恵まれてもいた。しかし、鉄道営業で利益が出なかったことは、決定的に不幸であった。
ここでは仮説1の対となる支出の過大を指摘したい。やはり具体的な記述は見られないが、状況証拠はいくつか認められる。
後年、茨城交通は茨城線の要員合理化を断行するが、路線の規模に対し整理される要員数が多いのである。しかも嘱託職員数が多い点、特異である。これは、茨城鉄道が冗員を多く抱えていたことを示唆する状況である。
勿論、時代背景として、各駅には駅長以下助役・信号係などを配置しなければならないといった、規則もしくは通念に縛られていた可能性はある。ただし、それにしても、嘱託職員数の多さは納得しにくい水準である。
もうひとつの高コスト要因として、施設の老朽化を挙げておきたい。開業当時の機関車はB6だったというから、疑う余地なく中古車であろう。また、各年次の決算報告に保守・修繕費の増嵩が頻繁に挙げられていることから、客車・貨車・レールをはじめとする主要施設の多くが中古車・中古品であった可能性を指摘しなければなるまい。参考文献(01)に明確な記述がないとはいえ、開業後の早い段階から保守・修繕費が重荷になっていた様子から、これら施設の大部分は開業当初から老朽化していたと推測できるのである。
【仮説3:一般論としての経営展望】
この仮設は、仮設1・2を全て包含する内容になる。
先にも記したとおり、茨城鉄道の計画発起は、日本初の鉄道が開業してから半世紀ほど経った時点である。半世紀という時間は、かなり長い。この間、良好な経営が期待できる新規の鉄道計画は、概ね出尽くしていたはずである。
茨城鉄道の計画が大正期まで具体化しなかった事実は、それまでの長い間、事業としての旨味を欠くと認識され続けていたことを暗示する。茨城鉄道の計画は、良好な経営展望を欠く条件下にあったからこそ、それまで具体化できなかったと考えるべきであろう。
■茨城鉄道の計画発起に隠されたもうひとつの意図
以上までの分析を、ある観点からここに整理しなおしてみる。 ・茨城鉄道の計画発起は恐慌発生と重なっており、景気動向はごく悪かった。
・茨城鉄道の計画は大正期まで具体化せず、良好な経営展望を欠く条件下にあった。
・上記の不利な状況に関わらず茨城鉄道の事業は発起され、かつ具体化した。
・茨城鉄道の建設費用は、ほぼ全て資本金により調達された形跡がある。
・茨城鉄道は、敢えて冗員を抱えていた可能性がある。
・「農村の病弊依然として深刻」という営業報告が見られる。
・茨城鉄道の債務免除はほぼ総額が受容された。
ここから先はまったくの推測である。堀江氏には、茨城鉄道を発起するにあたり、ある明確な意図を持っていたのではないだろうか。
おそらく堀江氏は、不況に直面し「病弊」に喘ぐ地域の現状を憂慮していたのである。地域に繁栄と安寧をもたらすための方策を思案していたのである。そして、これらを実現するための具体的な方法が、茨城鉄道であったのだろう。
初期段階においては、沿線富裕層から資本を糾合し、用地買収と建設工事を通じてこれを再配分する。中長期段階においては、鉄道事業の振興を図り、沿線の繁栄を喚起するとともに、多数の従業員を扶養する。より多くの人口を養うためには、冗員の雇用をも辞さなかった。・・・・・・
即ち、茨城鉄道は、一種の公共事業として具体化したのではないだろうか。
泉下の堀江氏には真意を尋ねようがないし、また、正史にかような記述はまったくない。単なる想像の域を出ないとの批判は免れえないだろう。しかし、状況証拠は数多く揃っており、堀江氏が救世済民の意図を持って茨城鉄道を興した可能性は否定できない。また、仮にその意図がなかったとしても、茨城鉄道の事業は救世済民を実現するように機能した。開業後の経営が不振に陥り、中長期的な安定を欠いた点は惜しかったものの、救世済民は半ばまで達成できたといえる。
今日、公共事業に対する批判が喧しい。これら批判のうち、中長期的展望を欠くという内容のものは相応に説得力を有する。なぜならば、財を再生産しない事業に投資しても、当面の雇用をつなぐ効果しか期待できず、中長期的な事業振興や雇用安定に結びつかないからである。しかし、最初から中長期的な展望がない事業と、中長期的に見ると結果的に失敗に終わった事業とを、同列に扱うわけにはいかない。これから実行すべき(すべきでない)事業の類型化と、失敗した原因及び責任の追求とは、分離して考慮しなければならない。
茨城鉄道の事業は、成功したとはいえない。しかし、その事業を遂行する過程のなかで、沿線地域の救世済民は半ばまで具現化した。惜しいことに、茨城鉄道は経営の安定を欠き、連年に渡り不振が続いた。だからこそ成功とは呼べないわけだが、あくまでもこれは結果論にすぎない。茨城鉄道が発起された真の理由については、さらなる詳細な検証を必要とするにせよ、発起人たる堀江氏の事績は相応に顕彰されてしかるべきであろう。
いささか余談にそれる。旧陸軍に属し、中国に駐留、数々の作戦に従事した経験を持つ方が、筆者にこう語ってくれたことがある。
「君は太平洋戦争がなぜ起きたか、知っているかね。その真の原因は、関東大震災にまでさかのぼらないと、理解することができないのだよ」
関東大震災により不況が助長され、多くの失業者が発生、これら失業者を救済するためにも中国大陸に進出しなければならなかったのだという。突飛な発想のように思えるが、あながち無茶な飛躍とはいえない。
以下は筆者の最近の感覚である。第一次世界大戦以降の社会現象は、鉄道事業はじめ、陸海軍の組織としての行動原理を含め、その多くは「雇用対策」の要素が加味されていたのではないか。この観点からの検証を加えないと、その時代(特に昭和初期)への理解を誤るのではないか。
茨城鉄道は、その尤なる事例であるかもしれない。あるいは、同時期に発起された鉄道計画の多くは、同様の性格を備えるものであったかもしれない。勿論これは、現時点では限られた史料の裏読みに基づく仮説にすぎない。たとえ遠い将来になっても、堅固な研究に基づく一文を残したいものではあるが、今のところは夢である。
■飛躍まじりの仮説
現在のところ根拠はまったく得られていないが、筆者は改正鉄道敷設法の社会的意義に関する解釈を変更すべきではないか、と強く直感している。批判を受けるのは承知でその仮説を記してみよう。まずは、茨城交通に関連して、事実を時系列で並べてみよう。
明治43(1910)年 軽便鉄道法公布
大正 7(1918)年 第一次世界大戦終結
大正 9(1920)年 最初の恐慌発生
大正10(1921)年 茨城鉄道の鉄道敷設特許取得
大正11(1922)年 改正鉄道敷設法公布
大正12(1923)年 茨城鉄道設立総会
関東大震災発生
大正15(1926)年 茨城鉄道赤塚−石塚間(16.6km)開業
まず、軽便鉄道法の社会的意義の解釈は、従来どおりのまま変更する必要はないだろう。即ち、鉄道事業への参入障壁を下げて、新規参入を促すというものである。これにより、ローカル鉄道の開業が相次いだのは紛れもない。そのなかには不採算の事業も多数あったはずで、参入障壁が緩和されてもなお、先行事業の経営実績が新規参入を躊躇させる一因となっていた可能性を指摘できる。
大正 7(1918)年以降は状況がやや変わる。第一次世界大戦の特需により景況が好転、市場規模が拡大したが、大戦終結により需要が一時にして冷えこんだ。市場には(あるいは見かけ上)潤沢な資金が供給されていたが、投資適格とされる事業が乏しく、梃子入れが必要だった。
そこで投資適格事業に設定されたのが鉄道だったのではないか。前述したような、民間資本の糾合→鉄道敷設による資本の再配分→鉄道事業の振興という、一種の投資モデルが構築されたのではないか。ただし、ローカル鉄道事業には事業不振に陥るおそれが伴う。その危険を緩和するセーフティ・ネットとして、改正鉄道敷設法が公布されたのではないか。
つまり、改正鉄道敷設法の意義のひとつとして、既開業の民営鉄道を国有化するという点を挙げられるのではないか。たとえ事業が失敗に帰したとしても、投資の一部なりとも回収できる仕組みをつくることにより、民間投資を喚起する方策が採られたのではないか。
前述したとおり、これは仮説であって確証ではない。しかしながら、個別事例をみるとその考えに行きつかざるをえない。例えば、別表57は飯山鉄道(のち国有化され飯山線)と河東鉄道(のち長野電鉄河東線)という2路線が包含されている。競合路線ともとれる鉄道が、それぞれ改正鉄道敷設法公布に先立ち免許を取得し開業に至っているという事実は、事業が失敗しても救いの手があることを示唆していると考えられないか。寿都鉄道・南部縦貫鉄道・善光寺白馬電鉄・北恵那電鉄・北丹鉄道など、経営状況が極めて悪いにも関わらずしぶとく営業を続けた(あるいは休止として免許を保持し続けた)路線がいくつもあるという事実は、国有化される期待があったからではないのか。
そしてこれは、茨城鉄道のちの茨城交通茨城線にもあてはまるのである。
■通史及び野史の見解
参考文献(02)では、茨城鉄道と改正鉄道敷設法との関連について、以下の見解を呈している。「茨城鉄道の計画が、大正 9(1920)年ころから、政友会所属代議士としての堀江正三郎を中心とし、地元有志によって企画されたという経緯をみれば、舞台裏をうかがうことは容易であろう。茨城鉄道の計画路線を、『鉄道敷設法』に付属する別表に記載されるよう工作したとみるのが自然と、筆者は判断する」
この見解は、「工作」との表現に見られるとおり読者にネガティブな印象を与えるものだが、「工作」の背景に対する言及は避けており、客観的記述に徹する意志を感じさせる。これは歴史書をつくるうえでの正当な姿勢といえる。
その一方、参考文献(04)には以下の記述が見られる。
「茨城鉄道の社長である堀江正三郎は、敷設法の大改正を推進した政友会の代議士であった。将来的には、施設を国に売却することで補償金を手に入れようとしたのでは、と私は邪推する」
まさに「邪推」と指摘されてもしかたない、論拠に欠ける批判といえよう。批判というよりもむしろ、誹謗に近い。ここが通史と野史の境界線、と評するのは酷かもしれないが、参考文献(06)とあわせ、JTBシリーズの限界をよく示す典型例ではある。
| このページは、2019年3月に保存されたアーカイブです。最新の内容ではない場合がありますのでご注意ください |