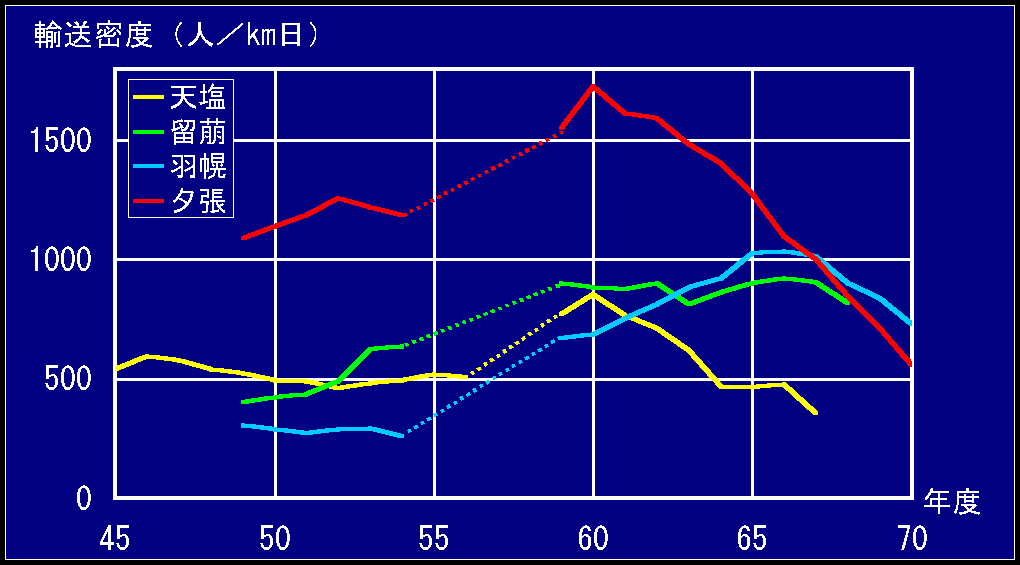
| このページは、2019年3月に保存されたアーカイブです。最新の内容ではない場合がありますのでご注意ください |
第5章 天鉄の営業成績
参考文献(01)には、景気の悪い文言が多いのが特色です。どのような会社であれ、苦難の時代はあるものですが、これほど苦難だらけの会社も珍しい。曰く。
「全般的に営業を開始したるも奥地炭礦は未だ開発途上にあり、本格的採炭に至らず」
「炭層の賦存状態は甚だ悪く大規模なる出炭は不可能」
「戦局は全面的に頽勢となり、国内の物資は不足し、人心は動揺し、為に炭礦の生産能率は減退し鉄道輸送亦不活発」
「炭礦の生産は終戦を境として不振の一途を辿り」
「生産は殆ど皆無の状態」
天塩礦の状況が想定よりもはるかに悪かったのが、最も痛いところでした。起業発起時の目論見では、生産量は45万トン/年。しかし実際には 5万トン/年程度もなかったようです。また、輸送先の人造石油留萠工場も、コバルトを触媒とする精製法を用いたため、触媒原料の確保難に伴い稼働も低調で、終戦と同時に閉鎖されてしまいました。
その当然なる帰結として、天塩炭輸送を需要の太宗として仰ぐ天鉄の経営は苦しくなり、「当社の営業も亦極度に逼迫し、幾度かの経営難に陥」るまでになってしまいました。
北炭は、生産量が少ない天塩礦の存続を諦め、昭和26(1951)年 3月に採掘を中止することを決めます。通常であれば、子会社である天鉄もまた営業廃止になるところでしょう。しかし、天鉄は屈しませんでした。
「地方鉄道の公共的使命を強く認識し、・・・・・・・・炭礦及び鉄道沿線一帯に亙る部落住民の死活問題にして、当社の進退は社会的にも波及するところ甚大なるに鑑み、自らの手にて炭礦を経営し、鉄道、炭礦の一本化により当社再建の方途を講ずることとなった」
天鉄は、北炭が諦めた炭礦経営に乗り出すことによって、自らの存続を賭けたのです。もとより天鉄は北炭の子会社ですから、炭礦経営のノウハウを有する役職員が多かったのかもしれません。それにしても、勇気ある決断だったといえます。
地上でどのような変化があろうとも、地下の炭層にまで影響が及ぶはずがありません。ところが、天塩礦の経営権が北炭から天鉄に移ったことで、生産量が目に見えて急増したから不思議なものです。人の和は、天の時及び地の利に関連しているのかもしれません。昭和31(1956)年10月には 9,300トン/月の産出量があり、参考文献(01)には「開礦以来の最高を記録」と特筆大書されています。
9,300トン/月が持つ意味は、当事者にはなにか格別の重みがあったのでしょう。天鉄の開業以前から常務取締役を務め、昭和22(1947)年から社長に就任し苦労を重ねてきた大西一男氏にとっては、ことに感慨深いものがあったに違いありません。
参考文献(01)「十五年史」はおそらく、谷ばかりだった天鉄の事業が上向いてきたことを記念し、さらなる発展を期す大西社長の意向により、編まれたものと想像されます。
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
とはいえ、しかしながら。
数字は冷酷非情に現実をあぶり出します。
天鉄及び天塩炭礦の業績は、確かに良くなったのでしょう。しかしそれは、創業当初の極めて不振だった時期と比べての話であって、絶対的な尺度で見れば、さして良好な数字が残されているとはいえません。
まず、旅客輸送密度の経年推移を図−3に示します。
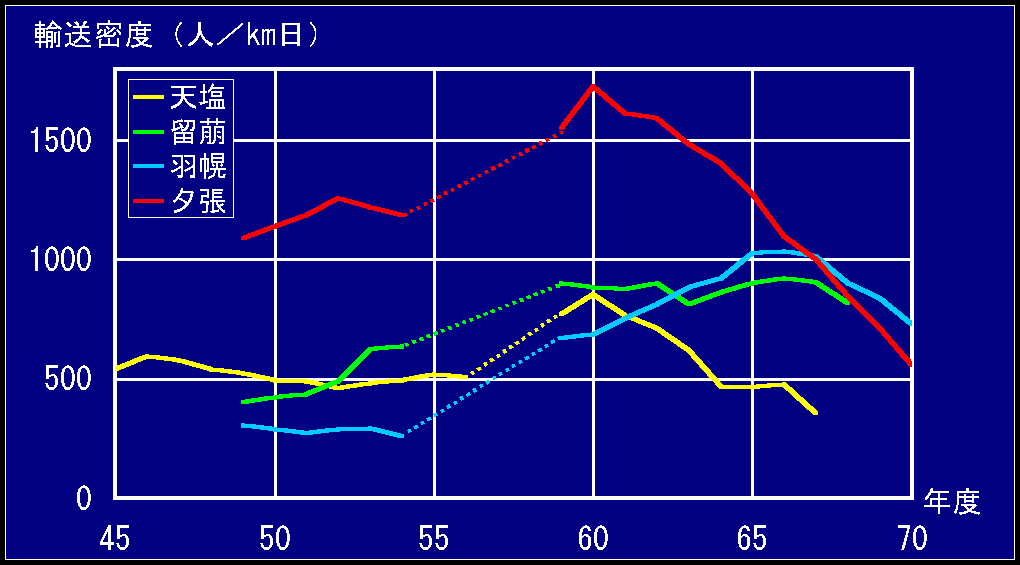
図−3 旅客輸送密度の経年推移
参考文献(05)に基づき作成。参考のため、留萠鉄道・羽幌炭礦鉄道・夕張鉄道のデータも併記した。
旅客輸送密度はいずれも低水準で特定地方交通線なみ、それもかなり低位の部類に属します。もっとも、旅客需要の少なさは礦山鉄道に共通する性格といえ、やむをえない面はあります。いくら沿線人口が多くとも、礦山の許での自給自足が基本であって、移動する需要がさほど多いわけではないからです。夕張鉄道の輸送密度が 1,500人/km日を越えているのは、むしろ驚異的な好成績と呼ぶべきなのでしょう。
それでも、天鉄は利用者の誘致に力を入れたようです。奥山様(承前)によると、留萠市内からの観光客を誘致するため、天鉄は本郷地区に桜を植え公園の整備を図り、さらに本郷公園駅を設置したとのことです。同様の事柄は天鉄バスの運転手も語っておりましたから、まず間違いないでしょう。
参考文献(01)に記述がないことから、本郷公園駅の設置は昭和32(1957)年の夏以降と思われます。筆者が現地を訪れる際に参照した、国土地理院地図にも記載されていました(いつ時点の版か手許に記録は残っていない)。少しでも業績を伸ばすための天鉄の努力がうかがえるエピソードといえます。
さて問題は、貨物輸送密度です。

図−4 貨物輸送密度の経年推移
天鉄の貨物輸送密度、これは少ない。あまりにも少なすぎる。ピークの昭和35(1960)年度でさえ 500トン/km日にすぎません。
この全数が天塩炭礦産の石炭と仮定して換算すると、18万トン/年になり、天塩炭礦の生産量は飛躍的に伸びたといえます。ところが、その輸送密度はわずか 500トン/km日でしかなく、性能の良い機関車があれば、1列車で運びきれてしまう量でしかないのです。天鉄の C58の性能及び勾配条件を考慮しても、2列車も仕立てれば充分に運べてしまうでしょう。この程度の輸送密度で鉄道経営を良好にするのは難しいと、いわざるをえません。
夕張鉄道と羽幌炭礦鉄道では、ピーク時の貨物輸送密度が 2,500トン/km日あり、これだけあればまずまず良好な収益を期待できそうです。留萠鉄道の 1,200トン/km日では、やや苦しいところかもしれません。ところが、天鉄には 500トン/km日しかありません。留萠鉄道と比べ半分以下、夕張鉄道・羽幌炭礦鉄道と比べれば5分の1しかないのです。どの鉄道も需要の根源は炭礦ですから、輸送密度の差はそのまま炭礦からの生産量の差といえます。生産量が他と比べ少ない天塩炭礦を戴く天鉄が、苦しい経営を強いられたのは当然でしょう。
しかも、天鉄には営業面での足枷をはめられていた形跡があります。参考文献(02)には、天鉄の業況紹介として次の記述があります。
「総じて鉄道業は、公共性をもつ関係から運賃の抑制をうけ、また施設、運行、保安面に監督官庁の干渉が多く、経営妙味の乏しいものとされているが、これに加えて冬期の除雪対策、夏期の一日四往復の運行を義務づけられる点から、依然として赤字を脱却しえない状況である」
どの記述にも興味深い点はあるのですが、夏期1日4往復の運行義務、という点は特に興味深い。誰がどのように義務づけたか詳しい記述はないものの、2往復でも間に合うのに4往復を運行しなければならないというのは、経営上かなり苦しいところです。
天鉄の運行本数は、昭和39(1964)年 8月時点でも同じく4往復(参考文献(06))あります。これは他の民鉄と比べ少ない水準なのですが、それでも輸送力過剰というあたりに、天鉄の厳しさがあるといえます。
25.4kmの路線、 135名の鉄道部門従業員、 3両の蒸気機関車、 6両の客車、29両の保有貨車、15両の借入貨車、 1両のラッセル車(昭和31(1956)年度末時点/参考文献(01))。これだけの資産を維持するためには、相応の収益を確保しなければなりません。天塩炭礦が全盛時の生産を続けたとしても、否、全盛時からさらに倍の生産量を挙げてさえ、天鉄は鉄道営業の維持ができたかどうか。
全盛期の 500トン/km日という輸送量は、道路事情さえよければ、10トンダンプを日に10台もチャーターすれば運べる量にすぎません。天鉄の運命を握る鍵は、エネルギー政策の方向というよりむしろ、沿線の道路整備の進捗だったといえるでしょう。
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
天鉄の廃止は、昭和42(1967)年 7月31日のこと。廃止に至った理由は、信頼に値する一次資料が皆無のため、よくわかりません。参考文献(11)などに記されている天塩炭礦の閉山という理由だけでは、説明しきれない面はあります。平成 3(1991)年に筆者が訪問した時点で、天塩炭礦の露天掘り部分はなお稼働していたからです。規模を縮小しながらも、天塩炭礦は命脈を保っていました。天鉄バスの運転手が語っていた、路線の維持管理に困難をきたしはじめていたことが、あるいは正しいのかもしれません。
ただ、いずれにしても、沿線の道路整備が進み、客貨ともにバス・トラックへの転換が容易にできる状況は整っていたのでしょう。
天鉄は興るべくして興り、消えるべくして消えた、といえそうです。
天鉄ばかりではありません。隆盛を誇った他の炭礦も、エネルギー政策の転換から次々と閉山され、石炭輸送を需要の太宗とする鉄道はことごとく消え去ったのです。
三菱美唄鉄道
三菱大夕張鉄道
夕張鉄道
北炭真谷地専用鉄道
三井芦別鉄道
羽幌炭礦鉄道
留萠鉄道
雄別炭礦鉄道
雄別鉄道
幌内線
万字線
白糠線
歌志内線
函館本線上砂川支線
:
:
:
大炭礦を戴く鉄道であろうとも、その大部分が昭和40年代のうちに消えたのです。天鉄が昭和42(1967)年まで営業を続けていたのは、あるいは奇跡に近い出来事だったのかもしれません。
| このページは、2019年3月に保存されたアーカイブです。最新の内容ではない場合がありますのでご注意ください |