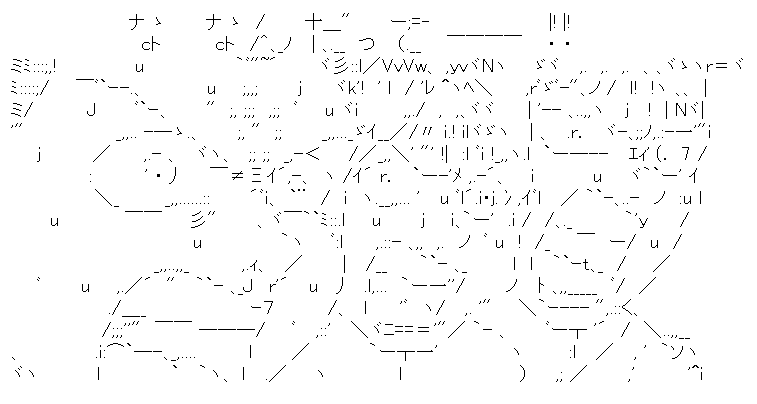私は今、 一人で佐々波さんの病室にいるんだ。 一応気晴らしにテレビをつけてはみたものの、 佐々波さんのふりをするために眼鏡を外しちゃったから、 ぼやけてあんまりよく見えないし、 だいいち、 腰を落ち着けて見る気分にはとてもなれなくて、 義体に接続されたコードをずるずる引きずりながらあっちへウロウロ、 こっちへウロウロ。
“八木橋さん。 そうやってあんまり落ち着き無く動かれると、 私、酔っちゃいそうでーす。 リラックスリラックス”
頭の中に、 タマちゃんの脳天気な声が響く。 その場にいない人の声が聞こえるっていうのは、 何だかとっても不思議な感じだ。 まるで自分がエスパーにでもなったみたいな気分だよ。
今、 私のサポートコンピューターは、 病室にある義体管理用のコンピューターを介して、 タマちゃんたちケアサポさんが常駐しているサポートセンターのメインコンピューターと直接繋がっている状態。 だから、 眼鏡をかけていない私の義眼に映し出されるぼやけた画像は、 サポートセンターにいるタマちゃんの眼の前のモニター画面にも転送されているし、 私が聴いた音もタマちゃんのつけているヘッドホンに筒抜け。 私が伝えようと思ったことは、 声に出さなくても、 タマちゃんには私の声として伝わるし、 タマちゃんがマイクに向って放った声は、 サポートコンピューターで、 あたかもその場にタマちゃんがいるみたいに、 音声に変換されて、 私に伝わるってわけ。
「うー、 無理だ。 リラックスなんてとても無理だよう」
ホントは口に出さなくても、 伝えようと思うだけで、 タマちゃんは音声データとして認識してくれるみたいなんだけど、 思念だけで物事を伝えるって行為に慣れていないから、 ついつい口を動かして膨れっ面で愚痴をこぼしてしまう。
私の聞くもの見るもの全てがタマちゃんに筒抜けなんて、 ただでさえ落ち着かない状態なのに、 その上、 佐々波さんのふりをして、 恋人と相談して、 男の義体にするか、 女の義体にするか決めるなんて、 人の人生にも関わる大事なことをまかされてしまって、 緊張するなっていうほうが無理だよ。 影でこっそりタマちゃんが行動を指示してくれるっていっても、 それを実行するのは私なんだからね。 自慢じゃないけど、 私はもともとプレッシャーに弱くて、 ボーリングをしたら、 スペアを取った後は必ずガーターになっちゃうくらいなんだよ。 普段は足が結構速いほうだったのに、 運動会になるとスタートで転んだりしたこともあるしね。 いくら機械の身体になったっていっても、 脳みそだけはもとのまんまだから、 この情けない性格は、 残念ながらちっとも直っていないんだ。
“うーん、 なんだかできの悪いビデオを見せられている気分でーす。 画像のピントは合ってないし、 視線があちこちさまよってゆらゆら揺れてるし”
タマちゃんは、 そんな私の気持ちなんかおかまいなしに、 相変わらず呑気な事を言っている。 視力0.1のぼやけた視界を延々見せられるタマちゃんには同情するけど、 少しは私の身にもなってほしいよね。
でも、 落ち着き無く佐々波さんの病室をウロウロ歩き回ったお陰で、 気がついたことがあるよ。
遊び心の欠片も感じられない、 無機質な白壁に囲まれた六畳ほどの大きさの部屋。 本当は今の身体には大して必要ではないけれど、 人間らしさを装うためだけに置いてあるベッドと枕と毛布。 私達を機械の身体だって自覚させるために置いてあるとしか思えない、 義体検査用の灰色のコンピューターとモニターディスプレイ。 佐々波さんの病室も、 私の病室も、 部屋の作りは全く一緒。
でもね。 一つだけ私の病室と違っているところがあるんだ。 私、 目が悪いから(ていうか自分からわざと、 近視になるように義眼の視力調整をしてるんだけどね)、 佐々波さんの病室に入ったときには気付かなかったんだけど、 よくよく見れば、 壁のあちこちに、 葉書くらいの大きさの小さな水彩画が、 丁寧に額に入れて飾ってあるんだ。 この部屋、 まるで、 小さな美術館みたい。
興味を惹かれた私は、 そうしないと見えないから、 鼻先を絵に触れるくらい近づけて、 小さな絵を、 一つ一つ眺めていった。
まるで燃えているみたいに、 山一面真っ赤に染まった紅葉、 今にも川魚に襲い掛かってやろうって羽根を振り上げた、 かわせみの雄姿、 小さな絵のそれぞれに自然の風景が生き生きと描かれていた。 本当に小さな絵だけど、 それがあるだけで、 この無彩色の、 機械の検査室にしか見えない義体患者用の病室だって、 暖かい自然の温もりに包まれているような、 そんな気さえしてきた。
「ずるい! なんで、 佐々波さんの部屋にだけ、 絵がこんなにたくさんあるのさ。 私の部屋にだって一つくらい欲しいよう」
ついタマちゃんに向って不平を漏らしてしまう私。
どうして、 佐々波さんの部屋にばかり、 こんなにたくさん絵があって、 私のところにはないんだろう。 これって、 患者差別だよ。 私はそう思ったんだ。 この絵は、 全部、 府南病院に最初からあったもの、 そう思い込んでいたからこそ、 タマちゃんに文句をつけたんだよ。
だから、 タマちゃんから、 この絵、 全部佐々波さんが描いたんだって聞かされて、 私、 びっくりしたよ。
“佐々波さん、 絵を描くのが大好きだって、 佐々波さんの恋人から聞いたから、 リハビリの一環で、 絵を描いてもらうことにしたのでーす。 私の前じゃ、 文句しか言わないくせに、 一晩たつと、 一枚絵ができてるの。 ホント素直じゃないよね”
そう言ってタマちゃんはくすくす笑った。
タマちゃんは、冗談めかして言ってるけど、 自殺を図って、 でも死に切れなくて、 そのうえ義体になってしまった佐々波さんを、 ここまで立ち直らせるのは、 並大抵の苦労じゃなかったはずだ。 それが、 ケアサポーターの仕事だものってタマちゃんは事も無げに言うかもしれないけど、 誰にでもできることじゃないよね。 私には、 すごいケアサポさんが付いてくれているんだって、 あらためて思ったよ。それから、佐々波さんについての認識も改めなきゃいけないね。こんな、プロ顔負けの素敵な絵を描くなんて、あなたは、ただのおなべさんじゃないんだね。
私は、 美術の成績がそれほど良かったわけじゃないし、 ましてや絵の良し悪しが分かるほどの知識もセンスもないよ。 けれど、 そんな私でも、 夏の砂浜を描いた絵から、 照りつける太陽のじりじりした暑さや、 むわっとした粘り気を帯びた海の匂いまで感じることができたんだ。 砂浜の真ん中にポツンと一つだけ描かれたビーチパラソルの作り出す真っ黒な日陰に思わず逃げ込みたくなったくらいだもの。 それから、草原を走る馬の絵は、 私が昔モンゴルで受けたような爽やかな乾いた風が、 私に向かって吹いてくるみたいだった。 私の機械の身体は、 もう季節の移り変わりを肌で感じることはできないけれど、 でも、 心で感じることはできるはずだよって、 佐々波さんの絵から教えられた気がしたんだ。
佐々波さんは、 自分のことをお人形さんだって言ってたけど、 決してそんなことないよ。 こんな風に、 自然の息遣いをそのまま絵にすることができるような人が、 機械のはずがないじゃないか。 佐々波さんの代わりに、 佐々波さんの書いた絵の一枚一枚が、 「オレは生きてるんだ」って叫んでるよ。 私には、 その声が聞えるよ。
佐々波さん、 もっと素直に自分の本心を口に出せばいいのに。 それは、 決して恥ずかしいことなんかじゃないよ。 馬鹿だね。 男ってホントに馬鹿だよね。
“八木橋さん、 心の準備はいいの? もう彼女、 来ちゃうよ”
タマちゃんにそう言われるまで、 私は、 そんなことを思いながらずーっと佐々波さんの絵を眺めていたんだ。
ノックの音に続いてドアがゆっくりと開かれる。 私は息をのんで、 病室の灰色のドアを見つめた。
部屋に入ってきたのは、 きちんとしたスーツに身を包んだすらっとした長身の女性。 年齢は、 二十台後半、 ちょうどタマちゃんと同じくらいだろうか。 美術館に置いてある彫刻を思わせるような、鼻筋の通った整った顔立ちの人だった。
彼女は、 テレビの前で間が抜けたように突っ立っている私を認めると、 なんだか思いつめたような固い表情で、 私のもとに歩み寄った。
「まだ、 その姿のままなのね・・・」
彼女はぽつりと独り言のようにつぶやくと、 そのまま彼女の意思の強さを表しているような大きな目で、 私のことをじっと見つめた。
私や佐々波さんが取りあえず入っているイソジマ電工製の標準義体の身長はちょうど160cm。 大きすぎず、 小さすぎず、 日本女性の平均値を取って、 この高さに設定してるんだって。 その私が、 ちょっと上目づかいにしなければ、 彼女の顔を見ることができないなんて、 ずいぶん大きな女の人だ。 私は、 佐々波さんみたいなおなべさんと付き合う女の子っていうのは、 小さくて可愛らしい女の子なんだろうなって勝手に思い込んでいたんだけど、 どうやら私の偏見だったみたい。 私の目の前で、 身じろぎもせず、 私のことをまっすぐ見つめている女性は、 凛々しくて、 カッコイイ。 大きな会社で、 バリバリ働いているキャリアウーマンなんだろうか、 と勝手に想像した。
彼女の名前は、 タチバナカズミ。 佐々波さんは、 彼女のことをカズミって呼んでいる。 それが、 さっきタマちゃんから仕入れた彼女についての予備知識。 でも、 私がカズミさんについて知っているのはそれだけ。 それ以外のことは何一つ知らない。 思わず、 はじめましてって言いそうになって、 私はあわてて言葉を飲み込んだ。
彼女も、 黙りこくって私を見つめるばかり。 私達の間に気まずい空気が漂った。
“タマちゃん、 どうすればいいの?”
なんて声をかけたらいいのか分からなくて、 たまらず、 ケアサポさんの控え室で、 この様子をじっくり見ているはずのタマちゃんに助けを求める。 もちろん、 実際には声なんか出してはいない。 有線通信とやらで、 この声は私とタマちゃんにしか聞えない仕組みなんだ。
だけど、 タマちゃんの指示が飛ぶ前に、 カズミさんが口を開いた。
「久しぶりね」
手を伸ばして、 私の頬っぺたをそっと撫でるカズミさん。
「手術のあと、 一回会ったっきりだもんね。 あとは、 何回ここに来ても、 あなたは会ってくれなかったよね」
カズミさんは、 そう言って、 寂しげに力なく微笑んだ。
「うー、 ごめんなさい」
佐々波さんのことなのに、 自分には関係ないことなのに、 私はなんだか自分自身が責められているような気になって、 胸が苦しくなった。 そして、 私は、 反射的に拳を握りしめて、 唇をかみ締めてしまう。 辛いとき、 何かに耐えなきゃいけないとき、 私が思わずしてしまう仕草だ。
それを見たカズミさんは、 いぶかしげに眉をひそめた。
“うーって言わないの! 何度言ったらわかるの?”
すかさず、 タマちゃんから、 突っ込まれる。
そうでした。 私は今、 身も心も佐々波さんになりきらなきゃいけないのでした。 でも、 姿かたちは佐々波さんそのものとはいえ、 心まではなかなか演じきれるものじゃない。 うっかりした隙に、 ついつい素の自分が出てしまう。 気をつけなきゃ、 と自分に言い聞かせる。
幸い、 カズミさんは、 目の前の義体に入っている人の正体が、 佐々波さんじゃないなんて気がつく様子はなかった。 ほっとすると同時に、 佐々波さんのふりをして、 カズミさんを騙しているっていう罪悪感に、 ちくりと胸が痛んだ。
「話は汀さんから聞きました。 女の身体のままでいるか、 男の身体に変えるか、 どちらか選ばないといけないんだって?」
カズミさんは、 相変わらず固い表情を崩さずに、 私に聞いた。
話がいきなり本題に入って思わず身を固くする私。
「そ、 そうなんだよ。 カズミは、 どうしたらいいと思う?」
慣れない男言葉で話すのは、 なんだか気恥ずかしい。 でも、 恥ずかしいとか言ってる場合じゃない。
佐々波さんが、 男の姿を選ぶべきなのか、 女の姿を選ぶべきなのか、 恋人であるカズミさんの意向を聞くこと。 それが、 意思のある操り人形としての私の役目なんだ。
カズミさんは、 佐々波さんに、 男と女と、 どっちになってほしいと思うんだろうか? 女の姿だったら、 佐々波さんが、 まだ生身の肉体を持っていた頃と中身はともかく外見だけは一緒になる。 きっと、 カズミさんにとっても馴染みのある姿だろう。 それとは逆に、 男の姿だったら、 いくら遺伝子解析をするとはいっても、 昔の佐々波さんとは、 かけ離れた姿格好になっちゃうのは間違いないよね。 でも、 佐々波さん自身は、 自分が男だと強く思っている。 そして、 意識は男なのに身体は女だっていうギャップにずーっと苦しみ続けてきたっていう。 そのことは、 佐々波さんの恋人であるカズミさんなら、 よく知っているはずなんだ。 どちらを選ぶにしても、 とても難しい問題。 でも、 必ずどちらかに決めなければいけないこと。 彼女は、 いったいどんな答えを出すんだろう?
私は、 彼女が口を開くのを、 ドキドキしながら、 今か今かと待ち構えた。 いや、 ホントは、 ドキドキするような心臓なんて、 もうないんだけどね。
でも、 カズミさんの答えは、 私が予想もしなかったものだった。
「どっちでも、 好きにすればいいよ。 だって、 もう、 私には関係ないことだもの・・・」
相変わらず、 寂しそうに微笑みながら、 カズミさんは、 初めて私から目をそらした。
「そ、 それって、 どういうことなの?」
あわてて聞き返す私。 ホントは、 「それって、どういうことなんだっ!」って男っぽく言わなきゃいけなかったのかもしれないけど、 カズミさんの予想外の返答に、 うろたえてしまって、 そこまで頭が回る余裕なんかあるわけない。 関係ないってどういうことなんだよう。 あなたたちは、 恋人同士のはずじゃないか。 そんな答えっておかしいよ。
私は、 大きく息を飲み込むと、 次の、 カズミさんの言葉を待った。
カズミさんは、 感情を極力表に出さないようにしているのか、 押し殺したような静かな声で、 でもきっぱりと言い切った。
「今日はね、 私、 あなたにお別れを言いにきたの」
「え?」
私は、 もう一度、 間が抜けた声で聞き返す。 カズミさんの言ったこと、 決して聞こえなかったわけじゃない。 ただ、 彼女の言うことが信じられなかったんだ。 信じたくなかったんだ。
カズミさんは、 続けた。
「お別れよ。 私、 もう疲れちゃった。 いくらあなたのことが好きでも、 あなたは、 私のこと、 まるで信じてくれないもの。 私、 あなたが、 こうして機械の身体になってしまって、 そのことで、 親からも見捨てられたって聞いてしまっていたから、 あなたが簡単に人を信じることができなくなってしまうのも無理ないと思ってた。 でも、 私なら、 あなたのことを変えられる、 変えてみせるって思ってたの。 だって、 私は、 あなたの身体のことなんか関係なく、 ずーっと、 あなたの心に惹かれていたんだもの。 昔から、 ずーっとね。 我侭で、 あまのじゃくで、 でも、 とても純粋な、 少年みたいな、 あなたが好きだったんだもの。 たとえ、 身体が機械になっても、 心があなたのままなら、 私はそれでよかったし、 あなたにも、 私の言うことなら伝わる。 私は、 そう思ってた。 でも、 それって私の傲慢で勝手な思い込みだったんだよね。 結局、 最後まで、私の言うことを信じてもらえなかったね」
カズミさんは、 そこまで一息で言うと、 くるりと後ろを向いた。
「あなたのこと、 今でも愛してる。 世界中の誰よりもすてきな男性だと思ってる。 あなたと知り合えて、 本当に楽しかったよ。 今まで、 ありがとね」
最後まで落ち着いた、 乱れの無い声だった。 でも、 そんな彼女の肩が小刻みに動いている。 私、 分かるよ。 きっと、 今、 カズミさんは、 泣きたいのを一生懸命こらえているに違いないんだ。
タマちゃん、 どうしよう。 私、 彼女に向かって何て答えたらいいんだろう。
佐々波さん、 この通信、 聞いてるの? あなたは、 本当にそれでいいの? 彼女を引き止めなくていいの? 私達、 全身義体の人間には、 普通の人と付き合う権利なんてない。 本気でそう思ってるの? そんな馬鹿な考え、 もうやめようよ!
佐々波さん、 あなたは、 私が想像もできないような、 辛い目に遭ってきたのかもしれないよ。 そして、 あんまり悲しいことがありすぎて、 自分のことを機械だって思ったほうがラクに生きれる、 そう思ってしまうようになっちゃったのかもしれないよ。 人を信じられなくなってしまうのも無理ないのかもしれないよ。
でもさ、 彼女のあなたを愛する気持ちは本物だよ。 そんなの、 私にだって分かる。 あなただって、 本当は気がついているはずだよ。 だったら、 もう一度、 人を信じてみようよ。 彼女の愛に応えてあげようよ。 自分がどんな姿になったとしても、 愛してもらえる。 今の私にとって、 こんな羨ましいことはないんだよ。
どこまでが自分の心の中で思ったことで、 どこからがタマちゃんや、 佐々波さんに伝えようとしたことなのか、 頭が混乱して、 なんだかよく分からなかった。
“そうか、 分かったよ。 じゃあ、元気でな”
唐突に頭の中に、 タマちゃんのつぶやきが響く。
“え?”
“八木橋さん。 聞こえなかったの? 正しい答えは 「そうか、 分かったよ。 じゃあ、 元気でな」 よ。 ハイ言って”
私は耳を疑った。 タマちゃんの言葉とは、 とても思えなかった。 そんなこと口にしたら、 この二人はホントに終わりになっちゃうじゃないか。
“なんで、 そんな悲しいこと言わなきゃいけないの? 私は、 嫌だよ。 絶対嫌だからね。 タマちゃんだって、 佐々波さんの本当の気持ちは知ってるはずじゃないか”
いくらタマちゃんでも、 そんなこと言うなんて、 許せない。 私はそう思った。 たかだか、 有線の通信で、 どこまで、 私の感情が伝わるか分からない。 でも、 電線を焼きらんばかりの強い怒りを、 この通信にはこめたつもりだった。
“うわ、 なにするの、 やめあせdfgyふじこlp;!!! “
突然、 タマちゃんの悲鳴を感知して、 私はうろたえた。 まさか、 私の怒りが通じたわけじゃないよね。
“どうしたの、 タマちゃん、 どうしたの? タマちゃん! タマちゃん!”
“・・・・・・”
私の呼びかけに、 なんの回答もない。 どうしよう。 タマちゃん、 いったい何があったんだよう。 一人ぼっちで、 この状況をどうやって切り抜けたらいいんだよう。 私分からないよ。
「じゃあ、 さようなら。 私の愛しい人。 いつまでも元気でね」
とうとう、 カズミさんは、 病室のドアノブに手をかけた
私は、 どうすることもできず、 彼女の後ろ姿を見つめるばかり。 ごめん、 タマちゃん。 佐々波さん。 やっぱり私じゃ、 なんの役にも立てなかったよ。
“待ってくれ!”
突然、 通信が回復した。 と思ったら、 タマちゃんじゃなかった。 その声は、 佐々波さん! 佐々波さん、 タマちゃんから無理やりマイクを奪い取ったんだね。
“佐々波さん? 今まで、 どこにいたの。 今までのやり取り、 全部知ってるの?”
“ずーっと聞いてたさ。 メ ガネザルが、 一人でオレの部屋にいたときからずーっとな。 そんなことはどうでもいいから、 待てってくれって言ってくれよ! は、 や 、く!”
「待ってくれ! ! !」
私は叫んだ。 目をつむって、 思いっきり。 部屋中の額縁をびりびり揺らすつもりで。
カズミさんが、 びくっとして立ち止まった。
“後ろからカズミを抱け、 思いっきりだ”
“あの、 私一応オンナなんですけど・・・”
“このさい、 そういうことは関係ないんだよ! は、 や、 く!”
“ふふふ、 佐々波さん。 やーっと、 その気になってくれたのね”
タマちゃんが、 突然通信に割り込んできたかと思うと嬉しそうに笑った。
“じゃあ、 八木橋さんの身体、 ちょっと貸しあげてね。 ごめんね八木橋さん。 はい、 いーち、 に、 さーん”
次の瞬間、 私の身体が自由を失って前のめりに倒れた。
(うわわわ!)
身体の力を失って倒れこむ私の眼の前に、 病室の床が、 まるで画像をどんどん拡大していくみたいに大きくなって迫ってくる。 いきなり身体が言うことを聞かなくなるなんて、 わけがわからない。
突然の事態に、 私は頭がパニックになって、 思わず悲鳴を上げた、 つもりだった。 でも、 喉の奥にあるスピーカーから声が出てくれない。 手も動かせないから、 身体をひねって受身を取るなんて器用な真似ができるはずもなく、 私はきれいに棒立ちの姿勢のまま倒れて、 したたかに鼻の頭を床にぶつけた。
重くて固いものを落としたときのような鈍い音が病室中に響いた。
(ぎゃっ!)
もしも生身の身体だったら、 きっと鼻血がどばどば出て、 床を血だらけにしちゃっただろう。 そのくらいの勢いで床に鼻っ柱をぶつけたんだ。 でも、 お陰様で、 今の私の身体はただの機械製品だから、 鼻血なんか流さないし、 たんこぶもできないし、 どんなに痛くたって涙もこぼれない。
けれど、 悲鳴の一つも上げられない、 腕一本動かせない身体のくせに、 床に鼻を打ちつけた瞬間の、 一瞬呼吸が止まっちゃうかと思うくらいの耐え難い痛みだけは、 しっかりと私の脳に伝えてくれた。 どうやら、 身体は動かせなくても、 感覚器官はしっかり働いているみたいだ。 全く、 ありがた迷惑な話だけどさ。
「れいじ君! 大丈夫?」
部屋を立ち去ろうとしていたカズミさんが、 身を翻して、 倒れた私に向かってあわてて駆け寄ってくるのが足音で分かった。
全然大丈夫じゃない。 うつぶせに床に倒れたまま、 1ミリたりとも身体を動かせないなんて、 大丈夫なわけがない。
“タマちゃん、 ひどいよ。 痛いじゃないかよう。 私の身体にいったい何をしたんだよう”
私の抗議に答えたのはタマちゃんじゃなくて佐々波さんだった。
“悪いな、 メガネザル。 ちょっとだけ、 お前の身体、 貸してくれ”
“なんだよう。 佐々波さん。 身体を貸すってどういうことなのさ”
“こういうことさ”
佐々波さんが、 そう言い終わるや、 「私」は立ち上がった。 ううん、 違う。 私は立ち上がろうとなんかしてない。 この身体が、 私の意志なんかおかまいなしに勝手に立ち上がったんだ。
なんなのこれは?
“佐々波さんのサポートコンピューターと、 八木橋さんの義体の神経系を接続してみたの。 義体のコントロール、 しばらく佐々波さんに貸してあげてね”
すかさずタマちゃんが、 情況説明してくれた。
つまり、 今、 私の義体を動かしてるのは、 佐々波さんってことだ。 私の意識は、 義体の隅っこに追いやられて、 何一つできず、 小さくなって、 ただじっと黙っているしかないってわけだね。 この義体のご主人様は、 私のはずなのにさ。
せっかく佐々波さんもその気になってくれたことだし、 ここは本人にまかせたほうが上手く事が運ぶのかもしれないよ。 そんなことは分かってる。 分かってるけどさ。 やっぱり自分の身体をアカの他人が好き勝手に動かされるのは面白くないよ。
膨れっ面で、 ふて腐れる私。 ま、 身体を召し上げられて意識だけの存在になっちゃった今の私に、 膨れっ面も何もないんだけどね。
「大丈夫だ。 なんともない」
佐々波さんは、 「私」の様子を心配そうに見守っているカズミさんを見上げた。 義体の感覚は、 私と 佐々波さんと二人で共有しているわけで、 今、 私が感知している、 近視のせいで輪郭のぼやけたカズミさんの顔の画像を、 当然、 佐々波さんも見ていることになる。
“うわ、 なんだこりゃ。 おい、 メガネザル。 ひでー目だな。 何も見えねーぞ“
案の定、 佐々波さん、 私に向かってぶつくさ不平を言った。
そりゃ、 そうだよ。 だって、 私の義眼の視力設定は左右とも0.1ないんだもの。 眼鏡をかけなきゃ、 何も見えないよ。
“私、 アンタのふりをするために、 わざわざ眼鏡を外したんだからね。 勝手に私の義体を使っておいて文句言わないでよ “
“分かったよ。 でも、 頭の中で、 ぶつくさ言われると集中できねーからこれ以上余計なことはしゃべるなよ“
これじゃ、 どっちがこの身体の持ち主か分からない。 でも、 まだ言い足りないことは山ほどあったけど、 佐々波さんの言う通り、 これを最後に私は黙ることにしたよ。 せっかくの二人だけの時間だもん、 私がでしゃばって邪魔したら悪いよね。 少しだけなら、 この身体、 佐々波さんの好きに使っていいよ。
「カズミ・・・ごめんなさい」
立ち上がった「私」は、 カズミさんに向かって、 深々と頭を下げた。
「どうしたの? いきなり」
カズミさんは、 ぽかんと口を目を大きく開いて「私」を見つめた。 漫画だったら、 はてなマークが、 カズミさんの頭上をぐるぐる回っているところだ。 カズミさん、 きっと、 いきなり謝られて、 戸惑っちゃってるんだ。
構わず「私」は続ける。
「オレはカズミを捨てて、 自殺しようとしました。 ごめんなさい。 それから、 こんな身体になってしまいました。 ごめんなさい。 カズミの優しさに甘えてずーっと我侭を言いたい放題だったかもしれません。 ごめんなさい。 カズミにも見捨てられるかと思ったから恐くて会えませんでした。 見捨てられるくらいなら、 自分から振ったことにしたほうがましだと思ってしまいました。 カズミを信じることができませんでした。 ごめんなさい。 本当にごめんなさい」
「私」は、 カズミさんに向かって頭を下げた。 ごめんなさいって言う度に、 何度も、 何度も。 ハタから見たら、 滑稽で馬鹿みたいに思えるくらいにね。
でも、 私には佐々波さんを笑うことなんてできないよ。
もしも、 もしもだよ。 そんなことゼッタイ考えたくないことだけど、 もしも、 おじいちゃんに、 お前は裕子じゃない。 ただの機械人形だって言われたとしたら、 私どうなっちゃってただろう? ホントなら、 一番自分のことを愛してくれるはずの家族に裏切られる。 そんな辛い経験をしたら、 誰も信じることができなくなっちゃうのも無理ないよ。 人と会うことが恐くなってしまうのも、 無理ないよ。
だから、 そんな苦しみを乗り越えて、 自分のしてきたことを振り返って素直な気持ちで謝ることのできる佐々波さんは、 すごいと思った。 身体は、 女の子なのかもしれないけど、 やっぱり男の人の強さを持っている人なんだ、 と思った。
ようやく顔を上げた「私」は、 今度は真っ直ぐカズミさんを見つめた。
カズミさんの瞳には、 もう、 さっきの戸惑いの色はなく、 真剣なまなざしで、 言葉の続きを待っていた。
「でも、 こんなオレを今でも愛してると言ってくれて、 ありがとう。 世界中の誰よりもすてきな男性だと思ってくれてありがとう。 だから、 オレも言うよ。 オレもカズミのことを世界中の誰よりもすてきな女性だと思っています。 だから、 カズミ! 行かないでくれ。 オレだって今でもオマエのことが・・・」
好きなんだ。
小さな声で、 つぶやく佐々波さん。 そんな声じゃ、 私にしか分からないよ。 ああ、 じれったいなあ。 この恥ずかしがりやめ!
“佐々波さん、 頑張れ。 もっと大きな声で言わなきゃ、 カズミさんに伝わらないよ“
黙って見守っていようと決めた私だけど、 佐々波さんに煮え切らない態度にじりじりしてついつい口出ししてしまう。
“うるせえ。 オマエが聞いてるから、 恥ずかしいんだよ。 いいから、 黙ってろよ“
佐々波さんは、 照れをかくすかのように、 ぶっきらぼうな調子で私に言った。 というか、 私に通信した。
あなたは男で、 私は女。 生まれついた心の性は違うけど、 でも、 同じ機械の身体を持つものどうし。 いわば、 同志ってやつだ。 今の私は、 ちっぽけな意識だけの存在かもしれないけど、 それでも、こうしてあなたのことを応援してるよ。 だから、 今のあなたは一人じゃない。 二人分の勇気があるはずだ。 機械の身体でだって幸せになれるっていう私の希望だって背負っているんだ。 頑張れ。
「え、 何、 よく聞こえなかったんだけど、 私のことがどうしたって?」
カズミさん、 いたずらっぽい微笑みを浮かべて、 しらばっくれる。 そのカズミさんの笑顔に勇気付けられたように、 「私」は顔を上げてゆっくりと、 一言、 一言かみ締めるように言った。
「オレは、 オマエのことが、好きなんだ!」
言葉と同時に佐々波さんは、 カズミさんを抱き寄せた。 と、 いっても、 カズミさんのほうが、 「私」より背が高いから、 どうしても「私」がカズミさんの胸に顔をうずめる形になって、 どうにも格好がつかない。
冷静に二人を観察している私は、 どうしてもそんな風に思っちゃうんだけど、 佐々波さんは必死だ。 今度は、 カズミさんの頭を、 壊れ物を抱くみたいにそっとつかんだ。 そして、 二人して、 しばらくの間、 じぃっと見詰め合ってる。
やがて、 カズミさんは、 目をつむった。
“ま、 まさか、 佐々波さん、 この私の身体で、 カズミさんにキスしようとしてるの? “
こんな時に声をかけたら悪いかなって思ったけど、 やっぱり聞いて確かめずにはいられない。
今、 義体を操ってるのは、 佐々波さんかもしれないけど、 義体の受ける身体感覚は私のサポートコンピューターにも入ってくる。 て、 いうことは、 佐々波さんがカズミさんとキスしたら、 その感触は、 寸分たがわず、 私にもフィードバックされちゃうってことなんだよ。 全く、 冗談じゃないよ。
前言撤回。私、この身体、佐々波さんの好きにつかっていいって思ったけど、やっぱり、キスはだめー!
確かに、 カズミさんは、 女の私から見ても綺麗で魅力的な人だとは思うよ。 でもさ、 私には、 そんな趣味なんてこれっぽっちもないんだからね。 キスするなら、 やっぱり男の人がいいよ。 ていうか、 女同士なんて気持ち悪いだけ。 できることなら、 今はそういうことはやめて欲しい。 そういうことは、 あとで、 二人っきりになってから、 ちゃんと自分の身体でして欲しい。
でも、 佐々波さんは、 私の言葉が聞こえているはずなのに、 まるで無視するんだ。 佐々波さんの頭の中には、 今この瞬間、 佐々波さんとカズミさんの二人きりしか、 いなくなっちゃってるんだね。 きっと。
「私」の唇が、 カズミさんの軟らかい唇に触れた。 もちろん、 いい大人同士。 それだけですむはずがない。 「私」はカズミさんの唇をひとしきりはげしく吸ったあと、 作り物の舌を、 カズミさんを求めて、 力強く彼女の口の中に入れる。 カズミさん、 うっとりした表情で目を閉じたまま、 「私」の動きに応える。 口の中で、 なんだか別の生き物が蠢いているみたい舌を絡ませあう二人。
おえー、 おえー。
すれ違い続けていた二人が、 お互いの本心を確かめ合った末に交わす激しい口付け。 きっと、 感動の場面だろうね。 外から見ていればね。 でも、 この場面に巻き込まれて、 女の子とディープキスする感覚まで強制的に共有しなければならない私にとっては、 迷惑以外の何者でもない。
それに、 ただ、 キスするだけだったらまだいいよ。 さっきから、 私の身体、 どんどん熱く火照ってきてる気がするんだよね。 あそこもなんだかむずむずするし・・・。 佐々波さん、 キスするだけならまだしも、欲情しちゃってるね。 機械の身体でも、 そういうことができるように作られているのは、 嬉しいことだし、 別に佐々波さんが一人で、 そういう気分になるのはかまわないんだけどさ、 私まで、 巻き込まないでほしいよね。 私まで変な気分になっちゃうじゃないかよう。 女の子とキスして、 しかも感じてるなんて、 私、 まるで変態になったみたいじゃないかよう!
「ふふっ。 れいじクン、 私の勝ちよ」
佐々波さんとカズミさんの二人にとっては至福の、 そして、 私にとっては苦痛以外の何物でもない、 長くて激しいオトナのキスを終えたあと、 カズミさんは、 まるで駆けっこ競争に勝ったおてんば少女みたいな勝気な笑顔を浮かべた。 激しいキスのせいで、 ちょっぴり剥げかかった口紅にもおかまいなし。 私、 カズミさんって、 もっと、 クールな人かと思っていたけど、 実は、 けっこう激しい性格なのね。 彼女のことが、 だんだん分かってきたよ。
それにしてもカズミさんの言う勝ちって、 いったい何のことだろう?
カズミさんの突然の一方的な勝利宣言にあっけに取られる私。 何か言おうとしかけて口を開きかけたまま固まってしまった佐々波さんだって、 きっと同じ気持ちのはず。
でも、 続いて彼女の口から飛び出した言葉は、 私たちをもっと驚かせるものだった。
「ここまでやらなきゃ、 キミは本気にならないって汀さんは言っていたけど、 本当に汀さんの言う通りになったわ。 ううん、 キスまでしてくれるなんて、 私の予想以上。 れいじクン、 ありがとね」
カズミさん、 今度は「私」のほっぺたに軽めのキス。 もちろん「私」は、 彼女にされるがまま。
つまり、 カズミさんが別れ話を切り出したのは、 タマちゃんの考え出した策略だってことだよね。 その話が本当なら、 私も佐々波さんも、 今までずーっとタマちゃんの手の平で踊っていただけってことになる。
“タ、 タマちゃん、 ホントなの?“
あわててタマちゃんを問いただす私。
すぐに、 例の有線通信で、 タマちゃんからの返事がくる。
“ありゃりゃ、 カズミさんばらしちゃったね。 でも、 八木橋さん。 しーっ。 今は黙って二人を見守りましょう“
私には、 ばつの悪そうな顔をしながら、 立てた人差し指を唇に当てているタマちゃんの姿がカンタンに想像できたよ。
面と向って、 カズミさんと会うことができない佐々波さんのために、 佐々波さんと同じ姿格好をしている私を身代わりにすることを考え出したり、 本当はカズミさんのことが好きなくせに、 本心をなかなか打ち明けることができない佐々波さんのお尻を叩くために、 カズミさんには、 あえて別れ話を切り出させたり、 私には、 「じゃあ、元気でな」なんて別れの言葉を言わせようとしたり、 森の子リスみたいな可愛らしい見かけによらず、 タマちゃんは策士だよね。 よくもまあ、 次から次へといろんな手を思いつくもんだ。
自分の義体を人に好き勝手に操られる。 それは、 確かに余り気分のいいものじゃない。 身体のコントロールを失って床に頭から落ちたときは本当に痛かったし、女どうしでキスをしたあげく、 自分の意思に反して身体が勝手に感じてしまうのも、 なんか悔しかった。
でもさ、 いくら、 担当患者を立ち直らせるためとはいえ、 私の義体を佐々波さんに使わせてみたり、 面会に来たカズミさんに嘘をつくようにお願いしたり、 そんなことが、 イソジマ電工のケアサポさんのマニュアルに載っているんだろうか? そんなはず、 ないよね。
全ては、 人を信じることができない佐々波さんの心を救うため、 そして、 たとえ機械の身体であっても、 普通の人と同じように恋していいんだって、 私に教えるために、 タマちゃんがマニュアルなんか関係なしに、 自分自身の頭で一生懸命考えて仕組んだことなんだ。 そう思ったら、 私、 タマちゃんのことを非難なんか、 できないよ。 タマちゃん、 あなたはすごい人です。 私は、 あなたを尊敬します。
「じゃあ、 お別れって言ったのは演技ってことか。 ひっでーな、 汀め」
佐々波さん、 口先では、 汀さんのこと、 ぶつくさ不平を言ってる。 けど、 心の中は、 私と同じ気持ちのはず。 その証拠に、 佐々波さんの口調からは怒りの色が全く感じられない。
「そう演技。 私には別れる気なんか、 これっぽっちもなかったんだから。 れいじ君に引き止められなかったらどうしよう、 どうしようって、 そればっかり考えて、 内心どきどきしてたの。 でも、 私は賭けに勝った。 君は、 私のこと、 引き止めてくれた。 嬉しかったよ」
カズミさんは照れたような、 はにかんだ笑みをみせた。
「でもね、 男の姿をとるか、 女の姿をとるか、 どっちでも好きにすればいいって言ったのは私の本心。 私ね、 安心したんだ。 ずいぶん久しぶりのキスだったけど、 そして、 その間に、 君の身体が、 こんなふうに見慣れない外見に変わってしまったけれど、 でも、 今こうして目を閉じて君とキスしてみたら、 やっぱりれいじ君は、 れいじ君で、 昔と何一つ変わってないってことが分かったの。 私、 君が、 どんな姿になっても大丈夫だから。 だから、 自分の身体のことは、 そして自分の人生のことは、 ちゃんと自分で決めましょう。 ね?」
まるで子供にでも諭すみたいに、 優しく「私」に声をかけるカズミさん、 なんだか、 私には天使のように見えたんだ。 カズミさん。 ありがとう。 生身の肉体を失って、 機械の身体になってしまった私達にとって、 昔と何一つ変わっていないって言ってもらえることほど、 嬉しいことはないよ。 ねえ、 佐々波さん、 そうだよね。
佐々波さんが静かに口を開く。
「オレ、 今までいろいろ我侭なことを言って、 カズミを困らせてきた。 だから、 どうせなら、 ついでにもう一つだけ、 我侭を言わせてもらえないか?」
佐々波さんが、 どんな表情をしているのか、 今の私には見ることができない。 でも、 同じ身体を共有している私には、 肩に必要以上に力が入って、 コチコチに緊張している様子がまるで自分のことのように伝わってきた。 佐々波さんが、 ただのわがままじゃない、 何かとても大事なことを言おうとしているのが、 痛いほど伝わってきた。
秒針のコチコチ時を刻む音がうるさく感じられるくらい、 静かな一瞬ののち、 佐々波さんは言葉を続けた。
「なあ、 カズミ。 これからの人生、 二人で生きて、 二人で決めるっていうわけには、 いかないだろうか?」
「ちょ・・・それって」
佐々波さんの言葉にうろたえるカズミさん。 いや、 うろたえたのは、 カズミさんだけじゃない。 私だってそう。 そして、 私には、 タマちゃんが、 ごくりと唾を飲み込む音が聞こえた。 ケアサポセンターで、 この様子の一部始終を冷静に見守っているはずの、 タマちゃんでさえ、 どきどきしている。
二人で生きて、 二人で決める。 その言葉の意味するものは、 一つしかないよ。
「今すぐにとは、 言わないよ。 オレ、 頑張って、 もっとカズミに相応しい男になる。 その時は、 オレと・・・」
佐々波さん、 そこで また、 一呼吸置いた。 カズミさんは、 身じろぎ一つせず、 真っ直ぐ「私」を見つめながら、 次の言葉を待っている。
「結婚してください!」
言っちゃった。 佐々波さん、 とうとう言っちゃったよ。
「返事の前に一つだけ聞かせて。 れいじ君、 自分で何言ってるか分かってる? 同じ性別同士じゃ、 結婚できないんだよ?」
佐々波さんのプロポーズを、 まるで自分のことのように浮かれて聞いていた私だけど、 当事者のカズミさんは、 私なんかよりずっと冷静だった。
よく考えたら、 カズミさんの疑問は、 もっともだよね。 外国では、 同じ性の人どうしが結婚した、 なんて話も聞くけど、 ここは日本だもの。 佐々波さんが、 いくら心は男だって主張しても、 そして、 たとえ、 今の佐々波さんが、 肉体を失って心だけの存在だったとしても、 戸籍上はあくまでも女。 日本では法律上、 女どうしの結婚は認められていないはずだよ。 前、 ニュースの特集で、 私そんな話を聞いたことがあるもん。
だから、 佐々波さんが、 カズミさんと合法的に結婚する手段はただ一つ。 義体換装のときに男の義体に入って性転換するしかない。 いくら、 心の性と一致する身体になるっていっても、 生身の頃の自分と全く違う姿になるのは、 勇気がいることに違いないよね。
「一度決めたら、 もう身体を交換することはできないって汀さんは言ってたよ。 あなたは後悔しないの?あなたにその覚悟はあるの?」
カズミさんの口調はあくまでも厳しい。 けど、 それは当然のことだ。
義体換装は一度きり。 その結果が、 もし、 気に食わなくても、 後悔しても、 二度目はない。 ずーっと、 その身体で生き続けなければいけない。 自分の愛する人が、 この先ずっと後悔しながら生きていくのをそばで見続けていくのは、 カズミさんにとっても辛いことに違いないもの。
でも、 佐々波さん、 男らしかった。
「もう男として、 覚悟は決めた。 後悔なんか、 しない。 カズミと一緒なら、 どんな苦しいことも乗り越えて行ける気がする。 オレ、 一生お前のことを大事にするよ」
なんの迷いもなく、 そうやってきっぱりと言ってのけたんだ。 格好よかったよ。
佐々波さんの固い決意を聞いたカズミさんの頬がうっすらと桜色に染まる。 そして、 照れを隠すかのように、 にっこり笑いながら「私」のおでこを指でピンってはじいたんだ。
「わがままで、 あまのじゃくで、 自分勝手な甘えんぼさん。 私、 そんな、 あなたのどこに惹かれちゃったんだろうね。 ははは」
カズミさんは、 口ではそんなことを言いながら、 なんだかとても嬉しそう。 そうだよね、 好きな人から一生、 お前のことを大切にするって言われて、 嬉しくない女の人なんていないよね。
「だけど、 私、 れいじ君のことよーく知ってる。 れいじ君は、 嘘だけはつける人じゃない。 私、 あなたを信じます」
大きな眼をめいっぱい細めて微笑むカズミさんの瞳から、 涙が一筋ぽつりと流れ落ちた。
「じゃあ返事は?」
恐る恐るカズミさんの顔を上目遣いに覗き込む佐々波さん。
「もちOKよ。 だから、 一生大事にしてね」
カズミさんは、 薄緑色のハンカチで涙をふくと、 満面の笑みを浮かべながら言った。
「や、 や、 やったぁ!」
佐々波さんの上ずった叫び声。
“やった、 やった!“
これは、 私の声。 もう遠慮なんかしなくていいよね。 思いっきり、 祝福してあげるよ。 佐々波さんの頭が割れちゃうくらいの大声でね。 嫌っていってもやめてやらないんだから。
“佐々波さん、 おめでとう “
タマちゃんも心なしか涙声だ。 自殺未遂の末に全身義体になってしまい、 両親にも見捨てられた性同一性障害者。 彼女、 ううん、 彼の面倒をずーっと見続けてきた、 タマちゃんの苦労は、 きっと私なんかじゃ計り知れないくらい大きなものだっただろう。
おめでとう。 タマちゃん。 タマちゃんの苦労も報われたね。
“ははっ。 やったぞ。 オレは、 やったぞおー。 おーいメガネザル、 聞いてるか? 汀、 聞いてるか?“
“聞いてるよ。 佐々波さん、 よかったね。 本当によかったね“
おめでとう。 そして、 私に勇気をくれてありがとう。
「やった、 やった、 やった」
興奮の余り、 握り締めた両拳を無意味に上げ下げして、 ダンスを踊るみたいに身体をくるくる回しながら、 病室を彷徨う佐々波さん。 完全に我を忘れて、 舞い上がっちゃって、 さすがのカズミさんも、 呆れ顔。 そして、 とうとう、 病室に置いてある灰色のコンピューターとぶつかって・・・。
プツン!
義体とコンピューターを繋いでいたコードが抜けちゃった。 同時に、 全身からすうっと力が抜けて、 またさっきみたいに転びそうになった。 あわてて、 傍らのベッドにしがみつく私。
あ、 今、 私、 自分の意思で身体を動かしたよ。
試しに、 両手を握ったり、 開いたりしてみる。 動く、 私の思い通りに身体が動く。 コードが抜けた拍子に、 義体とケアサポセンターとの回線が切れちゃったんだ。
“タマちゃん、 佐々波さん、 聞える? “
さっきみたいに、 二人に呼びかけてみる。 でも、 何の答えも返ってこない。 身体が、 自分の思い通りに動くようになったのは嬉しいけど、 よりによって、 こんな時に・・・。 どうしよう。
私は、 ちらりとカズミさんのほうを振り返った。
「じゃ、 お祝いに、 もう一回、 キスしよっか?」
私と目を合わせたカズミさん、 どんと来いと言わんばかりに両手を広げる。 ああ、 案の定こうなった。
でも、 せっかく、 ここまでうまく事が運んだんだ。 今更、 私が、 キスなんてできません、 なんて興ざめなことを言って場の雰囲気を台無しにするわけにはいかないよね。 やっぱり・・・orz
「うー」
私は、 重い腰を上げて、 よろよろとした足取りで、 カズミさんに近づいた。
(ごめん、 武田。 私だって、 したくてするんじゃないんだ。 許してね)
心の中で、 何度も何度も武田に謝る。 私が、 誰か他の人とキスしたなんて知ったら、 あいつ、 いったいどんな顔するだろう。 しかも相手は、 男じゃなくて、 女。 そりゃあ、 怒るに決まってるよね。
カズミさんに、 くるまれるように抱きつかれた私は、 目をぎゅっとつぶって、 かすかに震えながら、 カズミさんの頬っぺたに軽くキス。 今の私じゃ、 これが精一杯だよ。
「何それ? なんの真似?」
カズミさんは、 あからさまに、 不満顔だ。
「どうしたの。 もっと積極的にいきましょ」
そう言って、 色っぽいしぐさで髪を掻き揚げながら微笑んだかと思うと、 強い力で私を抱きしめる。 そして、 激しいキス。 私は無理やりといった感じで口をこじ空けられて、 舌を入れられた。
(ひいっ!)
声にならない悲鳴を上げる私。 当然のことながら、 誰にも伝わらない。
カズミさんの要求はキスだけじゃなかった。 キスなんて、 ほんの序の口だったんだ。 カズミさん、 激しいキスをしながらも、 右手をそろそろと、 下のほうに伸ばして、 私のあそこを、 服の上からそっと指で撫で付けたんだ。
「ぁっ」
カズミさんの腕の中で、 ひくんと身体が震えた。 あそこを軽く、 掃くような指使いで撫でられる。 ただ、 それだけで、 思わずしゃがみこんじゃいそうなくらい鋭い快感が、 私の身体を突き抜けた。
今の、 私の身体が受け取る快楽は、 一見、 生身の頃とそっくり忠実に再現されているように思えるけれど、 所詮は、 作り物の擬似的なデジタル信号にすぎない。 タネを明かせば、 義体のいろんなところが受け取ったデジタル信号を、 サポートコンピューターが、 生身の身体の感覚に似せた信号に作り変えて、 私の脳みそを騙しているだけなんだ。 でも、 そんなこと分かってるけど、 生身の身体に限りなく近い、 この感覚、 私は好き。 性感っていうのは、 人間が当たり前のように持っている感覚のほとんど全てを失ってしまった私にとって、 残された数少ない人間らしい感覚だからね。 まあ、 そんな知ったかぶりをするほど、 昔の身体で経験しているわけじゃないんだけどさ。
でも、 いくら好きっていったって、 時と場合によりけりだよ。 こんなふうに、 女の人にあそこを撫でられてまでして、 感じたりしたくはないよ。 私は至ってノーマルな嗜好なんだからね。 そんな趣味ないんだからね。 きっと、 佐々波さんのせいだ。 さっきのキスの時、 佐々波さんが、 感じまくっていたせいで、 身体に余韻が残っちゃったんだよう。
「れいじ君、 可愛いよ」
私の反応に満足げな笑みを浮かべたカズミさん、 長いキスを終えると、 今度は私の耳を口にぱくっと加えた。 その間中右手は休まずに、 ちろちろちろちろ蠢き続けて、 私に絶え間なく快楽を送り続ける。
「カ、 カズミ。 い、 今は、 やめとこうよ。 あとで、 時間があるとき、 じっくりとしよ・・・!!!ぅ」
私の力ない声は、 カズミさんに、 着衣ごしに軽くクリをなでられただけで、 カンタンにかき消されてしまった。
「れいじ君。 もう、 濡れてきたよ。 感じやすいのは身体が変わっても、 もとのまんま」
嬉しそうなカズミさん。
セックスの時は、 きっとおなべの佐々波さんがカズミさんを攻めているんだろうなあって、 私は勝手に妄想していたんだけど、 どうも様子が違うみたい。 二人のセックスは、 どっちかというと、 カズミさんが攻めで、 佐々波さんは、 カズミさんの腕の中であえぎっぱなしなんだろうか。 まるで、 今の私みたいにね。
って違ーう。 私、 こんなことされてる場合じゃない。 犯される。 このままだと私、 カズミさんに犯されちゃうよ。 でも、 だからといってカズミさんを突き飛ばして逃げるわけにもいかない。 私、 どうすればいいんだよう。 なんでいつもいつも、 こうなっちゃうんだよう!
コンコン!
いきなりのノックの音に、 あわてて私から離れるカズミさん。
遠慮がちにドアが開かれて、 見慣れた巻き毛の女性がドアの隙間から顔をのぞかせる。
「タマちゃん!」
救いの神の登場に、私は佐々波さんを演じなければいけないことも忘れて、 つい、 いつもの調子で叫んでしまった。
タマちゃんが、 私に向って、 パチリとウインク。
(た、助かったぁ)
ほっとしたら、 力が抜けて、 私は膝から床に崩れ落ちてしまった。
タマちゃんのはからいで、 私はうまく病室を抜け出して、 佐々波さんと入れ替わる。 その後、 タマちゃんを交えて佐々波さんとカズミさんが話し合った結果、 佐々波さんの義体換装手術は一週間後、 私と同時に行うことに決まったんだって。
こうして、 佐々波さんと、 カズミさんの面会は、 タマちゃんの目論見どおり、 いや、 目論見以上の成果を上げて終わったのでした。
そして、 三人が話し合っている間、 放っておかれた私は、 中途半端に火をつけられた身体を持て余したあげく、 自分の病室に戻って、 一人寂しく身体を慰めたのでした。 とほほ・・・。
佐々波さんとカズミさんの面会から、 一週間が過ぎた。
今、 私は義体換装手術の真っ最中。 私の脳みそは、 今頃きっと、 慣れ親しんだ標準義体から切り離されて、 新しい義体へ移されるのを待っているところだろう。
義体換装手術なんて言っちゃうと、 どうしても大掛かりな手術を想像しがちだけど、 吉澤センセイに言わせると、 実は、 たいした手間じゃないそうだ。 作業としては、 標準義体から、 硬いケースに包まれた脳みそと、 脳みそを生かしておくための生命維持装置だけを取り出して、 新しい義体に移植するだけ。 しかも、 脳ケースも、 生命維持装置も、 義体の分解検査をする時とか、 今回みたいに義体を換装する時に便利なように、 ユニット化されて、 カンタンに取り外したり取り付けたりできる仕組みになっているんだって。
「手術自体は接続チェックも含めて30分くらいで終わっちゃうよ」
吉澤センセイは、 こわごわ手術室に入ってきた私に向かって、 こともなげにそう言った。
確かに、 センセイの言うとおり、 換装手術自体は、 たかだか30分程度のカンタンな作業なんだろう。 でも、 短い時間とはいえ、 義体から引き剥がされて、 眼も見えず、 耳も聞こえず、 身体の感覚すら失った状態で過ごすことが、 こんなにも苦しくて、 恐ろしいことだなんて、 私は知らなかったよ。
生身の肉体の全てを失って、 今の私に残されたのは脳みそだけ。 義体化手術が終わって目覚めたあとで、 吉澤センセイから、 そう聞かされても、 私、 イマイチ実感が湧かなかったんだ。
だって、 私には、 機械仕掛けの代用品とはいえ、 見た目も肌触りも、 生身の身体と何ら変わりのない、 自分の思い通りに動く手足が与えられていて、 眼もちゃんと見えるし、 耳も聞えるんだもの。 失われてしまった感覚も多いけれど、 日常生活をするうえで、 不便だって感じることはないんだもの。
だから、 手術台に寝かされて、 タマちゃんから
「今から、 サポートコンピューターと脳の接続を切るからね。 覚悟はいい?」
って聞かれた時にも、 まだ、 それが何を意味するのかよく分かっていなかったんだ。 ちょっと身動きがとれなくなる程度のことで「覚悟はいい?」なんてずいぶん大げさなことを言うなあ、 なんて、 のん気に思っただけだった。
でも、 いざ、 義体の電源を落とされて、 サポートコンピューターと脳の接続を断ち切られて、 はじめて、 タマちゃんの言っていた「覚悟」っていう言葉の意味が、 分かった。
生身の部分なんて脳しか残されていない今の私にとって、 身体感覚っていうのは全部、 義体のセンサーが受け取った電気信号が、 サポートコンピューターを経由して、 脳にもたらされている擬似的なもの。 だから、 サポートコンピューターと脳の接続を切られるってことは、 身体の感覚を全て失ってしまうことなんだ。 視覚も、 聴覚も、 触覚も、 何もかも全て。
ただ目をつぶっただけなら、 まぶた越しにうっすら光の存在を感じることができるし、 どんな闇夜でも、 星だけは明るく輝いているよね。 光が決して届くことのない、 深い深い海の底にだって、 明るい輝きを放つ生き物がいるっていうよ。
でも、 今、 私が閉じ込められている世界は、そんな生易しいところじゃない。 暗闇にたとえることすら、 生ぬるく感じる。 これは、 そう、 無だ。 宇宙が生まれる前の、 虚無の世界に自分の意識だけがぽつんと漂っている、 そんな感じだ。
(嫌だ。 何なのこれ。 タマちゃん、 助けてよう! 誰か、 助けてよう!)
はじめ、 私は、 気が狂ったように、 喚き続けた。 でも、 すぐに、 どんなに泣き喚いたところで、 私の声は闇の中に消えていくだけで、 誰にも届きっこない、 助けなんか、 来るはずがないってことに気がつく。 今の私にできることは、 「覚悟」を決めて、 この、 光も、 音も、 上下の区別すらない、 脱獄不可能な魂の牢獄の中で、 無の恐怖に怯えながら、 ひたすらじっと耐えることだけなんだ。
義体のお陰で、 普段は何の不自由もなく身体を動かしている私だけど、 ホントの自分は機械の助けがなければ何一つできない、 赤ん坊より無力なただの脳みその固まりにすぎないってことを嫌というほど思い知らされてしまった。
一体、 どれくらい、 時間が過ぎたんだろう。
虚無の世界に、 唐突に白い英語の文字が浮かび上がった。 アルファベットと数字の羅列は、 まるで、 映画館の巨大なスクリーンで洋画のタイトルロールを見ているみたいに、 真っ黒な空間を埋め尽くして、 下から上に向って、 流れていく。
きっと、 これ、 サポートコンピューターの立ち上げ画面に違いない。 立ち上げ画面を私の脳が見ている、 というか、 感知しているんだ。 やっと、 私の脳が、 サポートコンピューターと繋がったんだ。
何が書いてあるのかは、 さっぱり理解できなかったけど、 それでも、 私は、 この世界から逃げ出すための蜘蛛の糸が天から降りてきたように感じていた。 どんなつまらない、 意味のないものでも、 何かを感知できるっていうだけで、 今までの虚無の世界に較べたらどれだけましか分からないよ。
しばらく、 ぼんやりと、 次から次へと現れては消えて行くアルファベットを、 眺める。
そのうち、 OK(それだけは分かった)という文字が表示されたかと思うと、 突然、 背中に、 硬い手術台の感触が蘇った。 いままで、 宙をふわふわ漂っていた身体がふんわりと、 手術台の上に仰向けに軟着陸したみたいな、 不思議な感覚。
まぶたの向こうに光を感じて、 ゆっくりと眼をあける。 まぶしいライトの白い光が、 天井から私のことを照らしていた。
「八木橋さん、 ご機嫌いかが?」
背後から強い光を浴びて、 逆光になったタマちゃんの黒いシルエットが、 私を見下ろす。
五体満足っていうのは、 すばらしい! それが、 たとえ、 作り物の擬似感覚だったとしても。
ライトのまぶしさに、 思わず眼を細めながら、 私は思った。
「うー、 機嫌いいわけないじゃないか。 私、 恐かったんだから。 本当に恐かったんだから・・・」
完全に感覚遮断のトラウマを植えつけられた! 三年に一回の入院検査のたびに、 こんな目に遭うのかと思うと、 憂鬱! そんなふうに愚痴の一つや二つ、 タマちゃん相手にこぼそうと思ったんだけど、 言いかけて、 あわててのどを押える私。
私の声、 変わってる・・・。
事故で身体を失った私は、 今まで、 標準義体っていう外見から何から規格化された義体に入っていたんだ。 声だって、 もちろん昔と違ってしまっていて、 ものすごい違和感があったんだよ。
でも、 この声は、 正真正銘、 私自身の声だ。 まだ生身の頃の自分の声だ。
「ふふふ。 八木橋さん、 声が変わっているのに気がついた? 八木橋さんのおじいさんから、 昔の八木橋さんが映っているビデオをイソジマ電工に送ってもらいました。 それを基に、 義体開発課の人たちが、 八木橋さんの声を再現してみたのでーす。 八木橋さん自身が聞く、 自分の声も、 そのビデオと、 もとの骨格から推定して、 再現したと言っていたけれど、 うまくいったかな?」
戸惑う私をおかしそうに眺めながら、 タマちゃんは言った。
「あー、 あー、 あー。 タマちゃん。 元どおりだ。 私の声、 昔のまんまだよう! すごいよ! すごいよ!」
愚痴をこぼすのも忘れて、 私は思わず興奮してしまった。
私が私の声って認識している声と、 他の人が私の声って認識している声は違う。 ビデオに映った自分の声を聞くと、 なんだか別人の声に聞こえるみたいにね。 そして、 ビデオに映った自分自身の声をそのまま再現するのは、 それほど難しいことじゃないと思う。 でも、 今、 私が聞いているのは、 世の中で私だけしか知らないはずの、 私自身が聞いている声なんだ。 そんなのどうやって調べるんだろう。
私は嬉しかった。 もちろん、 この声だって、 ホントのことを言えば、 昔の肉声とは違う。 ただ、 昔の声を真似した電気合成音がスピーカーから流れているだけ。 分かってる。 そんなことは分かってるよ。 でも、 例え、 そうだとしても、 この義体を作ってくれた人たちの、 少しでも義体から感じる違和感を取り除いてあげようっていう、 努力と心意気が私に伝わってくる気がしたんだ。
それにしても、 おじいちゃん、 いったいどんなビデオを送ったんだろう。 まさか、 運動会で、 スタート直後に転んだときのビデオじゃないだろうね。 そう思って、 ちょっぴり不安になってしまう私なのでした。
「じゃあ、 起き上がってみようか?」
「うん」
タマちゃんに促されて、 私は、 ゆっくりと身体を起こして、 周囲をみまわす。
吉澤センセイは、 私と同時に換装手術を受けているはずの佐々波さんのところにいるんだろうか。 手術室には、 私と、 タマちゃんしかいなかった。 ううん、 正確に言えば、 もう一人。
私の寝ていた手術台と、 丁度並ぶような形で、 もう一台手術台が置かれている。 そして、 その上に、 もう見慣れてしまった、 綺麗な顔の女の人が、 生まれたままの姿で眠っている。 もう、 私とは何の関係もない、 ただの抜け殻のはずなのに、 彼女の裸を見るのは、 やっぱり妙に気恥ずかしかった。
(短い間だったけど、 本当に有難う。 あなたも、 私の命の恩人だよ)
私は、 彼女に向って、 頭を下げた。
ホントは、 あなたの出番なんか、 もう来ないのが一番いい。 私みたいな目にあうのは、 もう私だけでたくさん。 でも、 そんな理想を言ったってしょうがないよね。 たくさんの人がこうして社会を築いて生きている限り、 やっぱりどうしても、 不慮の事故は起きてしまう。 だから・・・だから・・・。
(次に、 また誰かの役に立つ、 その時まで、 ゆっくりとお休みなさい)
「八木橋さん。 ハイ、 これどうぞ」
手術台から、 ぴょんと飛び降りた私に向かって、 タマちゃんが手渡してくれたものは、 鏡と眼鏡。
「換装手術が終わったばかりの人は、 みんな、 真っ先に自分の姿を見たいって言いまーす。 八木橋さんも、 そうでしょ」
確かに、 タマちゃんの言う通り。 ようやく自分の身体を手に入れた私。 一度、 診察室で自分の義体を見ているとはいえ、 やっぱり、 ちゃんと、自分自身が中に入った状態で、 自分を見たい。 そう思うのは自然なことだよね。
眼鏡をかけて、 タマちゃんから受け取った鏡を、 おそるおそる覗き込む。
鏡の向こうで、 昔のまんまの私自身が、 じぃっと私のことを見つめている。 フレームのない、 小さな眼鏡の奥でかすかに光る、 今の私の黒い瞳は、 強化ガラスとプラスチックでできた作り物かもしれない。 でも、 その機械の瞳の奥底に、 私は自分自身の強い意志の力を感じた。 この機械の身体の中に、 確かに私の命が宿っている。 そう思ったら、 嬉しくなった。
「こ、 ん、 に、 ち、 は」
私は鏡に向かって言った。 鏡の向こうの、もう一人の私も同じように口を動かした。
「これから、 一生あなたのお世話になります。 八木橋裕子といいます。 宜しくね」
鏡の向こうで、 17歳の女子高生が笑った。 久しぶりに聞く、 正真正銘、 自分の声での笑い声だった。
「ところで佐々波さんは、 どうなったの?」
自分の姿に満足した私は、 もう一つ、 とても気になっている、 私と同時に換装手術を受けているはずの人のことを聞いた。
「ふふふ。 佐々波さんの換装手術は、 もう終わってるよ。 一度あなたに挨拶しておきたいって、すぐ外の待合室で、 あなたが来るのを待ってまーす」
そう言って、 タマちゃんは、 手術室の観音開きのドアを指差した。
このドアの向こうに、 佐々波さんがいるんだ。 男になった、 佐々波さん。 いったいどんな姿をしているんだろう? 結構、カッコ良かったりするんだろうか?
今まで、 何度も会っているけど、 でもはじめて会う。 なんだか、 とても不思議な感覚だ。
「えと、 私はもう出ていいのかなあ?」
「もちろん! どうぞ、 こちらへ」
タマちゃんは、 私を出口まで導くと、 うやうやしく大げさな調子で頭を下げながら、 手術室の大きなドアを開いた。
手術室には窓なんてないから気がつかなかったけど、 待合室に出てみると、 もう夕暮れ。 府南病院の義体科の待合室は、 傾きかけた陽の光に照らされて、 影がくっきりと浮かび上がって、 まるで、 黒とオレンジの二色に染め分けられてしまったかのようだった。
もう、 診察時間も終わったんだろうね。 人影もまばら、 しーんと静まり返った待合室の、 整然と並べられた長椅子の端っこに、 女の人が二人ぽつんと腰掛けている。
一人は私も知っている。 相変わらず、 びしっと凛々しくスーツを着こなした、 佐々波さんの恋人のタチバナカズミさんだ。 そして、 もう一人は、 私と同じ、 白くてぶかぶかの入院服を着た、 私の知らないショートヘアの女の子。 長身のカズミさんと並ぶと、 座っていても、 頭半分くらい背丈が違っちゃうほど小さくて、 いかにも健康ですって自己主張しているような小麦色の肌をした、 綺麗っていうよりも、 やんちゃな子猫を思わせるような愛くるしい顔立ちの子だった。
佐々波さんらしき男の人は、 どこにも見当たらない。
「あなた、 八木橋裕子さんでしょ。 話はれいじ君から聞いてるわ。 ずいぶんお世話になったみたいね」
私を認めたカズミさんが、 立ち上がって、 手を差し出した。
私は握手をしながら、 面会の時の自分の痴態を思い出して、 思わず苦笑い。 カズミさんは、 初めて私に会ったように思っているかもしれないけど、 私達、 ホントは、 二度目まして、 だ。 でも、 あなたに、 あんなことや、 こんなことをされました、 なんて言えるはずがない。
「佐々波さんは、 どこにいるの?」
私の問いかけに、 カズミさんと、 女の子は、 顔を見合わせて笑った。
「よう、 メガネザル」
小さな女の子が立ち上がって、 馴れ馴れしい調子で、 私の肩に手をかけた。
私の知る限り、 私のことをこんなふうに呼ぶ人は一人しかいない。
「あなた、 さ、 佐々波さんなの? ホントに?」
「なんだよ。 そんなに驚くことかよ」
「だって、 だって、 佐々波さん。 男になったんじゃなかったの?」
私は、 もう一度、 目の前の佐々波さんの身体をまじまじと見つめる。 ひょっとしたら、 女の子に見えるだけで、 実は男の子なのかなあって思ったんだけど、 入院服の上からでもはっきりわかる胸のふくらみは、 どう考えても女の子のものだった。
「オレは、 前からずっと、 男だよ」
佐々波さんは、 不機嫌そうに、 ぷいっと私から目を逸らした。
そうか、 そういう言い方をしたら怒る人だったね。 あわてて言い直す私。
「佐々波さん、 男の身体にするんじゃなかったの? だって、 男として覚悟は決めたって言ったじゃないか。 カズミさんと結婚するって言ったじゃないか」
「男らしく割り切って、 女の身体で生きていく覚悟を決めたってことだよ。 男の身体だと、 カズミと結婚できないからな」
「え、 だって、 カズミさん、 女じゃないか。 佐々波さん、 何言ってるんだよう」
カズミさんは女だから、 佐々波さんがカズミさんと結婚するためにも、 当然男の身体を選ぶものだと思っていた。 なのに、 佐々波さんは、 カズミさんと結婚するために、 あえて女の身体を選んだのだという。 わけわからないよ。 女同士だったら、 結婚できるはずないじゃないかよう。
戸惑ってる私に向かって、 カズミさんがぽつりと呟く。
「私、 こう見えても身体は男だから」
「はじめまして、 私、 立花一巳といいます」
私の目の前の美女が言った。
失礼かなと思ったけど、 今度は一巳さんの身体をまじまじと見つめてしまう。 だって、 一巳さん、 すごい美人で、 スタイルだっていいし、 確かに女性にしては少し背が高いかなって思ったけど、 このくらいの背丈の女性だって、 いないことはない。 男だなんて言われても、 とても信じられないよ。
「くくく、 うまく、 化けてるだろ? オレもはじめは騙されたんだ」
佐々波さんは、 言葉を失って立ち尽くす私を、 面白そうに眺めた。
「れいじ君は、 どう頑張っても女の子にしか見えないからね。 後で後悔して、 泣き言を言うんじゃないよ」
一巳さんは、 そんな佐々波さんにピシャリと言い放つ。
そうなんだ。 佐々波さんは、 これから一生、 この女性型の義体で生きていかなくてはいけない。 もしも女の子だったら、 男の子にちやほやされそうな、 とっても可愛らしい顔立ち、 でも、 どう頑張っても男に見られないというのは、 男としての意識を持つ佐々波さんにとっては、 辛いことかもしれない。 一巳さんが、 面会の時、 佐々波さんに、 後悔しないか、 覚悟はあるか、 しきりに聞いていたのを思い出す。
「分かってるさ」
佐々波さんは、 一巳さんの顔を見上げて言った。
「カズミだって、 男の身体のままなんだ。 オレだけが、 男になってラクをするわけにはいかないよ」
そんなふうに言い切る佐々波さんは、 どんなに身体が可愛らしい女の子でも、 やっぱり男の心を持ってる人なんだって、 思ったよ。
えーと、 佐々波さんは、 身体は女性だけど、 男性の心を持っていて、 そして、 一巳さんは、 男性だけど、 女性の心を持っている。 でも、 心の性と身体の性は一致しなくても、 お互いに男と女ということには変わりが無くて・・・なんだかとってもフクザツ。
でも、 私、 分かってる。 難しく考えるからいけないんだ。 ホントは、 もっと単純なこと。 男の心と、 女の心が、 お互いを愛し合い結びついた。 ただそれだけのことだよね。 どんな姿をしていようと関係ないよね。
「それにしても、 メガネザルって・・・」
今度は佐々波さんが、 感心したように私のことを上から下まで見つめる。
「もっとオバサンかと思ってたけど、 意外と子供だったのな」
「な・・・な・・・な・・・」
絶句する私。
それは、 何かい。 佐々波さん、 私のこと、 今までずーっと、年増のおばさんだって思ってたってことかい。 ひどい。 そんなのひどすぎるよ。
あなたの心が男であるように、 私の心は17歳の女子高生。 決しておばさんなんかじゃないんだからね。
悔しいっ!