| 年(元号) | 年(西暦) | できごと |
| 昭和14年 | 1939年 | 留萠−達布間地方鉄道敷設免許 天塩鉄道株式会社創立 北炭天塩礦(栄坑)開礦 |
| 昭和15年 | 1940年 | 北炭天塩礦(寿坑)・天狗炭礦・新美唄炭礦開礦 |
| 昭和16年 | 1941年 | 天塩鉄道(後の天塩炭礦鉄道)留萠−天塩本郷間開業・天塩本郷−達布間車扱貨物のみ開業 林野局旭川支局小平蘂出張所(後の小平蘂営林署→達布営林署)開設 |
| 昭和17年 | 1942年 | 天塩鉄道天塩本郷−達布間貨客とも開業 |
| 昭和20年 | 1945年 | 小平森林鉄道建設開始 |
| 昭和22年 | 1947年 | 住吉・沖内・寧楽の炭礦開発 |
| 昭和26年 | 1951年 | 北炭撤退 天鉄による採炭事業継承 |
| 昭和27年 | 1952年 | 小平森林鉄道全通 |
| 昭和33年 | 1958年 | 小平森林鉄道全廃 |
昭和20(1945)年の森林鉄道建設開始は、大株主たる宮内省による緊急経営支援と想定される。森林鉄道接続による木材輸送の増加、さらに新規炭礦開発を加えても、「当社の営業も亦極度に逼迫し、幾度かの経営難に陥」るほど天鉄の経営は傾いたのだから、状況の深刻さがうかがえる。
■天鉄による採炭事業の継承
北炭は天塩礦の存続を諦め、昭和26(1951)年 3月に採炭事業中止を決定する。通常であれば、子会社である天鉄もまた営業廃止になるところであろう。ところが、なぜか天鉄は屈さなかった。
「地方鉄道の公共的使命を強く認識し、……炭礦及び鉄道沿線一帯に亙る部落住民の死活問題にして、当社の進退は社会的にも波及するところ甚大なるに鑑み、自らの手にて炭礦を経営し、鉄道、炭礦の一本化により当社再建の方途を講ずることとなった」
経済合理性を超越する侠気と呼ぶべきか。天鉄は北炭が諦めた炭礦経営に乗り出すことにより、自らの存続を賭けた。もとより天鉄は北炭の子会社であり、炭礦経営のノウハウを有する役職員が多く、相応の自信があったのかもしれない。それにしても勇気ある決断だったといえる。
地上でどのような変化があろうとも、地下の炭層にまで影響が及ぶことはありえない。ところが、天塩礦の経営権が北炭から天鉄に移った時期以降、石炭産出量が急増したから不思議である。昭和31(1956)年10月には 9,300トン/月の産出量を得て、参考文献(01)に「開礦以来の最高を記録」と特筆大書されることとなった。
■天鉄を後援した要素
この事態を、幸運が向いてきた、神風が吹いた、天佑神助のおかげ、などとオカルト的に理解すると本質を見誤る。参考文献(19)では、「本地域からは石炭が産出し、留萠炭田としてかつて活発に採掘されました。本地域の石炭は江戸時代末期にはすでにその存在が知られていたようですが、地質構造が複雑であること、交通の便が悪かったことから、本格的な開発がなされたのは昭和に入ってから」と概括されており、「複雑な地質構造」を如何に解きほぐすかが発展の鍵になったことがわかる。
留萠炭田の正体を知る努力は、北炭撤退とほぼ同時に本格化している。参考文献(20)によれば、「留萠炭田の層序・地質構造については、従来多くの調査が行われ、当調査所においても昭和26年度以来野外精査その他の調査研究が続行された」という。参考文献(20)そのものは昭和32(1957)年の調査であり、これら調査成果の積み重ねが天塩炭礦増産につながったといえる。また、これら調査がなされるという確信があればこそ、天鉄は炭礦事業承継の意欲と希望を持てたのではあるまいか。
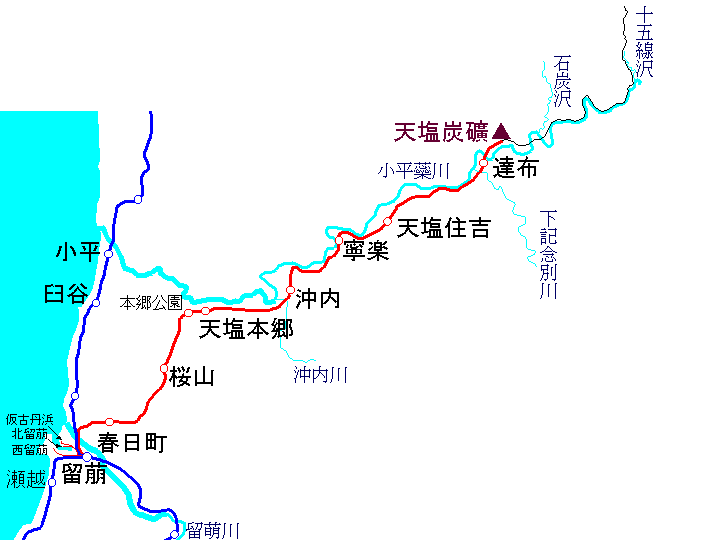
図−5 天鉄及び小平森林鉄道路線図
昭和30年代初頭にしてようやく得られた活況は、天鉄当事者には格別の重みがあったと思われる。天鉄の開業以前から常務取締役を務め、昭和22(1947)年から社長に就任して苦労を重ねてきた大西一男氏にとっては、ことに感慨深いものがあったに違いあるまい。参考文献(01)「十五年史」はおそらく、谷ばかりだった天鉄の事業が上向いてきたことを記念し、さらなる発展を期す大西社長の意向により編まれたものと想像される。
■絶対値はあいかわらず不振
とはいえ、しかしながら。
数字は冷酷非情に現実をあぶり出す。天鉄及び天塩炭礦の業績は、確かに良くなったのかもしれない。しかしそれは、創業当初の極めて不振だった時期と比べての話であって、絶対的な尺度で見ればさして良好な数字が残されているとはいえない。
まず、旅客輸送密度の経年推移を図−6に示す。
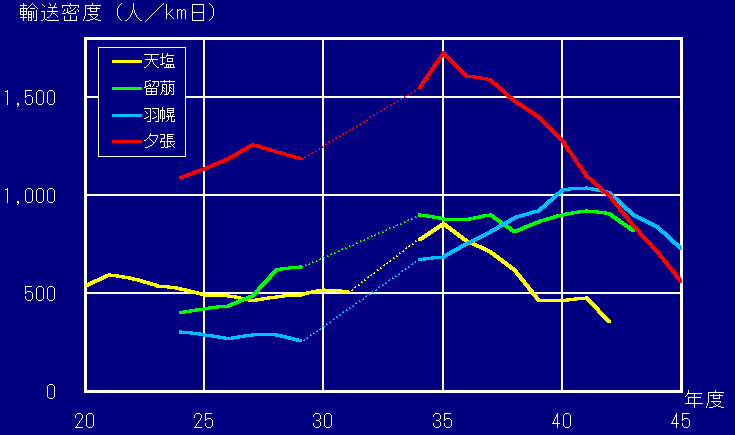
図−6 天鉄旅客輸送密度の経年推移
なお、容易に閲覧できる年度版に限りがあったため、昭和24(1949)年度・26(1951)〜29(1954)年度・34(1959)〜45(1970)年度のデータのみをとりあげた。図示するにあたり、昭和25(1950)年度は24・26(1949・1951)年度の平均値とした。昭和30(1955)〜33(1958)年度の数字は推測せず破線で表示した。また、昭和40年代(1960年代後半)のデータの欠落は、各鉄道の休廃止に伴うものである。
ただし、天鉄に関しては、参考文献(01)「旅客竝に貨物輸送高累年比較」から、昭和20(1945)〜23(1948)年度・25(1950)年度・30(1955)〜31(1956)年度の数字を推測した。「累年比較」は昭和17年度を基に各年度の成績を指数化したグラフであり、具体的な数字の記述がなく、また人・トンベースなのか人キロ・トンキロベースなのかも不詳である。従って、この推測はかならずしも正確でないことを付記しておく。同様の作業は、図−7に対しても行っている。
旅客輸送密度はいずれも低水準で特定地方交通線なみ、それも低位の部類に属している。もっとも、旅客需要の少なさは礦山鉄道に共通する性格といえ、やむをえない面はある。いくら沿線人口が多くとも、礦山の許での自給自足が基本であって、移動する需要が多いわけではないからだ。夕張鉄道の輸送密度が 1,500人/km日を越えているのは、どちらかといえば驚異的な好成績と呼ぶべきなのであろう。
それでも、天鉄は利用者の誘致に力を入れたとされている。奥山様(承前)によると、留萠市内からの観光客を誘致するため、天鉄は本郷地区に桜を植えて公園の整備を図り、さらに本郷公園駅を設置したとの由。同様のことを天鉄バスの運転手も語っていたから、情報の確度は高い。
参考文献(01)に記述がないことから、本郷公園駅の設置は昭和32(1957)年の夏以降と思われる。筆者の平成 3(1991)年現地訪問時に参照した国土地理院地形図にも本郷公園駅は記載されていた(ただしいつ時点の版か手許に記録が残っていない)。少しでも業績を伸ばすための天鉄の努力がうかがえるエピソードといえる。
さて問題は、貨物輸送密度である。
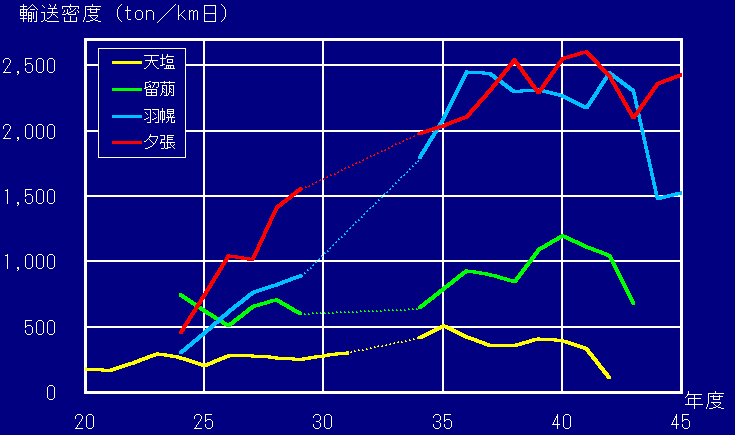
図−7 天鉄貨物輸送密度の経年推移
この全数が天塩炭礦産の石炭と仮定して換算すると、18万トン/年になり、天塩炭礦の生産量は飛躍的に伸びたとはいえる。ところが、その輸送密度はわずか 500トン/km日にすぎず、性能の良い機関車があれば一列車で運びきれてしまう量でしかない。天鉄の C58の性能及び勾配条件を考慮しても、二列車も仕立てれば充分に運べるだろう。この程度の輸送密度で鉄道経営を良好にするのは難しい、といわざるをえない。
夕張鉄道と羽幌炭礦鉄道では、ピーク時の貨物輸送密度が 2,500トン/km日あり、まずまず良好な収益を期待できそうだ。留萠鉄道の 1,200トン/km日では、やや苦しいところかもしれない。ところが、天鉄の輸送密度はわずか 500トン/km日。留萠鉄道と比べ半分以下、夕張鉄道・羽幌炭礦鉄道の二割程度である。どの鉄道も需要の根源は炭礦にあり、輸送密度の差はそのまま炭礦生産量の差といえる。生産量が他と比べて少ない天塩炭礦を戴く天鉄が苦しい経営を強いられたのは、当然すぎるほど当然というしかない。
■足枷多き経営
しかも天鉄には、営業面で足枷をはめられていた形跡がある。参考文献(02)には、天鉄の業況紹介として以下の記述が見られる。
「総じて鉄道業は、公共性をもつ関係から運賃の抑制をうけ、また施設、運行、保安面に監督官庁の干渉が多く、経営妙味の乏しいものとされているが、これに加えて冬期の除雪対策、夏期の一日四往復の運行を義務づけられる点から、依然として赤字を脱却しえない状況である」
どの記述も興味深いところだが、夏期 1日 4往復の運行義務という点は特に興味深い。誰がどのように義務づけたか詳しい記述はないものの、 2往復でも間に合うのに 4往復を運行しなければならないというのは、経営上の重荷であったろう。
天鉄の運行本数は、昭和39(1964)年 8月時点でもなお 4往復(参考文献(07))あった。これは他の私鉄と比べれば少ない水準だが、それでも輸送力過剰というあたりに、天鉄の厳しさがあった。
25.4kmの路線、 135名の鉄道部門従業員、 3両の蒸気機関車、 6両の客車、29両の保有貨車、15両の借入貨車、 1両のラッセル車(昭和31(1956)年度末時点/参考文献(01))。これだけの資産を維持するためには、相応の収益を確保しなければならない。天塩炭礦が全盛時の生産を続けたとしても、否、全盛時からさらに倍の生産量を挙げてさえ、天鉄は鉄道事業の維持ができたかどうか。
全盛期の 500トン/km日という輸送量は、道路事情さえよければ、10トンダンプを日に15台もチャーターすれば運べる量にすぎない。天鉄の運命を握る鍵は、エネルギー政策の方向というよりむしろ、沿線の道路整備進捗だったといえる。
その意味において、昭和34(1959)年の小平−達布間冬期除雪開始、昭和36(1961)年の天鉄バス留萠−達布間定期運行開始という二つのできごとは、天鉄の交通機関としての存在価値を大幅に低下させることになった。天鉄が割り切ってしまえば、昭和36年時点での鉄道事業廃止も充分にありえただろう。

写真−5 達布駅跡(手前が留萠方面)
■天鉄の廃止
昭和42(1967)年、天鉄及び新日本炭業経営の炭礦が閉山となり、小平町内全ての炭礦が閉山となった。昭和34(1959)年に天塩鉄道から天塩炭礦鉄道と改称していた天鉄は、炭礦閉山と歩調を合わせ鉄道事業を廃止した。
天鉄は開業からわずか26年での廃止となり、短命鉄道の一角を占めている。ちなみに、北海道の炭礦鉄道で天鉄よりも短命だった路線は、白糠線(白糠−上茶路間・19年)しか存在しない。
もっとも天鉄の場合、前述したとおり昭和36(1961)年での鉄道事業廃止もありえた。天鉄は営業当時から諸設備の老朽劣化がはげしかったという説もあるほどだ。また、今日の視点で見ても、天鉄には急所となる箇所がいくつかある。例えばここ。


写真−6 第一トンネル達布側遠景 写真−7 第一トンネル−桜山間
※:ころこく、と読む。実在する地名ではなく、三国志演義において、諸葛亮が司馬懿と魏延をまとめて焼殺しようとした場所として伝えられている。要するに周囲を急斜面で囲まれた狭い窪地で、細い一本の出入口しかないため、伏兵を置くには絶好の地形というわけだ。
このような地形に鉄道を敷設するからには、さぞかし水の始末に困ったと考えられる。晴天時には問題なくとも、ちょっとした大雨が降ればトンネル坑口付近は水没し、線路際(あるいは線路の上を)濁流が走ったのではあるまいか。地方私鉄ではよくありがちな、水害で運休→そのまま廃止、という展開があってもおかしくなかった。
現地踏査できていないが、第二トンネルは輪をかけて地勢が厳しい。国土地理院地形図から判断する限り、第二トンネル留萠側坑口は水がさらに走りやすい地勢であり、達布側坑口は二つの沢筋の合流部に直面している。どちらの箇所も、頻繁に路盤冠水(悪ければ流出)があったのではないかと思われる。
奇跡といえば、小平町内での炭礦事業は後に奇跡の復活を遂げている。昭和58(1983)年に空知炭礦達布露天坑及び吉住炭礦東坑が採炭を始めたのである。ただし、鉄道事業の復活までには至らなかった。採掘量は細々としたものであったし、それ以上に鉄道貨物の壊滅的衰退が進み、ローカル鉄道は社会的価値を失っていたからである。
さかのぼること昭和55(1980)年、既に国鉄再建法が公布されていた。同法により羽幌線ばかりか留萠本線まで廃止が検討されたほどだから、天鉄復活などもはやありえるはずがなかった。昭和50年代以降、日本の鉄道は大都市及び幹線旅客輸送中心という、世界的に稀有な発展を遂げることになる。
| このページは、2019年3月に保存されたアーカイブです。最新の内容ではない場合がありますのでご注意ください |