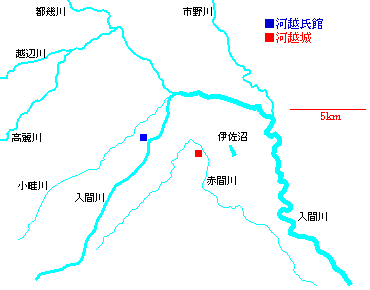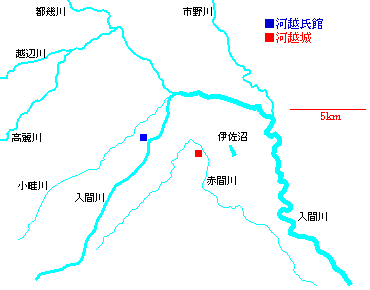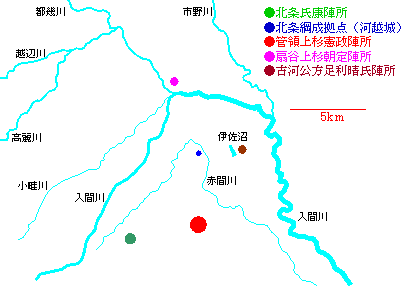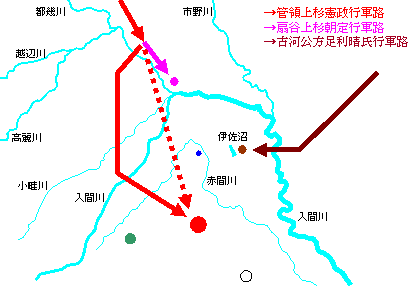|
このページは、2019年3月に保存されたアーカイブです。最新の内容ではない場合がありますのでご注意ください
|
そのⅠ 河越城の立地
1.河越城のなりたち
河越城は長禄元(1457)年、扇谷(おうぎがやつ)上杉持朝により築城された。城普請を奉行したのは大田道灌、江戸城を普請したことで名高い人物である。それゆえ都内には道灌山の地名が残り、日暮里駅前には道灌公の像が建立されている。
注:河越城を普請した人物については、道灌の父道真説、道真・道灌父子共同作業説などの異説も存在する。
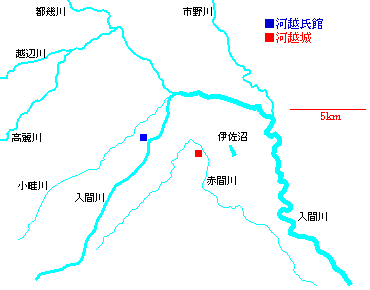
河越城位置図
河越城は台地の北端に位置しており、台地外縁の斜面を防壁に、台地外縁に沿う赤間川(現在の新河岸川)を外堀に、そして入間川を大外堀に配し、入間川と赤間川に挟まれた田圃などの低湿地帯を主防衛線とする、天然の障壁を最大限に活用した、まさしく鉄壁の守りを誇る名城であった。河越氏館の立地でも決して悪くはないが、入間川を迂回されてしまえば次の防衛線がないわけで、これと比べれば守備力が桁違いに強化されたと考えてよい。地味ながら、後の石山本願寺(大阪城)にも比すべき堅固な守りを備える城、それが河越城であった。
注:荒川が現在の流路となるのは江戸時代の治水工事による。この当時、入間川に荒川は合流していなかった。なお、当時の川の流路に関する資料は乏しいため、上の作図中に示した川の流路は全て筆者推測による。
以上の観点から河越城位置図を見れば、河越城の主防衛線は東及び北方面に対し極めて厚いことが理解できる。さもありなん、扇谷上杉氏は古河公方足利氏と抗争を繰り返しており、河越城が築城された意義を以て知ることができる。後に扇谷上杉氏は一族たる関東管領(山内)上杉氏とも相争うに至り、管領上杉氏は北方に蟠踞していたことから、河越城の戦略的意義はますます重きを加えることになる。
東・北方面に対して、河越城の西方面は防衛線が薄く、南方面に至っては丸裸に等しい。扇谷上杉氏はもともと武蔵南部・相模を拠点としていたから、当然といえば当然のことにすぎないが、河越城は南方面の守備に弱点を抱えていることは、おそらく誰の目にも明らかであっただろう。
2.河越夜戦前説
扇谷上杉氏・管領上杉氏・古河公方足利氏らが鶏の喧嘩を繰り返している間に、漁夫の利と呼ぶべきか、早雲を開祖とする(後)北条氏が勃興し、急速に勢力を拡大していく。そして、北条氏は扇谷上杉氏を駆逐してしまうのである。河越城はその立地上、南からの侵攻に対し極めて脆弱であり、河越城を落とした北条氏は女婿たる猛将綱成を守将とした。これに驚いたのは旧勢力の各氏。今までの抗争はどこへやら、仇怨を横に置いたかの如く一致団結し、北条綱成が籠もる河越城を大軍をもって包囲したのである。
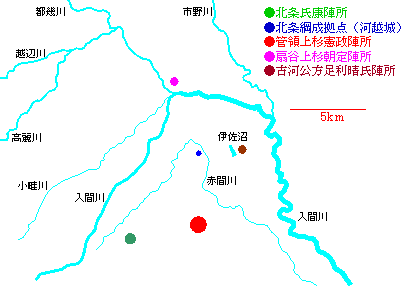
河越夜戦武将配置図 注:位置は全て筆者推定。
この時、大将たる管領上杉憲政は砂窪(現在の新河岸駅西方)に、扇谷上杉朝定は入間川北岸の伊草に、古河公方足利晴氏は伊佐沼に、それぞれ陣所を構え、その総勢はなんと八万に及んだともいわれている。これに対する北条は如何にも微力で、北条綱成の籠城勢がわずかに三千、救援に赴き三ツ木(現在の新狭山駅付近)に陣した北条氏康勢も八千にすぎなかった。単純に数だけを比較すれば七倍以上の懸絶があるわけで、北条勢の不利は明々白々であった。
注:大河ドラマ中では、扇谷上杉朝定は河越城直近西方に陣所を構えたと示されていたが、これは信じがたい。足場の悪い低湿地帯で、しかも籠城勢からの急襲を受ける危険もあるわけで、先陣ならばともかくとして、有力武将の陣所になったとは思われない。本稿では参考文献(2) の記述により、そして筆者個人の感覚から信じられる場所として、扇谷上杉朝定の陣所は伊草とした。
それにしてもこの武将配置図を見ると、各武将の性格がそのまま現れているようで興味深い。管領上杉憲政は、おそらく河越城は南方面が弱点であることをよく知ったうえで、絶対的に優位な地の利を占めている。扇谷上杉朝定は、賢明にも背水陣を避けた形であるが、及び腰に遠巻きしているだけかもしれない。面白いのは古河公方足利晴氏で、ひとり突出して河越城に肉薄している格好だ。度胸があるのか、虚勢を張っているのか、あるいはただの無思慮なのか。少なくとも、まったく無防備に伊佐沼西方に陣するはずがないと考え、伊佐沼東方の布陣と推定したが、実際のところはどうだろうか……。そして、実に絶妙な位置にいるのが北条氏康、ただしこれについては更なる解説が必要だろう。
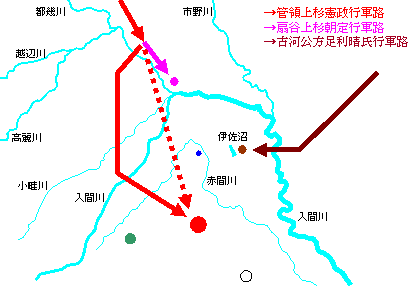
河越夜戦武将行軍路 注:行軍路は全て筆者推定。
管領上杉勢は、現在の国道 254号沿いに南下してきたと思われる。越辺川左岸のどこかで扇谷上杉勢を分派し、自らは絶対的優位な地の利を確保するため大迂回していく。そのための進路は、大軍の進退に便利というだけの理由で、高燥台地上を選んだに違いない。その「配慮」は結果的に入間川を楯となし、籠城勢からの急襲を避けることにつながった。逆にいえば、わざわざ低湿地帯を行軍し、進退に窮した挙げ句急襲を受けてしまうほど、凡愚な武将は滅多にいない、という話である。たとえ最短経路であっても、赤破線のような行軍路はありえないはずである。
注:管領上杉勢の進路は児玉往還(川越街道)そのものだった可能性はあるが、これだけの大軍の移動となれば、一旦松山城に集結したであろうと想定されることから、図のように想定した。
参考までにいえば、管領上杉勢の入間川の渡河地点はおそらく、河越城南西はるか遠方安比奈付近ではなかろうか。つまり管領上杉勢は、現在の安比奈線に沿って行軍してきたともいえるのである。
3.勝敗の分岐点
以上の推定が正しければ、北条氏康勢は管領上杉勢の退路を断つ構えを示していることが理解できるだろう。仮に北条氏康の陣所が図中○の位置(現在の朝霞駅付近)であれば、及び腰どころかへっぴり腰、著しく敢闘精神に欠ける構えといわざるをえないところだが、実際の北条氏康は鋭気溌剌・戦意旺盛なる武将であったはずだ。
そんな北条氏康であるというのに、上杉憲政がすっかり侮ってしまったのは、運の尽きというべきか。大軍ゆえの驕りか慢心か。なるほど、当時の北条氏康が順境にあったわけでないことは確かである。駿河今川氏とも抗争を続けており、せっかく斬り取った領域を割譲することを条件として、和睦する羽目におちいっている。しかしこれは裏表の事象であり、戦線を整頓する意味においては有利な条件であった。北条氏康は河越城救援に全力を傾け、智謀の限りを尽くし戦意なきことを装った。攻城勢は迂闊にも、その真の意味に気づくことがなかった。かくして攻城勢は北条勢を弱敵と侮るあまり、油断し、弛緩し、堕落していく。
上杉憲政最大の敗因は、自らの弱みに気づかなかったことにある。七倍強もの兵力差があった以上、力押しに攻めて河越城を落とすことは決して難事でなかった。敢えてそれをしなかったのは、自軍兵力の損耗と、これに伴う同盟諸将の離反をおそれたからであろう。八万の大軍といえども、実状は寄せ集めのようなもので、「敵の敵は味方」ていどの紐帯しかなかった。この弱みを自覚したうえで、北条氏康の決戦意図を見抜いていたならば、滞陣をいたずらに長引かせることなく、自軍兵力の損耗をも顧みず、数の力にものいわせ、強攻に強攻を重ね勝利を獲得していたに違いない。
このように考えていくと、八万もの大軍を催したことじたいが厭戦気分の裏返し、ともいえる。上杉憲政は内心で実は「北条氏康め自棄になって刃向かってくれるな」と臆していたのかもしれない。無論これは想像にすぎないわけだが、白拍子など呼び遊興に耽っていたというあたり、合戦の恐怖から目を逸らして現実逃避していた、とみなす方がむしろ合点がいきやすいのではないか。上杉憲政は、自らの弱みに正面から向き合えなかったという意味において、心の弱い武将であった。
天文15(1546)年 4月20日、北条勢が攻城勢に夜襲を仕掛けた時には、北条勢の勝利は約束されていた。攻城勢は長滞陣に倦み、戦意まったく騰がらず、軍紀も地に堕ちていた。数こそ八万あれど、もはや烏合の衆。ほとんど一支えもできずに潰乱したといわれている。そのなかで東明寺口では激戦が交わされ、扇谷上杉麾下難波田弾正の奮戦と不運なる落命が伝えられている。このことから「河越夜戦」は「東明寺夜戦」と呼ばれることもある。
「河越夜戦」により、安全地帯にいたはずの上杉朝定は討ち死にし、扇谷上杉家は滅亡してしまった。上杉憲政はかろうじて逃げ落ちたものの、家勢は衰亡の急坂を転げ落ちていくことになる。最後には長尾景虎に上杉姓を譲り、歴史の表舞台から退場した。代わりに登場した景虎は後に上杉謙信と名乗り、青史に名を刻んだばかりか、後世の人々の尊敬を受け続けるほどの大人物になった。上杉憲政は日本史上無名に近い存在だが、上杉謙信の名を知らぬ日本人は稀であろう。歴史とはまこと皮肉なものである。
この一戦にて関東南部での覇権を確立させた北条氏にしても、さらに後年「小田原評定」なる不名誉な事績を残し、世の冷笑を浴び続ける仕儀とあいなった。諸行無常とは歴史の理、栄枯盛衰と毀誉褒貶のはげしさには深く嘆じざるをえない。
さて、上杉憲政が逃げていった経路は必ずしも確かでない。敗走の記録は残らないものだ。さりながら、上杉憲政が本領さして駆け去っていったとおぼしき道筋は、東上鉄道が上州を目指すべき経路とほぼ近似していることは間違いなかろう。そのⅡ・ⅢではH.Kuma様の記事を素材として、東上鉄道がどのような道を選ぼうとしたのか、推理してみたい。
先に進む
元に戻る
|
このページは、2019年3月に保存されたアーカイブです。最新の内容ではない場合がありますのでご注意ください
|