
| このページは、2019年3月に保存されたアーカイブです。最新の内容ではない場合がありますのでご注意ください |
第5章 八雲における生活文化の変化
5-1 初期の農業
洋式農法の導入
徳川家では当初、初めの1〜2年は専ら畑作を中心に桑苗の栽培・雑穀の試作を行ない、後には水田を開いて田畑の耕作に従事し養蚕を開始することにより農業経営の基礎を固めることにしていた(1)。
士族移民たちは、かつて帰田法の適用を受けていた人たちを除くと、農業についての知識や経験などはあまりなかったため、徳川家開墾試験場では開拓使の奨励する洋式農法(泰西農法)を勉強し受け入れていくことにした。
1878(明治11)年2月、開拓使は「西洋農具貸与規則」を定め、15町歩以上の開墾を行なう者に勧業課吏員を派遣し開墾の応援をすることとしており、同年9月には開拓使函館支庁技術員が牛4頭を連れて移住が始まったばかりの遊楽部に来て、ソリキプラオ(牛刀)などの西洋農具を持って開墾の指導を行なっている。初代開墾地委員吉田知行は洋式農法の威力を見てその導入を考え、同年11月には移民の中から独身の4人を七重勧業試験場に派遣して、牛馬の取扱い、西洋農具の使用、馬具の製作などについて実習させる(2)など農法の研究につとめ、牛馬の飼育繁殖が積極的に行なわれた。
初期の酪農
酪農も早い時期から着目されていた。1882年には野田生地区に吉田知行を社長とする「株式会社野田生牧牛社」を創設し、同年7月には乳牛42頭・馬数頭・豚1頭・鶏253羽を飼育していたという(3)。1885年10月に欧州視察を行なった吉田は、開墾地委員片桐助作にロンドンから宛てた書簡のなかで、次のように語っている。
吉田知行書簡(1885年10月24日片桐助作宛より抜粋)
歐州ハ国ノ大小気候ノ寒暖ヲ問ハズ七、八分ハ牧場ト牧草畑ナリ。日本ノ米作ト一般ナリ。而シテ肉食ノ有益ナルコトハ理論ニ於イテモ実際ニ於イテモ強ユベカラザル事実ナリ。又運搬耕耘ニ牛馬ヲ使用スルノ有益ナルコト同様ナレバ将来日本ニ於イテ家畜ノ盛ンナルハ期シテ待ツベキ形勢ナリ。…(中略)…目下野田生ニテ牧牛ヲ為シ漸ク牛乳ヲ産スルモ未ダ牛乳ノ人体ニ必需ナルヲ知ラザレバ之レヲ需用スルモノナク、徒ラニ之レヲ放擲スル如キコトモアルベク…(中略)…然レドモ肉食牛乳ノ必要ヲ知リ運搬交通ノ便利能ク開クルノ時ニ至レバ何程野田生ノ牧牛ヲ拡張スルモ近傍二三箇村ノ需用ニモ足ラザルベク…
(『ゆうらふ』第8号に掲載の手紙を一部修正)
この手紙の中で吉田は、当時の牛乳需要に関して、一般的に栄養価の高い食物としての認識が不足しており、肉食・牛乳飲用の必要性が知られ、運搬交通の利便が開かれればその将来性があることを強調している。
この頃、一部の独身移民は、在来農法ではなく欧米式の主畜農法による開拓を試み、1882年には吉田知行の弟にあたる小寺?を中心に独身青年約10人が鷲ノ巣地区に共同経営農場である「鷲巣牧馬会社」を設立し、「鷲の巣耕舎」として、洋式農具を備え最新の知識を駆使して開墾に着手した。しかし、1886年には耕舎が火災に遭い農機具が全焼してしまい、翌年には解散の憂き目を見た(4)。また、1883年には野田追(5)にも鷲の巣耕舎に倣った「野田追耕舎」を組織したが、こちらも見るべき成果は上がらずに解散することとなった。
野田生牧牛社も1895年の大雪と飼料不足で多数の牛が死亡したため、事業は閉鎖された。当時すでに馬鈴薯澱粉製造が軌道に乗りはじめていたこともあり、酪農の合理性は顧みられることなく翌1896年に解散に追い込まれた(6)。こうして初期の酪農は大きく発展することはなく、再び日の目を見るのは澱粉価格の大暴落以後のことであった。
水田稲作の失敗
早い時期から西洋農法が注目される一方で、水田稲作や養蚕など在来農法の試みは続けられていた。1878年は移住時期が遅れたため収穫はほとんどなかったものの、翌年から本格的に農業が行なわれ、麻・大豆・小豆・粟・黍・玉蜀黍などは順調に生育し、十分に収穫することができた。また、養蚕も1879年は各自とも飼育経験がなく取扱い方法に難があったため収穫は少なかったものの、翌年には開拓使大野養蚕所において養蚕方法の研修を受けたため、前年よりも良好な結果をおさめた(7)。
しかし、水田稲作の場合は順調にいかなかった。1881年には官費により水田用水路が開発され、はじめて水田5町1反2畝10歩を開いたものの、結果はほとんど収穫を得ることなく無効に終わった。1881年の収穫は「土壌未ダ熟セズ耕耘未ダ精カラズ之ニ加フルニ風雨ノ害ヲ以テシ十分ノ登熟ヲ得ズ」わずか8斗に過ぎなかった。1882年も「苗ノ枯死スル者多ク生暢疾カラズ九月中暴風モ幾分カ害ヲ與へ」収穫は6石9斗2升、1883年には「少量ナガラ収穫アリ、其籾?ヲ脱シ精ゲ試シニ内地下等米ノ品位ナルヲ得タリ」として9石5斗6升の収穫を得たものの、1884年には「發芽ノ頃洪水ノ爲苗代田泥水ヲ被リ悉ク腐敗」したため、収穫は皆無であった(8)。
このような水田稲作の失敗は、田畑を中心とした伝統的な農業により開拓を推進しようとした当初の計画に打撃を与え、移民の生計自立のための大きな障害となった。
水田稲作が失敗したのには理由があった。八雲は三方向を山に囲まれ、とくに西部は標高800メートル級の山々が連なり、東部のみ内浦湾(噴火湾)に面する地形である。毎年6〜8月になると太平洋から南東季節風(ヤマセ)が吹いてくるが、八雲ではこれを真正面から受け、しかもヤマセが伴ってくる海霧は八雲西部の山々を越えることができない。このため、山々に遮られた海霧が八雲に溜まることとなり、この地に過度の湿潤をもたらし、作物の生成を著しく阻害するのである。下表は、1977年から86年までの間に毎月平均して何日間海霧がかかったかを示したもので、毎年6〜8月は平均して月に20日以上は海霧がかかることを示している。
(表10) ヤマセのため海霧のかかる日数(単位=日)

※『ゆうらふ』第28号より作成。
加えて、八雲の土壌は駒ヶ岳系統の火山灰または泥炭層で被覆されているところが多く、水はけも悪いことから、土壌地質の面でも農業適地とはいいがたいものであった(9)。これらの気象・地質上の制約のため、八雲は稲作にはまったく不適な土地であった。したがって、現在北海道では北見・旭川など道北に至るまで広く稲作が普及していながら、八雲では道南にもかかわらず、気象と地質の制約により現在でも水田稲作農家は皆無に近く、わずかに比較的気象条件の良い南部で細々と行なわれているにすぎない。
このような厳しい気候や土壌の条件に直面して、しだいに八雲では本州で伝統的に行なわれてきた農業を継承するよりも、八雲の厳しい自然条件に適応した独自の農業形態を発達させる必要があると認識されるようになった。
副業としての養鶏
士族移民の副業として広く定着したものとして、養鶏があげられる。愛知県では名古屋コーチンが生まれたほど養鶏が盛んであり、愛知県からの移民が多い八雲では入植早々から副業として養鶏が行なわれていた。士族移民の多くも、郷里において養鶏の経験があり、他の副業よりも容易に手がけることができたので、養鶏は副業として広く定着し、全農家が飼育するまでになった。1879年には徳川家開墾試験場で26羽が飼育されており、以後1880年には142羽、1881年には292羽、1882年には600羽、1883年には729羽と、年々増加の一途をたどり、販売・自家用とされ、鶏糞の肥料化も奨励されていた。
なかでも青年舎出身の八尾吉之助は養鶏事業に熱心であり、積極的な増殖・設備投資を行なったほか、八尾式仮母器(育雛器)を発明して養鶏事業の発展に貢献した。こうして八雲の養鶏事業は順調に伸展し、年間孵化数1万数千羽を数え、1913年には50羽以上の飼養戸数だけでも162戸に達していた。雛は道内各地をはじめ弘前・樺太方面まで広く販売し、鶏卵も各地に出荷していた。なお、当時八雲で飼養されていた品種としてはハワード系白色レグホン、名古屋コーチンが多かったという(10)。
馬鈴薯栽培の開始と澱粉製造の勃興
北海道における馬鈴薯栽培の歴史は古く、すでに18世紀初頭には北海道に普及して、寒冷地における救荒作物として定着しつつあった。開拓使もまた北海道農業の開発を進めるにあたり馬鈴薯に注目し、その普及につとめた。
八雲における馬鈴薯栽培は、1878(明治11)年に七重勧業試験場から配布を受けたアーリーローズ種8俵を元に栽培したのがはじまりとされている。馬鈴薯は地中で育つので、八雲のような湿潤冷涼気候かつ火山灰性土壌の地でもよく生長し、八雲の適作物とされた。こうして馬鈴薯の作付面積は急増し、1893年の27.4町歩から1900年には315.7町歩を数えるに至り、総作付面積のおよそ3割を占めた(表11)。このような馬鈴薯の作付増加の要因は、馬鈴薯が八雲の気候風土に適したものであっただけでなく、当時、馬鈴薯を原料とする澱粉製造が脚光を浴びるという時代背景があったからである。
(表11) 八雲における馬鈴薯作付面積の比率の推移(単位=%)
1879 | 1883 | 1888 | 1893 | 1900 | 1914 | 1915 | 1918 | 1919 | 1925 | 1930 | |
馬鈴薯 | 16.5 | 7.1 | 3.2 | 4.8 | 29.5 | 32.1 | 47.2 | 45.8 | 43.9 | 6.1 | 7.8 |
総反別 | 239 .600 | 1165 .110 | 1960 .706 | 5722 .202 | 10712 | 8012 .200 | 8888 .300 | 10098 | 10325 | 15031 | 14464 |
*林1955・1956・1963より作成。
八雲における馬鈴薯澱粉製造は、1882年に士族移民の辻村勘治がわさびおろしで擦り下ろして片栗粉を造ったのがはじまりであり、1885年には徳川家開墾試験場直営事業となったが、すべてを人力に頼る製造方法であったため、経費がかかる割には生産が上がらなかったので伸び悩んでいた。
しかし、1892年吉田知一(吉田知行の子)らが原動力に水車を利用して効率を高めた澱粉製造を開始すると澱粉製造は注目を集め、1900年には士族移民の川口良昌が、澱粉製造が八雲に最適の農村工業であり有望な事業であることを提唱して研究を進めた結果、「川口式澱粉製造器」を考案し、澱粉製造の省力化を図り製造効率を高めた。こうして澱粉製造は飛躍的な発展を遂げ、1897年の製造戸数24戸が1904年には241戸となり、生産量も123万8930斤、生産額9万5358円に達した(11)。
1905年には青年舎出身の内田文三郎を組合長に「八雲片栗粉同業組合」が結成され、製品検査を行ない品質の向上を図り、品質を雪月花の3等級に区分した。1906年には馬鈴薯の作付面積は3201町歩となり、八雲の馬鈴薯澱粉は「八雲片栗粉」として名声を博し国内はもとより海外にまで販路を広げ、1907年には全国一の高値で取り引きされるようになった(12)。また、徳川農場でも馬鈴薯の研究を行なって、品種改良を盛んに行なっていた。
「澱粉景気」とその結末
1914(大正3)年に第一次世界大戦が勃発すると、オランダ産やドイツ産の馬鈴薯澱粉の輸入がストップしたので、澱粉は一躍重要な海外輸出品となった。こうして澱粉価格は急騰し、八雲の馬鈴薯農業も空前の発展を示した。1915年には八雲の総作付面積の約半数が馬鈴薯となり、連作による連作を重ねて栽培した。
馬鈴薯は多肥を要求する作物であり、すでにこのころには連作による地力の消耗と病害虫による被害も発生し始めていた。堆肥だけでは到底間に合わず、プラウによって表土の下の火山灰層を鋤き起こしていわゆる深耕を行なうとともに、大量の大豆粕と過燐酸石灰を中心とした肥料投入を繰り返して対応し、馬鈴薯の収穫時期には八雲の労働力だけでは足りないので、他の町村から「芋掘り出面」(13)を連れてきたほか、運搬も八雲の馬の数では足りないので、遠く日本海側の町村からも馬を連れてきた。こうして八雲には「澱粉成金」と呼ばれる人たちも見られるようになり、空前の好景気は「澱粉景気」といわれるほどになった。八雲村はこの間、1902年に山越内村を合併していたが、その後の好景気に支えられ人口も急増した結果、1919年には町制が施行され八雲町となっている(14)。
しかし、こうした「澱粉景気」は一時的なものであった。1918年に第一次大戦が終結し、翌1919年に講和条約が締結されると、ヨーロッパでオランダやドイツの澱粉が市場に復帰するようになった。このため、八雲の澱粉は売れなくなり、澱粉価格も大暴落して、澱粉1箱(100ポンド)20円まで暴騰していたものが終戦後は一挙に3円80銭にまで下落し、安くても売れないという極端な不況に陥った。このため、澱粉製造事業は一転して不採算事業になり、多くの工場が放棄されることになった。好景気時に店から借りた肥料代などが澱粉価格の暴落で支払えなくなり、莫大な負債を抱え生活に困窮して夜逃げする者も続出するようになった。
また、新たに澱粉用馬鈴薯に代わる作物を育てようとしても、連作につぐ連作で土壌はすでに痛め尽くされ、甚だしく地力は消耗していたうえ、肥料を購入する金もなくなっていた。その結果、荒れ果てた土地を残して離農する者が続出し、農家戸数は激減した。馬鈴薯の作付面積も減少したが、馬鈴薯は依然としてこの地方の適作物であったので、八雲に残った農民たちは澱粉に代わる新たな馬鈴薯の商品化の必要に迫られた。
徳川農場では澱粉景気の最中の1915年に「八雲馬鈴薯研究所」を設立し、農事試験を行ない、品種改良や疫病予防の研究に取り組んできており、男爵芋が疫病に強い品種として栽培され始めていた。道内外からの種子の分譲申し込みにこの品種を紹介したことから、男爵芋が種子用馬鈴薯として定着し、これ以後八雲は道内有数の種子用馬鈴薯生産地となっていった(15)。
しかし、他方ではいわゆる略奪農法により痛め尽くされた地力を回復させる必要があり、それを解決する方法として酪農が再び脚光を浴びるようになっていく。
酪農への転換
前述のとおり八雲酪農の歴史は古く、1906年には山崎地区にあった石川牧場が牧牛事業に着手し、翌年からバター製造を開始して「笹印バター」として本州方面に売り出している。澱粉原料用馬鈴薯を中心とした農業は地力の低下を招き、略奪農業の様相を呈しており、「土づくり」のための有畜混合農業の必要性はしだいに認識されるようになり、酪農導入への素地はできあがりつつあった。ただし、馬鈴薯澱粉製造の全盛期においては、酪農は一部の篤志家を除いてあまり顧みられることなく、1918年ごろの飼養頭数はわずか200頭前後に過ぎなかった。
第一次世界大戦後の澱粉価格の大暴落は、八雲の農業に致命的な打撃を与え、一挙に離農転住する者が続出した。こうした八雲農業の危機に直面して、馬鈴薯に代わる八雲の気候風土に適応した農業形態を導入する以外に、八雲農業再建の道はなかった。こうして、八雲にもっとも適した農業として再び脚光を浴びたのが酪農であり、酪農への転換にあたっても指導的な役割を果たしたのは旧尾張藩士の子孫たちであった。
1920(大正9)年、当時の徳川農場長で青年舎出身である大島 鍛は、農場内の農民を説得して各部落に「畜牛組合」を組織させ、酪農業への転換を啓蒙した。同年には大島農場長自らが連帯保証人となって北海道拓殖銀行から資金を借り入れて、翌1921年に知内・木古内から雌牛を共同購入して飼養させた。また、1922年には旧尾張藩士出身の梅村多十郎が木古内・知内・上磯方面から58頭の雌牛を購入し、一般農家や小作人に貸与して酪農の普及に努めた。このような努力の結果、飼養頭数は年々増加し、1929年には2000頭を突破し、1930年には乳牛2476頭・飼養戸数787戸・乳量3万1875石・金額46万8881円と目覚ましい発展を遂げたのであった(16)。
乳牛の増殖に伴い堆厩肥が増産され、地力も徐々に回復に向かった。また、当初牛乳は個人経営の製酪が中心であったが、積極的な乳牛増殖の結果、生産される牛乳の販路確保のために練乳会社の分工場誘致を行なうことになり、1922年6月、北海道煉乳株式会社が仮設の集乳所を造って牛乳の受け入れを開始し、翌7月には八雲工場として本格的な操業を開始することとなり、酪農八雲の基礎がここに築かれたのであった。
酪農の発展
八雲町の基幹産業が酪農に転換してからも経営は順風満帆ではなく、1931(昭和6)年に大日本乳製品株式会社の乳価値下げと原料乳の受け入れ制限の方針に端を発し、団結派農民と会社擁護派農民との間で争われた牛乳騒動や、1936年のトリコモナス原虫による繁殖障害など紆余曲折があったが、この間にも八雲酪農は順調に進歩しており、乳牛の飼養頭数は年々増加していった。1939年には乳牛頭数3494頭・飼育戸数835戸・1戸平均4.2頭を数え(表12)、酪農もついに安定した域に入ったとして、「乳牛感謝の碑」が建立されている。
また、1935年頃にはこれまでの乳牛を加味した混同畑作農業から、飼料作物を中心とする輪作体系を取り入れた本格的な酪農方式が確立され、以後八雲は「酪農時代」に入っていった。
農民の中には、酪農経営について常に起こる数多くの問題を研究しようとする共同研究グループ「八雲酪農科学研究所」を組織するものもいた。彼らは農会・徳川農場や乳牛会社の協力も得て、土壌の改良・防風林の造成・飼料の栽培・落等乳の原因究明などの諸問題に取り組み、八雲酪農の発展に尽くした(17)。
しかし、第二次世界大戦が激しくなると、男子壮年者が相次いで徴兵されたことにより基幹労働力がいなくなり、飼養頭数も減少するなど酪農は低迷することとなった。
(表12) 八雲における乳牛飼養頭数の推移(1878〜1942年)
1878 | 3 | 1891 | 51 | 1904 | 84 | 1917 | 214 | 1930 | 2476 |
1879 | 11 | 1892 | 68 | 1905 | 92 | 1918 | 256 | 1931 | 2531 |
1880 | 10 | 1893 | 51 | 1906 | 96 | 1919 | 176 | 1932 | 2755 |
1881 | 27 | 1894 | 56 | 1907 | 87 | 1920 | 201 | 1933 | 3040 |
1882 | 52 | 1895 | 58 | 1908 | 101 | 1921 | 313 | 1934 | 3393 |
1883 | 64 | 1896 | 73 | 1909 | 186 | 1922 | 448 | 1935 | 3196 |
1884 | 52 | 1897 | 72 | 1910 | 162 | 1923 | 694 | 1936 | 3299 |
1885 | 52 | 1898 | 76 | 1911 | 267 | 1924 | 1106 | 1937 | 3059 |
1886 | 36 | 1899 | 40 | 1912 | 187 | 1925 | 1160 | 1938 | 3282 |
1887 | 48 | 1900 | 35 | 1913 | 257 | 1926 | 1338 | 1939 | 3494 |
1888 | 56 | 1901 | 36 | 1914 | 172 | 1927 | 1560 | 1940 | 3642 |
1889 | 54 | 1902 | 36 | 1915 | 174 | 1928 | 1790 | 1941 | 3623 |
1890 | 60 | 1903 | 40 | 1916 | 184 | 1929 | 2025 | 1942 | 3489 |
*『農協四十年史』より作成。
5-2移住初期の生活の状況
士族移民の移住当初の生活
尾張徳川家からの士族移民には新築の移住人家屋が割り当てられ、同時期に建てられた屯田兵屋などに比べると立派なつくりであったが、名古屋の武家屋敷とは比べ物にならない粗末なものであった。移民の住居は、間口5間半(約10メートル)・奥行3間半(約6.4メートル)の長方形に1坪半の便所を付けたものであり、西側に6畳と4畳半が各2部屋ずつと押入れが、東側に約10平方メートルの土間があった。天井はなく、農具・農産物置場となっていた。また、一部は踏天井となっており、その上で蚕が飼えるようになっていた。西側の部屋の一部は囲炉裏となっており、冬期は薪を炊いて暖房の場となった。
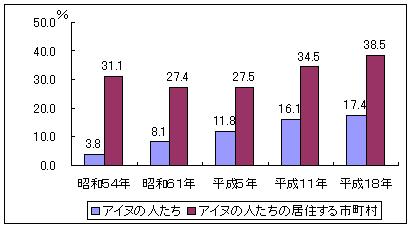
士族移民の開拓初期の住宅(復元、八雲町郷土資料館)


開拓初期の士族移民の住宅内部(復元、八雲町郷土資料館)
移民たちはまず、家の周りの草を刈り、木の根を掘って5日も6日も天日で乾かして火をつけ、焼けた跡を唐鍬で耕し、土を砕いて畑を作り、二畝・三畝と開墾した荒れ地に野菜や大根・馬鈴薯などを蒔いた。
こうして初年度は筋まき・坪まきなどによって食糧となる大豆・小豆・蕎麦・玉蜀黍などの自給作物を栽培した。新墾の畑は肥料を与えなくても収穫はあったが、開拓初期は一家の1年間の食糧が自給できれば上々であった(18)。
秋の収穫が終わると、家の近くに穴を掘って越冬用の馬鈴薯や野菜を貯蔵し、大豆は蒸して麹を入れて味噌を作った。小麦や蕎麦はひき臼で挽いて粉にし、うどんや蕎麦にした。このため臼はどの家にもあって、これを回すのは子どもたちの仕事であった。春先にはヨモギを摘んでおき、草もちなどをよく作ったという。このほかとろろ汁などもよく作られた(19)。
それまで温暖な名古屋の地で生活してきた士族たちにとって、道南とはいえ北海道の冬の寒さと雪の多さは想像を絶するものであった。大雪のため隣家との行き来もできないことすらあった。徳川家では移住者のために開墾地内に設置した板蔵で日用品や味噌の購買や貸与及び農産物の取扱いを行ない、米は函館から船で運んでいたが、大雪のために浜辺まで食糧を取りに行くことができなかったこともあった。また、遊楽部に到着した船が破船し、荷物や食糧が流されたこともあったという。このため、冬期は食糧の欠乏に悩まされることもしばしばあった(20)。
しかし、移民たちは徳川家による手厚い保護があり、最初の数年は米であるかどうかは別にしても食糧を支給されていたので、これ以上の飢えに苦しむということはなかった。
また、移民たちは寒さだけでなく、ヒグマの被害にもしばしば悩まされた。ヒグマは収穫前の畑の作物を荒らして食べてしまうだけでなく、牛や馬などの家畜を襲うこともしばしばあった。このため、地理に詳しいアイヌの人びとを雇い、鉄砲や仕掛け弓(アマッポ)を用いて熊狩りをしばしば行なった。初年度に移住した土岐冬麻呂は後年、次のような手紙を残している。
我々移住の翌年明治十二年吉田知行宅の西に大根を蒔しに最早抜き取らんとするころ知行は朝起出畑を見廻りしに、立派なりし大根は鋭利なる刃物にて沢山に切られたるに驚き能くみれば巨熊の足あと点々として見えたり、時に知行がおもへらく、移住人は此地に来り寒気と熊に恐れをなしたる場合此有様を知らしむるは開墾の事業に妨ならむと自ら手もて熊の足跡を消し匿し、馬鹿人間の悪戯として了りしが、約二十幾年の後此地に帰り或集会の席上始めて此時の有様をもの語り一同に当時の恐怖を偲ばしめたり、知行は徳川家より開墾事業の委員として遺され責任を帯び移住者を督励し発展を期待せし為斯く深き慮を為せり
初年移住人 土岐冬麻呂記す
(『八雲町史』より引用)
受け継がれた士族の生活習慣
士族としての風流のたしなみは八雲に移住したのちもしばらくは続けられた。尾張藩では俳諧や茶道が盛んであり、徳川慶勝から最初に移住を諭された角田弟彦は歌人として名の知られた存在であった。また、国学では本居宣長の系統を受け継いだ佐治爲泰・市岡金三郎などや、平戸藩学楠本端山の系統を受け継いだ海部昻蔵・片桐助作・小寺 ?など、八雲に移住した士族たちは江戸時代に国学・和歌・漢文・俳諧・茶道・洋学などを学び、高い教養を身につけた人たちが多かった(21)
とりわけ角田弟彦は八雲に移住したのちもさかんに歌会を催し、1920年に81歳で没するまで2万首以上にもおよぶ和歌を残している。1879年だけでも33回の歌会を行なっており、士族移民各自の家を回り持ちで行なわれた(22)。移住当初は開拓の厳しさや故郷への望郷の思いを詠んだ和歌が多かったものの、時を経るにつれ八雲の自然の美しさを見出し、それを詠んだ歌が増えてくるのが特徴であり、そのいくつかを紹介する。
かや刈りと谷地に入りたち今日もまた わが手末は血に染まりつつ(1878年)
我が君の御言かしこみ荒熊の 羆伏す野に庵してけり(1878年頃)
羆すむ野べすきかへしすきかへし かへすがへすも故郷ぞ思ふ(1879年頃)
やがて今雪に絶えなん山路を 先づ埋むるは木のはなりけり(1879年頃)
久方のあらぬかつらもわか葉して 八雲が原に夏は来にけり(1880年)
荒熊のひ熊ふす野とうとみしは 花を見ぬまの心なりけり(1880年前後)
息絶えんときのくるしさ知らねども 目やみの今にまさらざらまし(1920年、辞世)
また、武家出身らしく、八雲神社の例大祭などでは余興として、射的・柔術・剣術の競技や競馬、さらには蹴鞠などの奉納が行なわれている(23)。
八雲に移住して新しい生活を始めても、当初の生活は名古屋時代と変わらなかったという。しかし、八雲での生活は決して楽なわけではなく、名古屋時代と変わらない派手な生活は家計を圧迫することともなった。そこで、士族移民一同は1883(明治18)年に以下のような「定約書」を締結して、贅沢を戒めて質素倹約に努めることにした。この史料は、締結される以前の移住者たちの暮らしぶりを伝えるものとして貴重なものである。
定約書(全文)
近来社會ノ風潮華奢ニ流レ一朝米價下落ノ際ニ偶ヘハ倉皇措ク能ハス忽チ活計ノ道苦シムヲ以テ神速救済ノ方法ヲ設置セスンハ有ルヘカラス俚諺ニ之レアリ曰ク一利ヲ興スハ一害ヲ除クニ如カス故ニ村民一同集會ノ上左ノ十有五ヶ条ヲ審議決定イタシ候事
一、 盆歳暮各自互ニ進物等一切致サザルコト
但他ノ町村ヘハ此限ニ非ス
一、 平生衣服ノ儀ハ一切綿服タルヘキコト
但奥縞双子識糸結城位ヲ最上トシ然レトモ諸禮式ノ儀ハ此限ニ非ス
一、 履物ノ儀ハ表附一切履間敷事
但現近所有ノ物ハ検印ヲ以テ相用ユヘシ
一、 祭リ餅ノ儀ハ親類朋友タリト取遣致ス間敷コト
一、 上棟賄ノ儀ハ饗應ヶ間敷儀ハ一切致ス間敷コト
但蒸物ノミ配附スヘシ小児ノ豆粥ハ從前ノ通リ
一、 遠近又ハ親類ニ限ラズ興行事及頼母子等ノ依頼ハ一切相断リ可申コト
但親類カ又ハ親類アル村ヨリノ頼ミナレハ其身壱人ニ限ルヘシ然レトモ隣村ノ興行ノミハ時々衆議ヲ以テ相定ムルモノトス
一、 社寺又ハ種々ノ名目ヲ附シ寄附寄進等申来ルトモ一切相断リ可申コト
但親類アル村ヨリノ頼ミハ其身壱人ニテ止ル決シテ他人ヲ誘フヘカラス
一、 婚禮賄ノ儀ハ出立落付等ノ送リ膳又ハ弘メ式及近所ヨビ等一切致ス間敷コト
一、 五節句ノ祝儀ハ廃止ノコト
一、 謝恩講賄ノ儀ハ葉粥漬物ニ限ルコト
一、 社寺参詣又ハ寄納等ノ送リ向ヒ及見舞等一切廃止ノコト
但伊勢参宮ハ此限ニ非ス
一、 安産又ハ産ミカザリ祝膳及子生レ餅配布等一切廃止ノコト
但親類ハ此限ニ非ス
一、 年忘レ弔祭等ノ砌ハ茶漬煮染味噌汁ニ限ル 酒ハ三献引落シノコト
一、 葬式ノ儀ハ握飯煮染和布蒟蒻味噌汁ノ外ハ一切用ユ間敷コト
但アケ?夜モ葬式賄ニ準ス
一、 遠近ニ限ラス親類葬式有之節ハ近所出入又ハ懇意ノ者ト雖モ其主人ノ依頼ニアラスンハ参詣スルコトヲ得ス
右倹約ノ条々ハ本年一月ヨリ来ル明治二十年十二月迄満五ヶ年間其間各堅ク相守リ可申候因テ一統連名調印スルコト如件
(八雲史料482、「定約書」)
さて、名古屋は徳川宗春の時代からの伝統なのか、普段着や冠婚葬祭の派手な土地柄である。八雲でも移住当初は派手な服装をしている者が多かったようである。また、名古屋では現在でも祭りの際に餅をついてやり取りする風習や、上棟祝いに派手な接待を行なう家庭が多いが、八雲でもそれが引き継がれていたようである。
さらに、移住者の間では「頼母子講」が開かれていたようである。頼母子講とは「無尽」とも呼ばれ、仲間数人が集まって掛け金を払い、そのまとまった金を仲間内でもっとも困っている人間に融資するものであり、すでに鎌倉中期には行なわれていたことが確認できる金銭の相互補助システムである(24)。
「五節句」とは、正月7日(人日。七草の節句)・3月3日(上巳。桃の節句・雛祭り)・5月5日(端午。菖蒲の節句)・7月7日(七夕)・9月9日(重陽。菊の節句)であり、とりわけ5月5日は「菖蒲」を「尚武」とかけて、尚武の節日として盛んに祝う習慣があった。
「謝恩講」が見受けられるのは、愛知県は浄土真宗門徒が多く、移民の間でもこれを信仰するものが多かったためであろう。移住当初は八雲に寺院はなく、全員が神道の信者ということになっていたが、実際には浄土真宗の伝統行事は行なわれていたようである。また、「アケ?夜」とは「忌み明け」のことであり、四十九日のことを差すものである。こうした葬送儀礼の際には豪華な食事が出されていたことを示している。
ところで、士族移民には1889年に制定された開墾地郷約によって、徳川家に対する「御機嫌伺」が義務付けられていた。御機嫌伺には2種類あり、1つは年始の御機嫌伺、もう1つは例月の御機嫌伺であった。年始の御機嫌伺は、毎年正月元旦に開墾地事務所に出頭し、飾られてあった徳川家当主の写真を拝み、年賀帳に記帳するというものである。例月の御機嫌伺は、毎年4月15日・10月15日に同じく事務所に出頭し、徳川家に挨拶をするというものであったが、郷約制定前の日誌によれば、ほぼ毎月御機嫌伺を行なっていた時期もあった(25)。
また、この2つの御機嫌伺のほかにも、徳川家当主が来場した際には、士族との懇親会がもたれたが、これに先立ち各自が事前に当主に面会して挨拶をするという形の御機嫌伺も行なわれていた。
小作移民の状況と生活習慣
八雲には旧尾張藩士以外にもさまざまな移民がいた。士族移民が住み始めるより前に八雲に住んでいた人々は少なく、先住民族であるアイヌの人びとの家が20〜30戸程度、和人の家が10戸程度のみであった(26)。八雲に本格的に和人が移住したのは、徳川家開墾地が1886(明治21)年に野田生地区に平民出身の小作人を移住させたのが契機である。
徳川家開墾地では、当初は小作移民も愛知県出身者に限定して募集していた。とりわけ1892年ごろまではもっぱら東春日井郡(現在の春日井・小牧市周辺)出身者のみを募集しており、八雲町内では現在でも春日という地名が残っている。1892年以降も、1897年ごろまでは依然として愛知県出身者のみが選ばれ、年平均10数戸が八雲および野田生地区に移住していた。したがって、1897年ごろまでは八雲および野田生地区は、その人口の大部分が愛知県出身の士族または平民で占められ、あたかも「愛知コロニー」ともいうべき状況を呈していた。
実際、愛知県から北海道に移住する場合は、まず八雲に行き、そこで満足する土地を得られない場合は、石狩郡生振村など道内の他の地域に入植する人が多く、八雲は愛知からの移民が集まる拠点の役割を果たしていた。このため、徳川家開墾地以外の農場でも、石川農場・宮村農場・鈴木農場など愛知県出身者の割合が高い農場が多かった。愛知県から北海道に移住した人々は、全体的に見ればそれほど多いわけではないが、この時期に愛知県からの移住が多かった理由としては、1891年10月28日に起きた濃尾地震で、愛知・岐阜県内で壊滅的な被害を受け、生活に困窮する農民が増えたことがあげられるだろう。1897年には愛知県は547戸2301人の移民を送出しており、全国第8位となっている(27)。
移住当時の小作移民の生活文化が具体的にどのようなものであったのかに関する史料は残されていないが、1910年頃の徳川家開墾地による「八雲村徳川家開墾地沿革」という史料には、この当時の愛知県出身小作移民移住地の様子が描かれているので紹介する。
一 徳川家開墾地小作人沿革(一部)
徳川家開墾地カ小作人ヲ募集シ入場セシメタル明治二十一年初メテ五戸ヲ字野田生ヘ移シタルヲ以テ始メトス以来二十二年ニ又五戸ヲ移シ二十四年七戸ヲ二十五年二十四戸ヲ野田生ニ移シタル後ハ毎歳適宜之ヲ募集シ来レリ而シテ小作人ノ多クハ尾張國東春日井郡ヨリシタルモノ最モ多ク且ツ知己親戚互ニ相傅ヘテ呼應シ来リ往スルモノ専ラ尾張ノ産ナルモ以テ今ヤ他縣ノ人民ヲモ混スルアルモ野田生ハ殆ント他國ノ者ナク宛然小尾張見ルノ観ヲ呈セリ風俗人情已ニ同シ古来ノ風習慣例ヲ墨守シ小作料ノ上納ノ如キ頗ル円満ニシテ又煩累ヲ咸スルコトナシ…
(八雲史料452、「八雲村徳川家開墾地沿革」より)
この中で、1910年当時ではすでに他県出身者の比率もかなり増えているものの、野田生地区においてはほとんどが愛知県出身者で占められ、あたかも「小尾張」を見るがごとき様相であったとしている。
実際、徳川家開墾地では1897年以降は、愛知県以外からの小作人移住も認め、その数も年平均30数戸であったため、またたく間に小作人戸数は倍増し、結果として愛知県出身者の割合が相対的に低下している。これは士族に割渡されていた未墾地の開墾を1902年の成功期限に間に合わせるためであった。また、徳川家開墾地以外の農場も次々と創立され各農場も次々と小作人を募集して開墾に努めたので、八雲村の人口は年々増加し、1902年には山越内村を吸収合併し、1919(大正8)年には町制を施行するに至った。
小作人移民の出身県別内訳は、1912年の統計によれば、徳川・石川・八雲(鈴木)・岡田(久留米)・西田・若松・岩磐・宮村・中藤・増田の各農場における小作人戸数744戸のうち、愛知県出身者が324戸(43.5%)と最も多く、次いで石川県75戸(10.1%)・宮城県70戸(9.4%)・福島県45戸(6.0%)・福井県38戸(5.1%)・岐阜県38戸(5.1%)・青森県32戸(4.3%)・その他154戸(16.5%)となっている。徳川農場に限れば小作総数319戸のうち210戸(65.8%)が愛知出身であり、とくに野田生農場はほとんど愛知県出身者のみによって開墾されたので、1932年の段階でも82.7%の小作人が愛知県出身であった(28)。
ただし、1910年当時の八雲村全体の戸数は3039戸であり、当時の愛知県出身移民はほとんど農業従事者であったため、愛知県出身者の割合は、1912年の段階でも小作移民の324戸と士族移民の75戸を足した約400戸に過ぎず、村全体から見れば愛知県出身者の割合は13%程度である。農業従事者を除いた約2300戸は、商工業従事者と漁業従事者が多く、これらの人々は東北・北陸出身者が多いと推測される。とりわけ漁業従事者は東北出身者の割合が高いので、村全体で見れば東北出身者の割合が必然的にもっとも高くなるものと思われる(29)。
小作人移民の生活は、士族移民のものと比べて厳しいものであった。士族移民の生活に対してはさまざまな保護制度や援助があったのに対し、小作人移民にはなく、住居も士族移民のものと比べても粗末なものであった。彼らの住居は草葺きの丸太小屋が多く、床も丸太のままで、燕麦の穀を1尺(約30センチ)程度敷き詰め、その上にむしろを敷いていた。部屋の真ん中にはいろりがあり、割りまきを使ってたき火をして寒さをしのいだ。ストーブが導入されたのは大正初期頃からである。
なお、徳川農場関連の小作人に対しては、毎年正月には年賀の式が行なわれていた。これは、徳川家当主の写真を掲げ、年賀帳に記帳するというものであり、士族移民が行なった御機嫌伺と同一のものであった。年賀の式は、八雲農場で1月5日、ユウラップ農場で1月7日、野田生農場で1月15日という場合が多く、野田生農場での年賀の式では徳川農場長など農場関係者が列車などを利用して出張して行なっている。年賀の式の際には酒や汁粉などがふるまわれ、多数の参加者でにぎわった(30)。
5-3 生活文化の変化
衣類と住宅の変化
開墾当時の衣類は、故郷から持参してきたもののほかに、刺子と呼ばれる綿布を表と裏に合わせ細かく縫い刺ししたものを着て働いた。移民は農業に従事する者が多かったことから、活動性にすぐれた衣服が要求され、1902年頃からは東北地方からの移民が持ちこみ、活動性・防寒性にすぐれたモンペが各地で着用されるようになった。当時、外出着や晴れ着は和服が主流であったが、1920年代になると学校などで洋服が制服として採用されたこともあって、次第に洋服が流行しはじめた(31)。
履物は自家製の草履やわらじが中心であった。積雪の多い東北・北陸地方からの移住者が多いにもかかわらず、道内の他地域と同じくカンジキはそれほど普及していない。これは、雪質が違うためということもあるが、冬期の移動手段として橇が普及していたためでもある。
また、入植当時の住宅は前述の通り、一時しのぎに建てたきわめて粗末なもので、防寒設備も不十分であったので、ある程度生活が安定してくると、みな住居の建て直しを行なうようになった。農家では囲炉裏に代わり、まきや石炭をたくストーブが普及しはじめるなど、大正期以降、住宅の近代化が進んで行った。とくに大正中期以降、服装の洋風化とほぼ軌を一にして、住宅の洋風化も進み、文化住宅と呼ばれるトタン屋根2階建ての住宅が流行した。
八雲では酪農が次第に盛んになっていったので、折れ屋根付きの洋風畜舎やサイロが建てはじめられた。また、建築費がかさむためあまり浸透はしなかったものの、徳川義親が提唱した洋風の防寒保温住宅が1923・26年と試験的に建築されている。これはコンクリート造りまたは粘土造りで、内部にペチカを有する純洋風建築であり、徳川義親が欧米に外遊した際に見た現地の住宅を元に設計されたものであり(32)、今日道内各地で見られる防寒性にすぐれた住宅の嚆矢といえるものであろう。
食文化の変化
次に、食文化の変化について見ていきたい。八雲周辺では気象条件により米の栽培ができず、雑穀栽培が中心であったものの、徳川家開墾試験場への士族移民については、数年の間は東京の徳川家より米や味噌などの支給があり、米が主体の当時としては比較的豊かな食生活を送っていた。しかし、一般の小作人移民のほとんどは、米をなかなか口にすることはできなかった。そこで、当時の小作人移民の主食としては、米をとうもろこしや麦などと混ぜたものが食されていた。米は3分の1程度であり、残り3分の2がとうもろこしまたは麦であった。とうもろこしはひきわりにして粗いところを米や麦と混ぜて食べることが多かった。蕎麦や小麦は粉にして、手打ちそばや手打ちうどんとして食べたという。また、馬鈴薯・カボチャ・イナキビ・粟なども主な食糧となっていた(33)。
このほか、お菓子として、とうもろこしの粉を団子にしたものや、ヨモギから作った草もちもよく食されていた。また、黍から作った「黍オコシ」や、片栗粉に砂糖を加えてセイロで蒸した「澱粉ウイロ」も食されていたようである(34)。筆者が2006年夏に聞き取り調査を行なったところ、この「澱粉ウイロ」に類するものは1950年代頃まで食べられていたという。
第一次大戦中のいわゆる澱粉景気の時代には、好景気のため以前よりも米の量が増えた。しかし、澱粉景気は一時的なものであり、これ以後はまた粗食に甘んじなければならなかった。澱粉景気の終焉後、八雲では農業建て直しのため酪農への切り替えが行なわれたのは前述のとおりであるが、これに伴い、大正後期以降、食生活の中に牛乳やバター・チーズなど乳製品が入るようになったほか、この頃からバナナが大量に出回り、広く町民に食されるようになった。昭和に入るとシュークリームなどの洋菓子が店頭に陳列されるなど、食生活の洋風化が進んだ(35)。
このほか、副食として味噌漬けやフキ・コゴミ・ゼンマイ・ウドなどの山菜があり、また、ワラビやタケノコは乾燥させたり塩漬けにしたりして冬期の保存食にしたという。漬物ではこのほかに、身欠きニシン・大根・ニンジン・キャベツ・白菜などでつくったニシン漬けやたくあんなどが多くの家庭で作られていた。
調味料では、徳川家開墾試験場の士族移民の場合は、これも当初数年は徳川家より支給されていたが、一般の小作移民の場合は醤油や砂糖は購入することが多く、味噌はほとんどの農家で作られていた。
動物性のものでは、鶏卵は養鶏が広く普及していたため、多くの農家で自給可能であった。肉類は一般にそれほど食べられず、とくに開拓初期は「4つ足のものは食せず」という明治以前の習慣が根付いておりあまり食べられなかった。一方で魚類はイワシやサバなどが豊富にとれたほか、行商人からイワシ・サバ・ホッケなどを仕入れ、塩漬けやぬか漬けにして保存食とした(36)。また、道南地区一帯に伝わる郷土料理として三平汁は広く普及している。
一般的にハレの日の食事以外は、上記のような質素なものであった。士族移民も、若干恵まれているとはいえ、補助打ち切り後はそれほど小作移民と大差があったわけではない。しかし、徳川家開墾地ではしばしば華族関係者や開拓使関係者などが視察に訪れており、その際に出された食事は豪華なものであった。一例を示すと、1887年10月17日に徳川家代理として堀理事官一行が視察に訪れた際は、「鶏肉仕立薩摩汁 ソイマクロ差身 鮭塩焼 丼 鶏肉百合ツク子芋 トロヽ汁 香物 牛蒡乃漬」を提供している。また翌18日の朝食では「向ブリ切身 ブリ切身 芋ノ葛煮 香物 浅漬大根 日本酒 麦酒」を提供している。このほか、1890年1月15日には「ライスカレイ」が提供されており、これはおそらく八雲でカレーライスが提供された最初の記録であろう(37)。
ことばの変化
士族移民たちが話していたのはもちろん名古屋弁であった。名古屋弁には話す階層によって武家言葉・上町言葉・下町言葉・芸者言葉の4種類があったが、八雲で話されていた名古屋弁は、この中でも特殊な武家言葉に属しており、語彙も現在名古屋で話されている名古屋弁とは異なる部分が多い。現在は名古屋でも消滅した言葉であり、1955年頃に名古屋から八雲を訪れた人が八雲に残る武家言葉を聞いて感動したという話も伝わっているほどである。前出の『村の創業』には、士族移民が移住当初に話していた言葉がいくつか出てきているので、いくつか紹介することにする。
「まあ何誰だえも……おゝ省様か、お畑の手傅かえも、えらい事えらい事。」
「さあ皆やらないかんじょん。」
「お前此處はお船の中だぞよ、大須へはもう行けぬわな。お前は知らんせんがお船は北海道へ行つてしまふのだぞよ。」
「まあお前のやうに困るでないかよ、此處はお船の中だがや、皆様が笑やあすぞよ。」
「まあ今夜は何もあれせんがなも。」
「おいおい、あそこの楢の木の下に、今羆が寝てをるで氣を付けさつせよ。」
「いかいこと捕れたなも。」
「もうお國ではお彼岸だで、お彼岸櫻が咲く頃だぞえも、お天氣のよい日には、田舎へ行くと田螺が田の中から這ひ出して、ぞろぞろと歩いてをる頃だぞえも。」
(都築1916より抜粋)
このほか、士族移民の間では人名のあとに「そん」をつけて、「○○そん」という表現がよく用いられた。「そん」とは、漢字で書くと「尊」であり、「○○さん」という意味であり、武家ならではの表現である。
また、士族の間では次のようなわらべ歌が伝わっていた。同様のわらべ歌は士族に限らず、名古屋地区では広く歌われていたが、士族のものは武家言葉になっているのが特徴である。
田螺殿田螺殿、お彼岸参りをさつせぬか。
お彼岸参りはしたけれど、鴉と云ふ黒鳥が、足つゝき、目つゝき、
それでよう参らぬわいな。
(都築1916、133頁)
一方、人口面では圧倒的に多い小作人移民が話していた言葉については、記録がなく不明であるが、移住当初においては当然、故郷で使われていた言葉が用いられていたはずである。しかし、他府県からの移住者が増加するに従い、しだいに他府県出身者との交流が増え、人口面で多数派を占める地域の言葉に収斂または融合されていった。『村の創業』でも、年を経るにつれ会話の中に名古屋弁が含まれる頻度が低くなってきている。
また、『村の創業』にはアイヌの人びとが話していた言葉も出ているが、こちらは東北弁に近い言葉であり、士族移民が到着する以前から八雲に居住していた人々が使用していた言葉は東北弁に近い言葉が主流であった。
八雲の木彫り熊
八雲はかつて北海道みやげとして人気のあった木彫り熊発祥の地でもある。それを奨励したのは徳川義親であり、貧しい農民の生活を改善するための手段でもあった。
義親は1921〜1922年にかけてヨーロッパを旅行し、フランス・ドイツ・スイスなどの農民生活を視察した際に、スイスで熊をモデルにした木彫りの民芸品が売られているのをみて、八雲でも木彫り熊を農民の農閑期の副業(39)に奨励してその生活向上に役立たせようと考え、見本として木彫り熊をはじめ盆・フォーク・ペーパーナイフなどの民芸品を購入した。そして1923年に八雲を訪問した際、これらの見本を農民に見せて、出来あがった製品はすべて義親が買い取ることとして製作を試みるよう奨励した。
こうして1924年3月に徳川農場では、奨励している副業的な工芸品の製作普及と技術の向上を図るため、第1回農村美術工芸品評会を開催した。この品評会にはさまざまな工芸品が出品され、大新の伊藤政雄がスイスの木彫り熊をモデルに製作した作品もあり、これが北海道における木彫り熊第1号となった。これを見た義親は、伊藤政雄と東京在住の十倉兼行を講師に、徳川農場内で講習会を行ない、農場庭園内で熊を飼育して姿態観察を行なわせるなど、木彫り熊の製作を積極的に奨励した。さらに1928年には「八雲農民美術研究会」が結成され、技術の一層の向上が図られ、熊彫りは副業として定着した。その後、各地で行なわれた展覧会などに入選するようになると、八雲の熊彫りの評価も次第に高くなり、製作量も増加して1931年には3981個、1932年には5347個が生産され、熊彫りを専業とする者も現われてきた(40)。
このように八雲の熊彫りが名声を博するようになるにつれて、道内各地で八雲を真似て熊彫りを製作するようになり、熊の木彫りは一躍北海道を代表するみやげ物となった(41)。しかし、第二次世界大戦が激しくなってくると、こうした美術工芸品は贅沢品とされて熊彫りの需要も減ったので、ほとんどの製作者が生業として維持していくことは困難となり転業していった。それとともに八雲農民美術研究会も自然消滅した。
5-4 宗教をめぐる状況
八雲神社について
1878年5月に、最初の移住に当たって士族移民一同が連署結約した郷約には、「熱田神宮ノ分社ヲ建築シ、敬公ノ神霊ヲ合祀シ敬神報本ノ道ヲ守ルヘシ」とあり、翌1879年に熱田神宮の神符と徳川家歴代の神霊を板蔵の2階に祭り(42)、のちに八雲小学校の一部に移し、産土神として崇拝していた。
1884年には社殿を新築し、1885年に「八雲神社」の創立出願をして許可され、同年12月村社に列せられた。翌1887年には氏子総代の片桐助作と佐治為泰が熱田神宮に出願し分霊を仰ぎ、許可された。この分霊奉遷にあたっては徳川慶勝が明治天皇に直接奉請して勅許を得たものと伝えられている。以下は、1885年に熱田神宮に対して出された「御分霊願」である。
御分霊願(全文)
御分霊願
北海道胆振国山越郡八雲村鎮座産土八雲神社ノ義熟田大神ヲ奉祭候処昨明治十九年十二月村社二被列候二付私共儀氏子総代トシテ御本宮へ参拝仕、皇大神之神御分霊ヲ奉遷シ永ク奉仕致度氏子中挙リテ奉懇願候条右請願御聞届被成下弥敬神ノ志操御引立被成下度此段奉願侯也
胆振国山越郡八雲村氏子総代
片桐助作
同
佐治為泰
明治二十年三月一日
熱田神宮宮司 角田忠行殿
(八雲史料549、「八雲神社由緒」より)
熱田神宮の分霊を祭る神社は、全国でも八雲神社のみで、社章も熱田神宮と同じである。熱田神宮の祭神は熱田大神・天照大神・日本武尊・素戔鳴尊・宮簀媛命・建稲種命であり、三種の神器の一つである草薙剣も祭られている。ただし、三種の神器を祭る神社は本来分霊ができず、慶勝の頼みにより分霊はしたものの、長い間熱田神宮は1944年5月11日に下記の証明書を出すまで八雲神社を分社として認めてこなかったという(43)。
証明書
明治二十年三月一日付北海道胆振国山越郡八雲村氏子総代片桐助作及佐治為泰ヨリ当神宮宮司角田忠行ニ宛テ、同村鎮座産土八雲神社ニ奉斎スヘキ熱田皇大神ノ御分霊奉戴ニ関シ出願ノ書類ハ別紙写同文ノモノ当時当神宮ニ於テ受理セルコト実証ニ有之従ッテ御分霊ノ儀モ允可セシコト被推定候条此段証明候也
昭和十九年五月十一日
熱田神宮宮庁
(『改訂 八雲町史』より引用)
八雲神社では、これらの祭神のほか、1934年5月4日には八雲町開拓の始祖と仰ぐ徳川慶勝命を合祀しており、神社には慶勝の書簡および額、義礼の額などが保管されている。
また、八雲神社の宮司は代々和合会員であり、例大祭は毎年6月20日から3日間行なわれている。これはかつての熱田神宮例大祭と同日である。1897年ごろまで八雲神社例大祭は「源敬公御祭典」とも呼ばれ、祭りの際は熱田祭の古法によって、大きな的の真ん中に神社の千木の切れ端を結びつけて、それを弓で射る古式があった(44)。また、現在では行なわれていない山車の巡行もかつては行なわれていたようであり、祭りの際は花火の打ち上げも行なわれて大いににぎわったようである(45)。

八雲神社(字は徳川義親筆によるもの)
そのほかの宗教の状況
名古屋は浄土真宗門徒の多い地域であり、士族移民たちも名古屋在住時代は真宗の門徒が多かった。しかし、移住後は当初浄土真宗の寺院が存在しなかったことから、移住者全員が神道に鞍替えするようになった。ただし、前述の「定約書」には「謝恩講」という言葉が見られることから、神道でありながら、浄土真宗の宗教行事も各自で行なっていたようである。
八雲に浄土真宗の寺院ができるのは、1892年に八雲仮説教所ができてからのことである。その後1899年に、徳川義礼より土地の下付を受け、真宗大谷派の八雲山安楽寺が開山した。その後は、かつて真宗門徒であった士族は安楽寺の檀家となった者や、神道のまま残った者もいた。また、青年舎出身者を中心に、キリスト教に改宗する者もいた。これは、青年舎出身者の多くが、当時クラーク博士などの影響でキリスト教が盛んであった札幌農学校で学び、洗礼を受けて帰ってきたためであった。
士族移民以外でも、小作人移民は真宗門徒の多い愛知や北陸出身者が多数を占めたため、八雲では浄土真宗の門徒が多くなっている(46)。一方、東北出身者は曹洞宗を信仰するものが多く、愛知出身者で曹洞宗寺院の檀家の者や、東北出身者で真宗の檀家の者はきわめて少ない。
このほか、特筆すべき寺院としては、野田生地区に徳川山建長寺というものがあり、これは浄土宗の寺院であるが、尾張徳川家の宗派と同じことから、名古屋にある浄土宗建中寺と徳川家にちなんでこの名前となった。開基の経緯に関しては不明であるが、徳川家当主からも時折寄進があったようである。なお、建長寺の檀家で愛知出身者はそれほど多くない(47)。八雲には、このほか日蓮宗の寺院もあり、ほとんどすべての宗派の寺院がそろっている(48)。
5-5 今日の八雲における生活文化
食文化とことばの変化
筆者は2002年夏以来、八雲町での聞き取り調査を行なっているが、2002年に最初に八雲町を訪
(表13) 現在の八雲町立岩地区の住民構成
初代の出身県 | 移住時期等 | 初代の出身県 | 移住時期等 | ||
1 | 福井県南条郡 | 1897年 | 31 | 青森県中津軽郡 | 1980年 |
2 | 不明(道内?) | 1929年町内から移転 | 32 | 青森県 | 1983年 |
3 | 愛知県中島郡 | 51の分家 | 33 | 名古屋市 | 1878年 |
4 | 愛知県丹羽郡 | 1890年 | 34 | 名古屋市 | 33の分家 |
5 | 愛知県春日井郡 | 1893年 | 35 | 愛知県中島郡 | 1890年 |
6 | 愛知県春日井郡 | 5の分家 | 36 | 不明(道内?) | 1962年余市から移転 |
7 | 愛知県中島郡 | 1912年 | 37 | 不明(道内?) | 1897年大野から移転 |
8 | 愛知県中島郡 | 1889年 | 38 | 山形県 | 1914年枝幸から移転 |
9 | 山形県 | 1938年北見から移転 | 39 | 愛知県東春日井郡 | 1894年 |
10 | 愛知県丹羽郡 | 44の分家 | 40 | 愛知県西春日井郡 | 1894年 |
11 | 新潟県古志郡 | 1916年 | 41 | 愛知県西春日井郡 | 1894年 |
12 | 愛知県中島郡 | 35の分家 | 42 | 愛知県西春日井郡 | 41の分家 |
13 | 愛知県中島郡 | 1903年 | 43 | 静岡県小笠郡 | 1912年 |
14 | 名古屋市 | 1886年 | 44 | 愛知県丹羽郡 | 1897年 |
15 | 愛知県東春日井郡 | 1892年 | 45 | 愛知県東春日井郡 | 1892年 |
16 | 愛知県西春日井郡 | 1892年 | 46 | 愛知県東春日井郡 | 1895年 |
17 | 名古屋市 | 1886年 | 47 | 山梨県北巨摩郡 | 1919年 |
18 | 愛知県中島郡 | 51の分家 | 48 | 宮城県栗原郡 | 1905年 |
19 | 愛知県東春日井郡 | 長万部から移転 | 49 | 愛知県 | 1895年 |
20 | 愛知県西春日井郡 | 1897年 | 50 | 宮城県栗原郡 | 1905年 |
21 | 宮城県仙台市 | 不明 | 51 | 愛知県中島郡 | 1898年 |
22 | 徳島県阿南市 | 1911年 | 52 | 福島県 | 1989年 |
23 | 愛知県中島郡 | 24の分家 | 53 | 青森県 | 1931年 |
24 | 愛知県中島郡 | 1878年 | 54 | 愛知県愛知郡 | 1896年 |
25 | 愛知県中島郡 | 24の分家 | 55 | 宮城県栗原郡 | 1908年 |
26 | 新潟県中魚沼郡 | 1914年 | 56 | 不明(道内?) | 1968年 |
27 | 名古屋市 | 1878年 | 57 | 不明(道内?) | 不明 |
28 | 名古屋市 | 1879年 | 58 | 江差町 | 1913年 |
29 | 愛知県西春日井郡 | 41の分家 | 59 | 名古屋市 | 1881年 |
30 | 不明(道内?) | 1989年町内から移転 |
※太字は士族出身者。囲み数字は愛知県出身者。『鵬鷲』より作成。士族出身者の割合が少ないのは、就職や進学などで八雲を離れる割合が小作移民出身者より多いためである。また、近年の酪農の不振も離農に拍車をかけている。
れた際は、調査を進める上での仮説として、愛知県出身者が中心となって開拓が進められた土地であるので、尾張の文化が色濃く残っているのではないか、ということが前提条件としてあった。しかしながら、調査の結果は、仮説を大きく裏切るものであった。
まず、食文化に関していえば、日常の食生活の中で愛知から引き継いだと思われるものはほとんど存在しない。筆者は2002年夏に、かつて鷲巣耕舎や青年舎が置かれ、現在は牧場や畑が点在する八雲町立岩地区(旧称鷲の巣)のいくつかの農家を回り、食生活について聞いてみた。立岩地区は2001年現在で約60戸の農家があり、このうち割にあたる37戸は先祖が愛知県出身であり、東北・北陸出身者の比率は低い(表13)。したがって、この地区では愛知の食文化が現在でも色濃く残っているのではないかと考えていたが、実際には道内の他地域とほとんど変わらない食生活であり、愛知県以外の出身である家庭のそれと大差はなかった。立岩地区以外でもこの傾向は変わらず、全般的に八雲町内では町内どこの地域でも北海道の他地域と同じような濃い味付けであり、調理方法も均一化されているといえる。
これに対し、全道的な傾向として、ハレの日の食事には出身地域の特徴が残されることが多い。民俗学の世界では各家庭の出身地方の差異を如実に表す食べ物として雑煮がよく例に出されるが、とくに北海道はさまざまな土地からの移住者の子孫によって形成されたため、雑煮にも各家庭によってさまざまなバリエーションがあり、たとえば道内では比較的多い四国出身者の子孫の家庭では、餡の入った丸餅入りの雑煮が見られることもある。
名古屋式の雑煮は、「菜雑煮」と呼ばれ、醤油味にモチナ(小松菜)または白菜と角餅のみが入り、上に削り節を載せるだけの、きわめて質素なものであるが、何軒かで雑煮について話を聴いてみたところ、名古屋式の雑煮を作っている家庭は立岩地区では2戸(I家・Ts家)のみ存在した。また、話を聞いたところ、かつては名古屋式の雑煮
を作っていたという家もあった。現在も名古屋式の雑煮を食べている2戸とも士族出身であり、このうちTs家は名古屋式の雑煮ではなくなっていたが、Ts氏がI氏からその話を聞いて、最近名古屋式の雑煮に戻してみたということである。したがって、移住当初から現在に至るまで変わらずに名古屋式の雑煮を継承したのは立岩地区ではI家ただ1戸のみということになる。また、このI家ではゴリと呼ばれる小魚の佃煮も食べられていた。
このほかの家庭では、出身地域にかかわらず豚肉や鶏肉を用いた雑煮が一般的となっている。北海道における雑煮の形態の普遍的な傾向として、丸餅から角餅に、味噌味・小豆味から醤油味への変化が見られ(49)、現在の北海道では、醤油味・角餅に肉類の入る雑煮が多くなっているが、この傾向は八雲でも同じだということである。なお、立岩地区では雑煮が丸餅である西日本地域の出身者は1戸のみであり、このほかの農家では雑煮が角餅の地域である愛知県および東北地域の出身者が中心となっているため、現在では丸餅の雑煮を作っている家庭は存在しない。
移住者のことばは食生活以上に変化している。前述の士族が用いた武家言葉については、士族移民1世代目の間では話されており、名古屋出身の両親の下で育った2世代目の間でも話されていたという。ところが、3世代目になると名古屋弁はほとんど話さなくなり、2世代目が亡くなった1970年前後にはまったく聞かれなくなった(50)。
愛知出身の小作人移民が話していたであろう名古屋弁も、現在ではまったく残っていない。先祖が愛知からの小作移民出身で、現在立岩地区で酪農を営むK氏(1920年生まれ)によると、彼が子どもの頃(1930年頃)にはもはや名古屋弁はほとんど話されておらず、かえって武家言葉のほうがよく残っていたということである。K氏自身は士族の家系ではないので、士族の会である「和合会」には入会していないが、K氏の妹が前出のTs家に嫁いでおり、またK氏も北海道帝国大学に入学し、八雲酪農の指導者的な存在であり士族出身の酪農家とは親交が深かったことから、士族とはつながりが深く、士族のことばを耳にする機会はよくあり、現在でも「やっとかめ」など名古屋弁の語彙を古い仲間内で断片的に使用することはあるとのことである。
現在の八雲町では、出身地域にかかわらず、北海道弁のなかでも訛りの少ない、札幌周辺で話されているのとあまり変わらない言葉が主流となっている。むしろ特徴的なのは、漁業従事者とそれ以外の町民とのことばの差である。すなわち、漁業従事者においては東北弁に近い、いわゆる「浜ことば」が話されており、それ以外の町民とくに農業従事者の話す北海道弁とは明確に差異がある。八雲の農業従事者で浜ことばを話す人はほとんどいない(51)。
浜ことばは、八雲町落部より南の地域では主流のことばとなっており、函館をのぞけば道南地区で広く話されていることばである。八雲町内でも、噴火湾沿いの地域と落部地区では主流となっている。落部は1956年に八雲町に合併された地域であり、旧名が茅部郡落部村となっているとおり、渡島国に属する地域であり、函館志向が強く本来八雲の経済圏ではない。また、浜ことばを話す人々は漁業従事者に多く、気質の面でも農業従事者とは相容れない部分が多い。
このことは、落部村を合併してから50年を経た現在でも、浜ことばを話す旧落部村民と北海道弁を話す旧八雲町の多くの人々との間に、「八雲と落部は違う」というような意識を生じさせている。また、旧落部村地域を除く八雲町でも、浜ことばを話す人々が住む地域と、北海道弁を話す人々が住む地域は国道5号線で明確に分断されており、農閑期に農業従事者がアルバイトで漁村に出向き、帆立貝の殻剥きをしたり、時化の際に漁業従事者が農家の手伝いに来たりすることがある程度で、両者間の交流はそれほどない(52)。
また、アイヌの人びとの話すことばについては、明治初期にはアイヌ語以外にも浜ことばが話されていたことは前述のとおりである。現在、アイヌの人びとは漁業従事者がほとんどであり、農業従事者との交流は他の漁業従事者と同じくそれほど多くはない。
宗教行事の変化
八雲神社の例大祭は現在に至るまで6月20〜22日であるが、行なわれる祭りの内容は創建当初とは大きく変化している。かつては熱田祭の古法にのっとって射的の神事が行なわれ、柔術・剣術・獅子舞等の奉納が行なわれたり、余興として競馬や蹴鞠等が行なわれたりしたが、現在ではこれらの行事はなく、わずかに相撲大会が行なわれる程度である。また、史料ではかつては山車の巡行が行なわれたものの、明治後期以降は神輿の巡行に変わったようである(53)。
現在でも神輿の巡行は行なわれており、獅子舞や神楽も踊られているが、実際にはすでに熱田祭の伝統は受け継がれておらず、神楽も道南一帯で踊られる「松前神楽」となっている。これは、前述のとおり、熱田神宮が長い間八雲神社を分社と認めてこなかったため、熱田神宮と八雲神社との間に人的交流が何もなかったということもあるが、戦時中の1943年に、町内に飛行場を建設する際に八雲神社が移転させられ、その際に神社所有の史料のほとんどが失われてしまったためである。また、戦時中は贅沢が戒められ、神社の例大祭であっても簡略化が要求された時代でもあった。戦後になると、資金難もあって熱田神宮から宮司を呼ぶ資金はなく、例大祭の際には近隣の神社の宮司が集まって回り持ちで祭りを行なうため、どうしても祭りの内容が各神社とも均一化せざるを得ない状況となっている(54)。
ところで、八雲では八雲神社例大祭にあわせて「八雲山車行列」が行なわれているが、これは八雲神社とは無関係である。これは、町内の青年団体・サークル「若人の集い」が町を活性化させるために1982年に始めたもので、1988年には「八雲山車行列実行委員会」が発足し、現在では「YOSAKOIソーラン祭り」の関係者が参加することもあり、八雲町を代表する祭りに成長している。
また、宗教行事ではないが、結婚式は現在道内のほとんどの地域で会費制のものが主流となっており、八雲町も例外ではない。
郷里との交流
士族移民たちは移住当初の時期は、八雲を「墳墓の地」と覚悟して移住したといっても、郷里である名古屋には親類などがおり、名古屋との関係もしばらくは続けられたようである。たとえば、第1回移住者の吉田知行は1883年に徳川家の家令に任命されしばらく八雲を離れたが、家令を辞任した後は郷里である愛知郡岩作村(現在の愛知郡長久手町岩作)に戻り、1906年5月に岩作村など3村が合併して長久手村が発足した際に、その初代村長に就任しているが、のち八雲に戻りそこで死去している。また、角田弟彦も八雲移住後も東京の徳川家に挨拶に寄ったついでに名古屋を訪問し、知己と再会をしている(55)。
ところが、年が進むにつれ故郷を知る1世代目が亡くなり、八雲生まれの2世代目が中心となると、遠隔地のため交通費がかかること、道内の傾向として東京志向が強いことなどから、しだいに故郷との関係は疎遠になっていった。
しかし、北海道100年を迎えた1960年代後半以降、全道的な傾向として北海道開拓の歴史を見つめなおす動きが盛んになり、八雲町でも開基100年を迎えた1978年には盛大な記念式典が行なわれ、郷土資料館が開館している。こうした中、1982年に、当時の尾張徳川家第20代当主徳川義知は小牧山公開55周年記念事業の際に、小牧市長に八雲町と相互交流するよう提言した(56)。これを契機に小牧市関係者が八雲を訪問し、八雲町側も相互交流を快諾した。小牧市は旧東春日井郡にあり、愛知県では最も多くの北海道移民を送出した地域であった(57)。こうして小牧市と八雲町の相互交流が開始され、現在では小牧と八雲は友好都市となっており、毎年夏冬に行なわれる児童の交流学習・経済面での交流・八雲山車行列への小牧市の参加・議会の交流などが今日に至るまで継続されている。
児童の相互交流も現在は20回を超え、毎年夏には小牧市の児童が八雲を訪問し、冬には八雲町の児童が小牧を訪問している。小牧市児童の八雲訪問は6日間の日程で、歓迎会・町内見学・町内渓流でのヤマベ釣り・郷土資料館見学・木彫り熊実演見学・大新墓地での吉田知行の墓前への献花などが行ない、八雲町児童の各家庭にホームステイして交流が行なわれている。八雲町児童の小牧訪問も6日間の日程で、歓迎会・美術館見学・竹細工の体験学習・名古屋市内見学が行なわれ、同じく小牧市児童の各家庭にホームステイしている。
また、小牧市では「交流市民の会」が組織され、毎年6月の八雲山車行列や11月の大漁秋味まつりにも交流団が訪問し、八雲側からも小牧市民まつりへの物産提供や山車の参加が行なわれ、小牧・八雲の交流はすっかり定着した感が強い。
これに対し、名古屋市は尾張藩の本拠であり、八雲と名古屋との関係は開拓以来の歴史をもっているが、人口規模があまりに違うために行政レベルでの交流は小牧市に比べるとそれほど活発ではなく、児童の相互訪問なども行なわれていない。それでも1994年以来八雲町関係者が名古屋市内で毎年11月に八雲物産フェアを開いている。物産フェアは徳川美術館にもほど近い大曽根商店街で行なわれており、筆者は2004年と2006年に八雲物産フェアに出かけたが、残念ながらあまり賑わっているとはいえない状況であった。
名古屋と八雲の交流でユニークなのは、1982年以来毎年8月に名古屋大学・愛知医科大学・藤田保健衛生大学の医師が八雲で実施する無料の「町民ドック」である。この町民ドックは当初、名古屋大学の医師が尾張藩士の移住から100年を経て、名古屋の人と移民の子孫との健康状態を比較するのが目的であった(58)。しかし、移住後100年を経て愛知出身者もほとんどが他府県出身者と混血していることからその目的は達成できず、現在では40歳以上の町民なら誰でも健康診断が受けられるようになっている。
また、最近になって八雲高校の修学旅行先に名古屋の徳川美術館が加えられ、2003年8月1日の開町125周年記念式典や2005年10月1日の八雲町・熊石町合併記念式典では、小牧・名古屋の両市長・両市議会議長など愛知県関係者から多数の祝辞が寄せられている。
しかし、残念ながら名古屋市民の八雲の知名度は低く、旧尾張藩士の開拓の歴史に関してはまったくといっていいほど知られていないばかりか、名古屋市発行の公文書などでも2000年発行の『新修名古屋市史』には若干触れられているものの、それ以前発行の『名古屋市史』などでは一行も触れられておらず、名古屋市博物館の展示や幕末尾張藩に関する企画展でも八雲のことは無視されている。しかし、八雲町の本音としては、小牧市よりもむしろ八雲のルーツである名古屋市ともっと交流したい(59)とのことで、小牧市と八雲町があくまでも友好都市であって、姉妹都市提携は結んでいないのもそれが理由である。
尾張徳川家と八雲のその後
尾張徳川家と八雲との関係はその後、どのように変化したのであろうか。第二次世界大戦終了後日本で行なわれた各種の改革は、八雲町と徳川家との関係にも大きな影響を及ぼした。すなわち、農地改革によって寄生地主制が否定されたことにより、徳川農場も小作制の農場として維持していくことは不可能となり、1948年10月15日に徳川家開墾試験場以来70年の歴史に幕を閉じている。また、華族制度の解体に伴い、先祖伝来の財宝などに莫大な財産税が課税されたことから、旧華族の没落が進み、これは尾張徳川家とて例外ではなかった(60)。
しかし、徳川家と八雲との関係がこれで終わったわけではない。前述の通り、徳川農場では1933年以降、山林事業に経営の主体を移しており、小作人は漸次解放しつつあった。このため、農地解放後も山林の多くが残り、これらは売り払われることなく徳川家当主を社長とする「八雲産業株式会社」の土地となった。これが可能だったのは、徳川義親が1931年に財団法人「徳川黎明会」を設立し、先祖伝来の品々をまとまって展示する「徳川美術館」を1935年に名古屋に開館しており、財産税課税を免れたためである。したがって、尾張徳川家では他の華族と異なり、華族制度解体の影響を最小限にとどめることができたのであった。
八雲産業株式会社は、尾張徳川家の資金管理を目的とした会社であり、本社は尾張徳川家がある東京都豊島区目白で、かつての敷地を分割して高級賃貸住宅や女子学生寮の経営を行なっている。また、旧徳川農場は「八雲事業所」となり、植林・造林事業を行っている。
徳川義親は戦後もたびたび八雲産業の社長として八雲を訪問している。しかし、戦後は以前のように八雲に経済的な援助を行なう余裕はなくなり、また小作人がすべて自作農として独立したことから、八雲産業関係者を除くと、徳川家と直接のかかわりを持つ者はいなくなった。この頃になると、移民の2世代目も高齢となり、3世代目が中心となってきた。しかし、義親が戦前に八雲に多大な貢献をしたことは忘れられず、戦後も広く町民に尊敬されていた。このため、1966年には旧小作移民も含む町民が「徳川さんを顕彰する会」を設立して、町民からの寄付で得た200万円で胸像を建立し、義親の80歳の誕生日である同年10月5日に義親を招いて除幕式を行なっている。義親は1976年9月に89歳で死去したが、八雲町では義親生誕90年に当たる同年10月5日に追悼式を挙行し、多くの参加者を集めた。

徳川義親胸像
義親の子で第20代当主義知はそれほど八雲を訪問してはいないが、八雲町と小牧市の交流を推進した。義知の養子である第21代義宣は1958年以来頻繁に八雲を訪問し、訪問の際には徳川美術館館長としての講演が主催されたが、2005年11月に71歳で死去した。現在の当主は義宣の子である第22代義崇であり、八雲産業株式会社社長として頻繁に八雲を訪問している。
現在では、義親存命中の八雲を知る世代も高齢になりつつあり、八雲に対する経済的な援助もないことから、徳川家に対する尊敬の念は薄れつつあるのが実情である。しかし、1970年代以後の郷土史ブームも手伝って、1980年代以後はその歴史をなかだちにした愛知県との新たな交流が行なわれるようになってきた。
このほか、八雲町長が就任した際には徳川家への報告が現在でも伝統的に行なわれている。また、公務などで八雲町関係者が東京を訪問した際も、東京の徳川家を訪問して挨拶することが慣例となっている。2005年11月の義宣死去の際には、八雲町長はじめ八雲関係者も多数葬儀に参列している。
和合会の現在
一方、士族移民の子孫と徳川家との関係は現在も続いている。1914年に結成された「徳川家移住人和合会」は現在でも活動しており、年始の御機嫌伺は、徳川農場が八雲産業と名を変えた現在でも続いている。
また、和合会では徳川家慶弔への挨拶を欠かさず行なっている。最近では1998年12月末に亡くなった徳川正子(義知夫人)の葬儀と1999年4月に行なわれた義知7回忌と正子百ヵ日の供養への参列、2000年1月の義崇氏の結婚式へのお祝いの品の贈呈、2005年11月の義宣の葬儀への参列などが行なわれている。また、八雲開墾碑・義親胸像などの建立、義親正四位・正三位昇進や開村80年などの際の記念植樹も行なっているほか、毎年暮れに徳川家へ豆と鮭を献上している。これは、1878年の「郷約」や1889年の「徳川家開墾地郷約」でも定められていたことであり、士族たちは「献上豆」「献上鮭」といった。この物品献納は戦後も「贈呈豆」「贈呈鮭」と名称を変えて現在でも行なわれている(61)。
しかし、和合会も結成から70年以上が経過すると会の活動も沈滞気味となっていた。そこで1986年に、1915年以来ほとんど無修正だった会則を現代に即応させるよう改正し、それにあわせて士族移民の直系の子孫のみならず、分家の子孫や母方が士族という人も入会できることにした。これによって和合会員はそれまでの40人から72人に増加し、会報『八重垣』を刊行して会員の消息や八雲・徳川家の近況について伝えることにした(62)。
和合会では、親睦会が毎年行なわれ、昔を懐かしむ場所となっている。この会への参加は和合会員のみに限られているが、徳川家関係者や町長などが参加することもある。筆者は2003年夏に特別に親睦会への参加が許されたので、その時の模様を書いてみる。
2003年の親睦会は徳川義宣氏の八雲訪問に合わせ7月28日(月)に行なわれ、出席者は和合会員のほか八雲産業社員・徳川林政史研究所関係者・山内八雲町長(当時)で、総勢20人余りでアルコールも入り賑わっていた。会長の挨拶、出席者の自己紹介などが行なわれ、義宣氏も挨拶のなかで、「八雲はふるさとと感じている。また各藩の北海道開拓は各所で行なわれたが、八雲のように和合会という組織を結成して開拓から125年経ても来町のたび歓迎してくれ、暮れには鮭や豆を送ってくれるところは他にない素晴らしいことで、どこに行っても自慢できること」と大変喜んでいる様子であった。
会員のなかには「私と徳川さんの付き合いは関ヶ原の合戦に加勢したときからで…」という人もいたが、なかには自分の家のルーツについてあまり詳しく知らない人もおり、会員の中でも士族の歴史に対する関心には温度差があるように感じられた。しかし、そのような人でも今でも徳川家に対して開拓のルーツとして一定の敬意や親しみを感じている人がほとんどであった。
和合会員の徳川家への思いも人それぞれであり、「父親が会員だったので自動的に会員になっただけで、今の徳川家にはあまり関心がない」という人もいるが、会員の中ではそういう意見は少数派であり、「やはり八雲の始祖徳川慶勝の子孫であり、大事にしたい」というように親しみを感じている人が多く見られた。
前者の見方は、もはや徳川家は経済的に八雲に援助はできず直接生活に関与しないのであるから当然出てくる見方である。しかし、生活上何のメリットもない徳川家に今なお親しみや尊敬の念を持っているのは何故だろうか。
この理由としては、江戸時代まで徳川家は絶大な権威を保っており、明治維新後も形式的には四民平等となったものの、封建的主従関係が残り、とくに徳川家開墾試験場が当初士族のみによって構成されていたため封建的主従関係がそのまま持ち込まれたことが、八雲に江戸時代と変わらない主従関係が長く残った要因であり、その影響が現在も残存していることとが挙げられよう。また、伊達士族と異なり主君は入植せず、長年にわたり八雲の主君的存在として資金援助を行ない、それが八雲の発展に大きな役割を果たしていたことも挙げられるのではないだろうか。
<註>
(1) 八雲史料163、「徳川家開墾試験場條例」、第27款。
(2) 林1955、98頁。
(3) 八雲史料452、「八雲村徳川家開墾地沿革」(以下、「沿革」と略す)。
(4) 同、「沿革」。
(5) 当時、野田追川を挟んで北側は野田生、南側は野田追という地名になっていた。のちの地名変更により野田追の地名は現存しないが、川の名前は野田追川のままである。
(6) 同、「沿革」。
(7) 林1955、98-99頁。
(8) 林前掲論文、100-101頁。
(9) 武田1956、71-73頁。
(10)『八雲町史 上巻』、444-445頁。
(11)林1956、100-101頁。
(12)『町史 上巻』、406-407頁。
(13)「出面」とは「日雇い労働者」を表す北海道方言であり、英語の”day men”が語源といわれている。
(14)大島1952。
(15)『町史 上巻』、407-409頁。
(16)同、419-421頁。
(17)同、430頁。
(18)八雲史料408〜、角田弟彦「胆振日記」などの記述による。
(19)都築1916どの記述による。
(20)都築1916、46-49頁。
(21)片桐・安藤1993、76-81頁。
(22)田川1957、14-17頁。歌会以外にも茶の湯の会も何度か開かれていたようである。
(23)八雲史料304〜「日誌(八雲日記)」・「胆振日記」をはじめ、「杉立正義日誌集(431)」などに八雲神社祭典の際の記述が見られる。
(24)頼母子は無尽とも呼ばれ、掛け金が払えない場合わずかながら利息がかかり、それでも払えない場合、以前に払い込んだ掛け金は没収となる場合が多かった。このため、地域共同体内部での富裕層と貧困層の序列が確たるものとなり、封建社会を支える要因のひとつともなっていた。このシステムは現在でも農村・漁村部を中心に広く行なわれている。泉・蒲生1952では、道内の農村でも「ゆひ慣行」があることを明らかにしている。
(25)前出「日誌(八雲日記)」・「胆振日記」の記述による。
(26)八雲史料163、「遊楽部実況概略」。
(27)徳川家開墾地では当初、平民への土地の分与を認めていなかったため、自作農を希望する者は八雲以外に移動する場合が多かった(中村1998、58-59頁)。石狩郡生振村はこうした人々によって開拓された町であり、やはり東春日井郡出身者が多かった。なお、八雲では東春日井郡出身者以外にも丹羽郡・中島郡出身者も多い。
(28)林1963、101頁。
(29)八雲町の場合、南部地区は江戸時代の1800年から和人地であり、すでに和人の定住が見られた。この地に住んでいた和人は東北とほぼ共通した文化的背景を持った人々であった。
(30)前出「日誌」の記述による。大正期以降は義親夫妻の写真に変わっており、大正天皇が没した翌年の1927年をのぞきほぼ毎年行なわれている。
(31)『八雲町史 下巻』、583-587頁。
(32)同、590-595頁。
(33)聞き取り調査による。
(34)前出「日誌」1887年9月24日の記述によると、接待用として黍オコシや澱粉ウイロを提供したとの記述がある。
(35)『町史 下巻』、596頁。
(36)聞き取り調査による。
(37)いずれも前出「日誌」の記述による。
(38)片桐・安藤前掲書、82頁。
(39)農閑期の副業として熊彫りが奨励されたのはこれが最初であるが、木彫り自体は「アイヌ彫り」として移住当初から行なわれていた。ただし、これは商業目的ではなく、盆や器など生活目的のものであった(大島『徳川農場沿革史』の記述による)。
(40)『町史 下巻』、437-439頁。製作された熊彫りは徳川家が買い上げ、八雲来場者へのお土産品としても使われていた(前出「日誌」の記述による)。
(41)熊彫りは現在アイヌの人びとの工芸品と思われているが、これは八雲の熊彫りに刺激されて旭川近文コタンでも熊彫り製作を開始し、やがて道内各地に広まっていったものである。
(42)ただし、「日誌」などの記述によれば、徳川家当主に関する祭典は当初から義直・義宜に限られ(のち慶勝も)、それ以外の当主に関する祭典が行なわれた記録はない。
(43)八雲神社での聞き取り調査による。
(44)都築1914、181-182頁。
(45)前出「日誌」・「胆振日記」等の記述による。
(46)浄土真宗門徒が多いのは北海道全域に共通する傾向である。これは、初期移民の多くが真宗門徒の多い北陸出身だったからであり、北陸地方が明治初期には全国有数の人口を誇っていたのも、単に農業が盛んであっただけなく真宗門徒が多かったため農村部での間引きが少なかったことも理由のひとつとして挙げられよう。
(47)聞き取り調査による。
(48)現在、八雲町では八雲駅周辺の旧国道5号線から少し海側に入った地区に寺町が形成されており、臨済宗を除くすべての宗派の寺院があるが、浄土真宗の寺院が最も多く、三派すべてが揃っている。南部には江戸時代創建の寺院も存在するが、士族移民でその檀家になった者はいない。
(49)宮良高弘氏による。
(50)聞き取り調査による。
(51)同。
(52)K氏による。
(53)前出「日誌」の記述による。
(54)聞き取り調査による。
(55)前出「日誌」・「胆振日記」の記述による。
(56)『中日新聞』、1982年9月17日付。
(57)小牧市との交流を徳川義知が提言したのは、小牧山がかつて尾張徳川家の所有(1927年義親が小牧市に寄付)であり、小牧山公開55周年記念事業の一環としてであった。ただし、八雲町への小作移民は旧東春日井郡といっても現在の春日井市出身者が多く、小牧市出身者の比率はそれほど多くない。むしろ小牧市出身者が多いのは旧石狩郡生振村(現石狩市)である。
(58)『北海道新聞』、1995年11月5日付。
(59)聞き取り調査による。
(60)尾張徳川家では1947年3月に課税価格1698万9000円・税額1390万6000円の申告をした。この申告は1951年2月28日に更正され、課税価格1800万3000円・税額1481万8000円となり、莫大な財産の大半を失っている(小田部1988、209頁)。
(61)横井1984、70-73頁。
(62)『八重垣』、創刊号。
| このページは、2019年3月に保存されたアーカイブです。最新の内容ではない場合がありますのでご注意ください |