犯罪被害者と新世紀の刑事法制
〜刑事「行政」から刑事「司法」への転換を〜
中島 健
■第1章 はじめに
近年、犯罪事件における「被害者の権利」の確立が課題となっている。1997年、旧山一証券の顧問弁護士をしていた岡村 勲弁護士宅に暴漢が侵入し、同弁護士の妻が殺害された事件では、裁判所によって被害者である岡村弁護士が妻の遺影を法廷に持ち込むことが許可されず、これが大きく報道された。1998年4月の山口県光市母子殺害事件では、被害者の夫である本村 洋氏が犯人である19歳の少年に対して強く死刑を望んだにも関わらず、一審判決が無期懲役となり、量刑判断における被害者感情が議論された。また、その他多くの少年事件、刑事事件において、数え切れないほどの被害者やその遺族が捜査や裁判から排除され、裁判期日や判決内容すら知らされない、更には少年事件においては事実関係や加害者の氏名・住所すら分からない、といった環境に置かれている。
こうした流れを受けて、政府も法務省、警察庁を中心に被害者対策問題に取組みはじめ、2000年には
犯罪被害者保護法
(平成12年法律第75号「犯罪被害者等の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律」)、刑訴法等改正法(平成12年法律第74号「刑事訴訟法及び検察審査会法の一部を改正する法律」)、少年法改正法(平成12年法律第142号「少年法の一部を改正する法律」)、そして2001年には
犯罪被害者給付金支給法
改正法(平成13年法律第30号「犯罪被害者等給付金支給法の一部を改正する法律」)が成立。また、報道における被害者問題の扱いも相対的に大きくなり、各地でボランティアによる被害者支援団体が新設されるようになってきた(1998年「全国被害者支援ネットワーク」設立)。夫婦間の暴力(ドメスティック・バイオレンス、DV)やストーキングが社会問題化したのもちょうどこのころで、これらに対しては
DV防止法
(平成13年4月13日法律第31号「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律」)、
ストーカー規制法
(平成12年法律第81号「ストーカー行為等の規制等に関する法律」)が相次いで制定された。
しかし、諸外国と比較して、我が国における被害者保護政策は今だ極めて遅れているといっていい。そもそも、「被害者」が学問的に研究されはじめたのは1948年のハンス・フォン・ヘンティッヒ(ドイツ・ボン大学教授)の著書『犯罪者とその被害者』からだが、1958年に我が国にはじめてそれが紹介されたものの、実際に被害者補償法制が成立したのは1980年のことであり(昭和55年5月1日法律第36号「
犯罪被害者給付金支給法
」)、東京医科歯科大学に民間初の「犯罪被害者相談室」(現在、社団法人・被害者支援都民センター)が設立されたのが1992年、警察庁の「被害者対策要綱」が制定されたのが1996年(警察庁次長通達)、検察庁の「被害者等通知制度」が出来たのが1999年。そしてようやく2000年になって、上記被害者保護ニ法(
犯罪被害者保護法
、刑事訴訟法改正法)や少年法改正、
犯罪被害者給付金支給法
改正(2001年)に至ったのであった。前出の岡村弁護士が代表幹事を務める「全国犯罪被害者の会(あすの会)」の資料によれば、現在、加害者に対しては医療費、食料費、光熱費、生活管理費、国選弁護費等に427億9104万円(平成12年度)使われているのに対し、被害者には、
犯罪被害者給付金支給法
に基づく給付金が5億6800万円支払われているだけで(平成12年度)、それも国内の重大犯罪被害者に限定されているという。
そこで本稿では、何故、我が国においては被害者対策がこれほどまでに遅れてしまったのか、また今後「被害者の権利」を一層確立するためには、何が必要なのかについて、私見を述べて行きたい。
■第2章 刑事法制の基本的性格
刑事手続とは、犯罪と刑罰を定める実体法である
刑法
(明治40年法律第45号)に規定された犯罪行為を行った者に対して、刑罰を課すための具体的実現に関する手続きのことであり、我が国においては、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)、刑事訴訟規則(昭和23年最高裁規則第32号)、少年法(昭和23年法律第168号)等で具体的に規定されている。
そもそも我が国の刑事手続は、戦前にあっては、強い欧州法の影響下にあったため、訴訟とはいえ裁判所自らが実質的真実究明を目指して捜査、公判を遂行する職権主義的、糾問主義的な制度が採用されていた。例えば、戦前の判事(裁判官)は検事(検察官)と共に(行政府たる)司法省の管轄下にあり(ちなみに、当時は裁判所も司法省の管轄下にあった)、また法廷では判事と検事が正面の一段高いところに同列に着席し、弁護人は被告人と共に判検事と対面する二面構造を採用していた。
しかし戦後の占領改革で、「刑事手続は民事手続と同じ」と考え、「実質的真実の究明」よりも「適正手続の保障」を重視する戦前米国法の影響を受けた刑事訴訟法の全面改正が為された(現行刑事訴訟法は戦前のイリノイ州刑訴法を、また少年法は1943年の模範少年法をモデルにしている)。その結果、「対等な社会構成員間の法的紛争を処理する」という民事司法の考え方が導入され、検察当局も被告人(加害者)とと同じく対等な立場に立つものとされた。米本国ではこの考え方が徹底されており、その為「対等」である当事者同志で司法取引を行い、被告人との間の法的紛争を双方の同意で消滅させることも認められる(市民間で和解するのと同様の感覚で「取引」するのである)。何故ならば、(後述するように)民事訴訟とは「法」を使った当事者間の私的紛争の処理であり、当事者同志がそもそも「紛争が無い」と考えれば法を持ち出す必要が無くなるからである。こうした当事者主義(弾劾主義)の考え方は一部が現行法が導入され、現行刑事訴訟法は原告(検察官)と被告(被告人)とが対立して攻撃・防御を行い、その主張について裁判所が第3者の立場から判断を下すという「訴訟」の類型(三面構造、対審構造)を採用している(※参考:刑事訴訟法第1条)。
| 裁判官(判事) 検察官(検事) | 裁判官 (判 事) | |||||||||
| ↑ ↓ | ||||||||||
| 弁護側 (弁護士) | 弁護側 (弁護士) | ←→ | 検察側 (検 事) | |||||||
▲糾問主義の裁判構造(左)と弾劾主義の裁判構造(右)
しかしながら、こうした刑事法制は、戦前であれ戦後であれ(=法廷の構造がどうであれ)、結局のところ、現在及び将来の「国家社会の治安維持」という行政目的を達成するための手段であった。即ち、「法」には、権力(強制)的要素と正義的要素があるが(なお、これについては月刊「健論」2001年8月増刊号 『法とは何か』 の 第2編「『法』への視点」 を参照して頂きたい)、特に刑法や刑事訴訟法といった「公法」は、そうした政策目的を達成するために制定された政策遂行手段としての法という性格を色濃く有する。そして、現在の刑事法制は、基本的に「刑事行政」の道具として機能しているのである(以下、本稿ではこのような考え方を「刑事行政主義」と呼ぶことにする)。
■第3章 刑事法制における当事者の地位
ところで、こうした(刑事)行政目的を達成するためには、被疑者の権利を制限し、強制力(強制処分)を発動して捜査・公判を行う必要がある。即ち、刑事行政は究極の侵害行政(国民の権利を侵害することで行政目的を達成するもの)であり、被疑者及びその関係者の精神・身体の自由その他の基本的な人権を侵害する危険性が高い(事実、強制処分はそうした法益侵害を一定の範囲内で認めるものー逮捕や押収ーであり、それが正当化されるのは
法令行為<刑法第35条>
として違法性が阻却されるからに他ならない)。その為、基本的人権の尊重を基本原理とする
日本国憲法
は、
第31条
から
第40条
にかけて、刑事訴訟のあり方に関して特に詳細な規定を持っており、刑事訴訟法もまたそうした憲法上の保障も踏まえて、幾つかの重要な原則を定めている。その具体例を実際の刑事手続に従って列挙すれば、まず捜査に関して、「任意捜査の原則」(刑事訴訟法第197条1項)・「強制処分法定主義」(刑事訴訟法第197条1項但書)、「令状主義」(
日本国憲法第33条〜第35条
)があり、続いて公訴提起に関して「起訴状一本主義」(予断排除の原則、刑事訴訟法第256条第6項)、公判、特に事実認定に関して「証拠裁判主義」(刑事訴訟法第317条)、「弁論主義」(刑事訴訟法第298条第1項、但し第2項は職権探知主義を認める)、「自由心証主義」(刑事訴訟法第318条)、「自白法則」(
日本国憲法第38条第2項第3項
、刑事訴訟法第319条第1項)、「伝聞法則」(刑事訴訟法第320条第1項、例外は第321条以下)、「違法収集証拠の排除法則」(学説)、「疑わしきは被告人の利益に(無罪推定)」、また刑が確定した時点で「一事不再理」(日本国憲法第39条)といったものがあり、更に刑事手続全体に関して「弁護人選任権」(
日本国憲法第34条
、刑事訴訟法第30等)、「法定適正手続の保障(手続法定の原則)」(
日本国憲法第31条
)及び「黙秘権の保障」(
日本国憲法第38条1項
、刑事訴訟法第198条2項、第291条2項、第311条1項等)が挙げられる。即ち、犯罪の加害者は、「(侵害行政である)刑事行政の客体」であるが故に、彼・彼女が強力な行政権に対抗できるよう手厚く保護されているのである。
他方、犯罪被害者は、刑事行政主義の下においては、その「主体」であるところの警察官・検察官・裁判官(以下、「刑事当局」とする)の「持ち駒」の一つに過ぎない。現に、
犯罪被害者保護法
成立以前の我が国では(一部は同法成立以後も変わらないが)、被害者が刑事手続に関与できるのは、①警察官の「微罪処分」における同意(現行法上、警察官は全ての事件を検察官に送致=送検しなければならないが<全件送致主義、刑事訴訟法第246条>、例外として、検事正の指定する一定の微罪については、「微罪処分」として送検しなくてよい)、②親告罪(被害が軽微だったり、加害者が被害者の親族だったり、被害者のプライバシーに配慮する必要があるので、被害者の告訴を待ってはじめて捜査出来る犯罪。強姦罪・名誉毀損罪等)、③付審判請求(公務員同志で「身内」の犯罪を隠したりしないように、公務員の一定の犯罪で検察官が不起訴処分とした場合、その被害者がこれを裁判所に訴追させることができる制度。刑事訴訟法第262条・第270条)、④検察審査会への申立て(検察官の不起訴処分に対して、一般国民から選ばれた検察審査委員がこれを審査する制度。限定的な陪審制度である。検察審査会法)だけであり、後は非公式的に、⑤上級検察庁への意義申立て(行政不服審査法は検察官の不起訴処分に対しては適用されないが、高等検察庁への上申書提出が事件を動かすことがある)があるだけである(更に犯罪者処遇の段階では、地方更生保護委員会の仮出獄の審査にも関与できる可能性がある)。無論、加害者(被告人)の裁判に呼び出されることもあるが、これはあくまで「被害が生じた」ことを立証する検察側の証人としてであり、被害者固有の権利として法廷に出席し意見を述べることは出来ない。しかも、検察側証人として出廷しても、被害者は検察官の質問に答える形でしか発言できず、更には弁護側の厳しい反対尋問に晒される。2000年の法改正の結果、刑事訴訟法第292条の2で「被害者の意見陳述」が認められたが、この条文は意見陳述を「認めた」に過ぎず、「権利」として被害者に与えているのではない(アメリカでは、既に多くの州が被害者衝撃供述<Victim Impact Statement, VIS>の権利を認めている)。
それどころか、事件の種類によっては、「刑事行政」の遂行上「被害者」を必要としない場合もある。何故ならば、「国家社会の治安維持」という行政目的には、必ずしも被害者の存在は必要ではないからである。典型的なのが刑法上「国家に対する罪」や「社会に対する罪」として規定されたものであり、例えば「国交に関する罪」(
刑法
第2編第4章)や「賭博及び富くじに関する罪」(
刑法
第2編第23章)には直接の「被害者」と呼べるような者は存在しない。しかし賭博行為は、「政府や公共団体が独占する」という行政目的達成のために刑法の中に入れられ、これに反すると刑罰を課される。即ち、ここで「賭博及び富くじに関する罪」は刑事行政の手段として機能しているのであり、被害者は必要無いのである。
■第4章 刑事紛争当事者としての被害者
以上見てきたように、現行制度上、被害者は「刑事行政の主体」たる刑事当局の一要素に過ぎず、刑事手続には極めて限られた役割しか与えられていない。これは、刑事手続を「刑事行政」の一つと見ればある意味当然の帰結であろう。
事実、理論的に見ても、民事紛争と刑事紛争は全く同一ではない。国が直接当事者になるような事件(例えば、行政目的を達成するために罰則を制定し、それに違反した者を処罰する場合)は別として、一般に、民事紛争が当事者同士の相対的・私的なモメゴト(私訴)であり、仮に当事者同士が同意すれば紛争の存在そのものを否定したり、私的に紛争の終結をなすことが出来る(これを当事者主義という)。また、民事紛争は当事者同士の私的事件であるから、紛争相手を提訴できるのはあくまで相手の行動によって自己の権利を侵害された者に限られるのであり、何等の利害関係も無い第三者が関与することは出来ない(このような訴訟を主観訴訟という)。これに対して刑事紛争は、単なる当事者同士の私的紛争として放置することが出来ないほどその事態が深刻であり、その意味では公的な意味を帯びるようになる(だからこそ、刑事訴訟のことを「公訴」、検察官を「公訴官」という。「検察官」の英語訳は「Public Procecutor」である)。従って、例え当事者同士がその紛争の存在を否定したとしても(例えば、暴力団が身内で起きた殺人事件を隠蔽する、等)、それで紛争が処理されたことにはならない。また、例え自己の権利が侵害されたわけではない第三者であっても、その紛争を司法機関に提訴(現行法では検察官への「告発」)し関与することが出来る(このような訴訟を客観訴訟という)。何故ならば、殺人や傷害等の社会規範に著しく反する犯罪行為は、単に相手方(紛争当事者たる被害者)に対する対人的不法行為であるのみならず、社会の一般的規範に反し社会構成員全体に対して脅威を与える対世的違法行為だからである。そして、そのような行為を取締ることは社会全体の公益に資するからこそ、政府は刑事法制を整備し司法警察官、検察官そして刑事法廷を設けて違反者を処罰するのである。
| 刑 | 刑事当局 (国 家) | ||||||
| 事 | ↑ ↓ | ||||||
| 行 | |||||||
| 政 | 犯罪者 加害者 | ←→ | 被害者 | ||||
| 刑 | 事 | 司 | 法 | ||||
▲刑事紛争における刑事行政と刑事司法の関係
しかしながら、被害者は、そのようにして「刑事行政」の一要素であると同時に、「紛争」(Dispute)の当事者であることは疑いない。そもそも、法とは過去におきた社会における紛争を「正義の認定」という側面から解決し処理せんとするもの(そして、それにより社会を統合するもの)である。即ち、二人の当事者(社会構成員)の間に具体的な紛争が発生した時、(1)その紛争を法的に再構成した法的争訟を裁判に提訴し、(2)事実に法律を当てはめて結論を出し(法的三段論法)、(3)その法的結論(判決)を強制執行して事実に反映させ、もって紛争を処理するのである(なお、この定義については本誌2001年8月増刊号 『法とは何か』 を参照して頂きたい)。無論、紛争の処理はこの他にも政治的処理や政治的手法と法的手法を混合させた調停があるが(※下図参照)、法的処理は当事者の一方の(法的)主張を正義であると強く認定し、紛争解決を助長するところにその特徴がある。であるならば、犯罪事件(刑事事件)といっても、それが社会構成員間の紛争であることに変わりは無く、被害者を紛争当事者と把握して彼・彼女に当事者としての法的権利を正面から認めることはむしろ自然ではないだろうか(以下、本稿ではこのような刑事法制の考え方を「刑事司法主義」と呼ぶ)。加害者の行ったことが対世的違法行為であっても、それが同時に対人的紛争であることは否定できないのである(逆に純粋の私人間紛争であっても、それを「裁判」として決着させようとするときは、客観的正義の問題が語られる以上「対世的性質」は僅かながら残っている)。
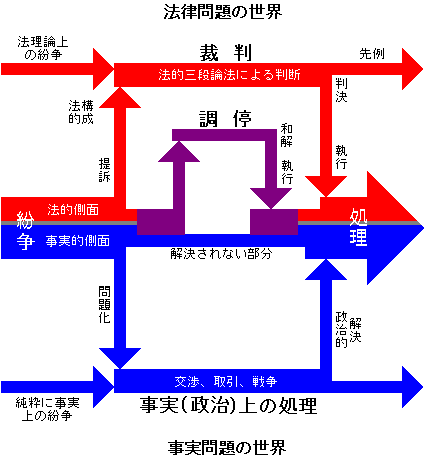
▲紛争とその処理(法的処理、政治的処理、調停)
無論、現行法下でも、その「紛争」の内、民事的側面については「民事紛争」として把握され、損害賠償請求訴訟の対象となっていた。しかし、「民事紛争」による処理は「正義の認定」と(原則として)「金銭賠償」のみであり、例え加害者が生命、身体等の重大な法益を侵害したのだとしても、被害者側は名誉と財産的補填しか得られない。私人の訴追によって加害者の生命や身体を同等に罰することは公序良俗に反すると考えられるからであるが、問題を民事的側面のみに限定しようとすれば、それは「等しき者は等しく扱え」とする形式的正義の論理(あるいは正義基準)に反し、不正であろう。しかも、例え損害賠償請求訴訟を提起したとしても、一般の凶悪犯罪者の場合、加害者には被害者に対する十分な賠償をするほどの資力も無く、殆どの場合は被害者が泣き寝入りするしかない。社会構成員間の紛争であるからといって、金銭賠償以上の刑罰(制裁)を求めることが出来ない理由は無い(財産法上の財産取引に関連した紛争には金銭賠償という財産上の処理しか選択できないにしても、不法行為法まで財産法の流儀に従う必要は無い)。そしてそのことが、刑事的側面への期待ともなるのである。
■第5章 被害者の権利と「修復的司法」
それでは、被害者を刑事紛争の当事者と見た場合、どのような形で被害者を刑事手続の中に地位を確立することが出来るであろうか。
ドイツやフランス等の大陸法諸国、台湾(中華民国)そして戦前の我が国には、刑事訴訟法の中に「附帯私訴」という制度がある。これは、検察官の加害者に対する刑事裁判(公訴)に、被害者の加害者に対する民法上の損害賠償請求(民事訴訟。私訴)を附帯させるものである。通常、被害者は、加害者に対して損害賠償請求訴訟(私訴)を提起するときは、相手(加害者)が自分の権利を侵害し、被害を与えたことを立証し、裁判官を納得させなければならない(即ち、訴訟を提起した被害者側に立証責任がある)。しかし、附帯私訴であれば、刑事裁判で立証された事実や証拠を私訴でもことごとく流用することが出来ることから、被害者としては新たな民事訴訟や立証をする必要が無く、立証責任が軽減される。しかも、私訴の原告として主体的に刑事裁判に参加することが出来るので、単なる刑事行政の客体の地位に甘んじることもない。また、現在の制度では刑事裁判と民事裁判が別々に行われるため、場合によっては刑事裁判と民事裁判の判決が異なる可能性がある(例えば、刑事裁判では無罪になった被告人=加害者が民事裁判では有罪になる)(これを「矛盾裁判」という)が、附帯私訴であればそのような事態も避けられる。
他方、イギリスやアメリカ等の英米法国(コモン・ロー諸国)では、刑罰の中に被害者に対して損害賠償を命じる制度がある(損害賠償命令)。これは、附帯私訴とは異なり、加害者に対する刑罰(即ち、刑事訴訟)の一貫として被害者の回復を図ろうとするもので、附帯私訴のように被害者側からの申立てすら必要ではなく、強制執行も国が自動的に行ってくれる。この制度にも、附帯私訴と同様の利点がある(被害者の立証責任の軽減、刑事裁判における被害者の立場の強化、矛盾裁判の回避)。
| 伝統的な刑事司法 | 修復的司法(RJ) | |
| 事件の概念 | 犯罪 | 紛争、害悪 |
| 事件に対する対応 | 権力的手段 (刑罰、処分等) | 理性的手段 (対話等) |
| 刑事手続の目的 | 犯罪者の処罰・更生 | 紛争処理、損害回復 |
| 当事者 | 国家と犯罪者 | 被害者と犯罪者 |
▲従来の刑事司法と修復的司法との違い
近年、これらの伝統的な被害者支援制度に加えて、「修復的司法」(Restorative Justice)なる考え方が提唱されている。これは、既に本稿第4章で見てきたように、刑事手続を従来のような国家対犯罪者の犯罪事件としてではなく、被害者との犯罪者の紛争と見る考え方である。修復的司法に連なる考え方は1970年にカナダのキッチナーで始まった「被害者=犯罪者和解」制度で、これが1970年代後半に北米から欧州にかけてVOM(Victim-Offender Mediation。被害者犯罪者調停)、VORP(Victim-Offender Reconciliation Program、被害者犯罪者和解手続)等という名前で広まった。これらの制度は被害者と犯罪者の対話によって不起訴処分を下したり示談交渉を成立させたりするもので、「被害者支援」と共に「犯罪者の社会復帰、ダイバージョン」という2つの意義を持っていた。一方、これとは別に、ニュージーランドでは1980年代末から先住民族マオリ族の慣習を応用した家族集団協議(FGC、Family Group Conferencing)という制度が導入され、これがオーストラリアやアメリカに広まった。これは、「シェイミング理論」(逆ラベリング理論。敢えて加害少年に犯罪者であるとのレッテルを貼る)に基づいて、加害少年に自己の犯した罪を自覚させるもので、主として少年犯罪における加害者の社会復帰を念頭に置いていた。その他、修復的司法の考え方に類似するものとして、世界各地には量刑サークル(Senting Circle。カナダ・ユーコン準州のインディアンに対する制度。インディアンは国家の刑罰に感応しないので、地域の名士が量刑を行う)やバランガイ司法(フィリピン。「隣り組」による司法)、アダット(インドネシア慣習法)といった制度がある。
修復的司法は、犯罪の真相や動機、被害者の悲しみや怒りを直接犯罪者から聞き出し、あるいは聞かせることが出来る点、犯罪者からの再被害やお札参りを防止できる点、そして犯罪処理(刑事手続)に主体的に参加することが出来る点で、被害者にとって有益である。そればかりか、犯罪者(加害者)の側も、被害者の悲しみや怒りを直接受けて更生の手掛かりとしたり、被害者の損害回復に関与して罪悪感を軽減したりといった点で有用であるし、更には国家・社会としても、司法に対する信頼を維持したり法執行機関の負担を軽減させることが出来る(ダイバージョンを行う場合)。
その一方で、修復的司法にはいくつかの問題点が指摘されている。第一に、この制度によって犯罪者と対面したくない被害者に対面を強制したり、犯罪者側が量刑緩和を目論んで口先だけの謝罪を行ったりする可能性がある。これでは、損害回復にも犯罪者更生にも結びつかないばかりか、却って司法機関が扱う事件数が増え(統制網拡大効果)、裁判所・警察・検察の負担が増えることも考えられる。また、第ニに、この制度は刑事事件を加害者と被害者の紛争を見るので、その目的は被害者の被害回復と共に加害者の更生にも置かれるが、後者を重視し過ぎると、結局被害者を今度は犯罪者処遇・更生の道具に貶めかねない危険性を孕んでいる。
なお、我が国では近年、
犯罪被害者保護法第4条
で「刑事和解」(刑事裁判上の和解)なる制度が新設された。これは、当事者間で成立した示談(和解契約)を公判調書に記載することで和解契約の成立を公証するもので、これにより被害者は直ちに刑事事件の判決を以って債務名義を取得し、加害者に対して強制執行が出来るようになった(ある契約の結果を強制執行するには「債務名義」が必要で、通常の示談では、示談交渉の結果を公正証書で作成しない限り「債務名義」は得られなかった。従って、被害者はこれまで、一旦示談に応じた加害者が和解金の支払いを拒否したときは、改めて和解契約の存在確認を求めて民事裁判を起こし、勝訴判決を得てこれを強制執行する必要があった)。無論、この制度は加害者との示談交渉がまとまったときにしか使えないが、民刑分離思想を打ち破る制度として注目される。
では何故我が国でこのような制度が存在しないのか。それは、我が国においては先ほど指摘した民事紛争と刑事紛争の区別(民刑分離)が厳格にされたことと無関係ではない。即ち、現在の刑法理論の通説では、犯罪者に対する応報としての刑罰よりも犯罪者を社会復帰させることのほうに主眼が置かれ(応報刑理論から教育刑理論へ)、それこそが困難であり先に考えられるべき問題だと認識されている。その為、そもそも応報的な色彩を持つ被害者支援・被害回復は犯罪者の社会復帰とは矛盾するものとされ、対被害者関係は民事訴訟に集約されると考えられてきたのである。「もう二度と過ちを犯さない」と誓った犯罪者を簡単に許す日本と、それだけでなく「被害者に対する責任」を果たしてはじめて犯罪者は許されるのだとする欧米。その違いが、被害者に対する法的地位の違いとなって現れたのである。加えて、附帯私訴制度も損害賠償命令制度も、加害者に十分な資力が無いことが多いので実際には履行率が低くなりがちであるし、附帯私訴であると却って訴訟を遅延させたり、公訴が提起されなかったとき(不起訴処分、起訴猶予処分)に問題を残す、とされる(なお、フランスでは起訴強制主義と予審制度を採用しているので、我が国のように検察官が裁判官の関与しない中で不起訴処分や起訴猶予処分を決めてしまうことは無い)。
更に、戦後の我が国においては、政府(在朝法曹)ばかりでなく民間(在野法曹)即ち弁護士や刑法学者の側にも、刑事行政主義の維持と被害者の放置に加担した。確かに、上述したように刑事法制を「刑事行政」と見た場合、その客体たる犯罪者の権利を厚く保護することは必要であるし、また憲法上の要請でもあった。しかし、そうして「法」の権力的側面のみを強調しすぎた結果、被害者の権利や損害回復を重視することは厳罰化=行政権力の強化に繋がるものとして排斥され(例えば、被害者が法廷で意見を供述すると、それが裁判官に過剰に作用して量刑判断が重くなりすぎる、といった主張が今でもある)、刑事司法主義的な考え方を遂に持ち得なかったのである。しかも、「現在」及び「将来」を志向する刑事行政主義(現在及び将来の秩序維持を目指すのが「行政」である)にとって最大の関心事は「将来」の「再発防止」(加害者の社会復帰)であり、「過去」を志向する刑事司法主義(過去の紛争を法的に処理するのが「司法」である)とはそもそも「顔の向いている方向」が異なる。例えば少年法について、被害者保護を企図した一昨年の法改正の際「少年の立ち直りを妨げるもの」として反対の大合唱があがったことは記憶に新しい(この問題については、
本誌2000年12月号
「
少年法改正に賛同する
」を併せて参照して頂きたい。刑事政策の「専門家」は非行少年の「将来の立ち直り」や「再犯防止」を根拠に改正反対論を強く主張したが、これは刑事行政主義的な発想に基づく主張であり、刑事司法主義を主張する改正論者に対しては何等説得力を持ち得なかった)。
■第6章 おわりに:刑事「行政」から刑事「司法」へ
無論、被害者問題は法制度上のものだけではない。多くの重大犯罪被害者は、承諾なくして実名を報道され、近隣住民は興味本位の噂やヒソヒソ話で被害者を巻き込み、犯罪の種類によっては被害者側の落ち度を詮索され、無用な批判や誹謗・中傷を受けることもある。被害者自身が負ったASD(急性ストレス障害)やPTSD(心的外傷後ストレス障害)等の精神的障害や四肢の肉体的損害は、自力でこれを回復しなければならない。実際、1978年8月の三重県「隣人訴訟」事件(津地判昭和58年2月25日判例時報1083号125頁)では、弁護士による不用意な民事訴訟提起の勧奨と、それを興味本位で報じた新聞・テレビが却って紛争を劇化させてしまった(詳細は月刊「健論」2001年8月増刊号
『法とは何か』
の
第4編第2章第3節
を参照して頂きたい)。こうした実態も、結局は被害者の権利が正面から認められて来なかったことの弊害なのである。
刑事行政は本来、社会秩序を乱した犯罪者を処罰するというだけでなく、それによって被害を受けた国民を支援することも含まれるはずである。最近になって、被害者学の発達や犯罪被害者の権利確立を求める運動により、第1章で指摘したような様々な法律が制定され、限定的ながら情報の開示や刑事手続参加(
犯罪被害者保護法
、刑事訴訟法第292条の2)、損害回復(
犯罪被害者給付金支給法
)が図られるようになってきた。しかし実際の刑事行政の基本的哲学は、刑事事件を担当する裁判官から現場の警察官まで、国家社会の治安・秩序を維持するという行政目的を達成することに今なお主眼が置かれ、刑事法はその手段と化している(法道具主義)。そしてそれ故に、加害者は国家行政の客体として厚く保護され、起訴するかどうか、裁判の期日をいつにするかは被害者と無関係に決められ、訴状も、冒頭陳述書も、論告要旨も、判決も被害者には送られて来ない。つい最近まで、遺族が殺された被害者本人の遺影を持ち込むことすら、「刑事行政の邪魔になる」として排除されていたのである。今こそ、刑事事件に対する国家の関与のあり方を刑事「行政」から刑事「司法」へと転換し、刑事手続における被害者の位置を「要素」から「主体」へと昇格させ、被害者の法的地位向上を図るべきではないだろうか。
既に、いくつかの被害者学者や日本弁護士連合会が「犯罪被害者基本法」の制定を主張しているが、刑事司法への転換を図る基本的方向性を定めるものとして必要であろう。既にいくつか紹介した最近の一連の法改正は確かに我が国犯罪者保護史上大きな進歩であったが、いずれも「刑事行政主義」の枠組みを維持し、対症療法的に行われたものに過ぎない。例えば、
犯罪被害者保護法第2条
で認められた被害者の優先傍聴も「権利」ではなく、裁判所の配慮規定である。これは、犯罪被害者の立場が依然として訴訟の当事者ではなく、そうであるとすればそうした第三者に傍聴の「権利」を与えることは出来ない、とされたからである。その他の規定も概ね同様の問題を含んでおり(例えば、少年法)、戦後GHQが主導して制定した現行刑事訴訟法(イリノイ州法をモデルにしているとされる)は、特にその傾向が強い。参考までに、本サイトに
被害者基本法案・健論会私案
を掲げておく。
我々は、意識して加害者・犯罪者となることを避けることは出来る。しかし、被害者となる潜在的な可能性からは、誰も逃れられないのである。
※主要参考文献
市川正人・酒巻 匡・山本和彦 『現代の裁判』 有斐閣アルマ、1998年
井田 良 『基礎から学ぶ刑事法』 有斐閣、1995年
井上達夫 『共生の作法ー会話としての正義ー』 創文社現代自由学芸叢書、1986年
小島武司編 『裁判キーワード』新版補訂版 有斐閣、2000年
小島武司編 『現代裁判法』 三嶺書房、1987年
椎橋隆幸・高橋則夫・川出敏裕 『わかりやすい犯罪被害者保護制度』 有斐閣リブレ、2001年
椎橋隆幸 「犯罪被害者保護・支援の課題と展望」 『法律のひろば』2001年6月号
田中成明 『法理学講義』 有斐閣、1994年
田中成明 『転換期の日本法』 岩波書店、2000年
田中成明 『法理学講義』 有斐閣、1994年
田中成明 『法的思考とはどのようなものか』 有斐閣、1989年
田中成明 『法の考え方と用い方』 大蔵省印刷局、1990年
田宮 裕 『刑事訴訟法』 有斐閣、1992年
船山恭範・清水洋雄・中村雄一 『スタッフ刑事政策』 こぶし社、2000年
諸沢英道 『被害者学入門』新版 成文堂、1998年
六本佳平 『日本の法システム』 放送大学振興会、2000年
我妻 栄他 『新法律学辞典』新版 有斐閣、1967年
和田安弘 『法と紛争の社会学』 社会思想社、1994年
各種被害者団体のホームページ
その他
中島 健(なかじま・たけし) 大学生