裁判官に政治活動の自由を認めるべきか(第1回)
〜法的紛争処理の本質に迫る〜
中島 健
■目次
■第1章 はじめに 第1節 寺西和史判事補事件 第2節 高まる処分反対論 第3節 問題意識 ■第2章 処分反対論の根拠 ■第3章 「裁判」の機能と政治活動 | (以下、次回) 第2節 公平性維持の必要性 1、フィクションを演じる必要性 2、裁判実務に反映されている「フィクション性」 3、価値観の多様化と手続的正義の重要性 4、総合知、実践知としての法学 第3節 比較法学的立場の難点 ■第4章 寺西判事補の行動について ■第5章 おわりに |
■第1章 はじめに
●第1節 寺西和史判事補事件
1998年5月24日、仙台高等裁判所は、仙台地裁(泉山禎治所長)が申し立てた同地裁の寺西和史判事補(当時33歳)に対する懲戒処分を求める分限裁判で、同判事補を戒告処分とする決定をした。この分限裁判は、寺西判事補が同年4月18日、当時国会で審議中だった組織的犯罪対策法案(特に通信傍受法案)に反対する集会「つぶせ!盗聴法・組織犯罪対策法 許すな!警察管理社会4/18大集会」に出席し、「パネリストとして話すつもりだったが、所長に『処分もありうる』と警告された。仮に法案に反対の立場で発言しても積極的な政治運動には当たるとは思わない」等と発言し、言外に法案に反対する意思を表明したため、仙台地裁の裁判官分限法(昭和22年法律第127号)に基づく懲戒の申立てを受けて行われたもので、政治運動を理由とするものとしては初めてのケースだという。申立て理由について地裁は、「多数の者が集まった会場において、仙台地方裁判所の裁判官であることを明らかにした上、『集会でパネリストとして話すつもりだったが、泉山仙台地裁所長に『処分する』と言われた。法案に反対することは禁止されていないと思う。』旨の発言をし、言外に右法案に反対する意思を明らかにして同法案に反対する運動を盛り上げ、もって、集会主催団体の主張を支持する目的で、裁判官という職名の有する影響力を利用し、多数の者が集まる集会で同主張を支持する趣旨の発言をしたものである」とし、これが
裁判所法
(昭和22年法律第59号)
第52条第1号
にいう「積極的に政治運動をすること」に該当し、
同法第49条
にいう「職務上の義務に違反した」としている(この種の事件は戦後はじめてのことである)。
処分を決定した仙台高裁の小林啓二裁判長は、「裁判官はその地位、身分に伴って当然、積極的な政治運動をしないことを職務上の義務として求められていると解するべきである」との判断を示し、「裁判官が身分を明らかにして政治的立場に肩入れした場合は、法規による制約を加えられ、秩序罰として相応の処分もやむを得ない」「裁判官が特定の政治的立場にあることが分かれば、事件の当事者や関係者が判断内容を素直に受け取らなくなる恐れがある」とした。裁判で寺西判事補側は「発言は法案に一切触れず、パネリストとして参加することができない理由を述べただけ」などと主張したが、決定は「現職の裁判官であると明らかにし、地位を利用して見解を語ろうとした」と認定し、「現職の裁判官にも法案に反対する人がいることを鮮明に印象づけ、反対運動を盛り上げる一助になったのは明白」として被告人側の主張を退けた。
▲最高裁判所(東京都千代田区)
更に、寺西判事補側の即時抗告を棄却した 最高裁判所 大法廷(裁判長・山口 繁長官、最高裁判所民事判例集52巻9号1761ページ、平成10年12月1日)は、「寺西判事補の言動は積極的政治運動で職務義務に反し、戒告が相当」として仙台高裁決定を支持した(判事5人は反対意見)上で、「三権分立制度の下で司法権・違憲立法審査権などを持つ裁判官は外見上も中立・公正を害さないよう政治的勢力とは一線を画すべきだ」と指摘。「積極的な政治運動」を「組織的、継続的な政治上の活動を能動的に行い、裁判官の独立などを害する恐れがある行為」と定義し、裁判官の表現の自由の制約は「裁判への国民の信頼維持など立法目的は正当。禁止により得られる利益は失われる利益に比べ重要で、利益の均衡を失わない」「一国民として、中立・公正を疑われない場での反対意見表明は禁止されない」と合憲の判断を示した。
※注記
『ジュリスト』1150号(1999年2月15日号) 有斐閣
もっとも、最高裁の「積極的な政治運動」の定義はなお謙抑的であり、より厳しい制限が必要であると思われる。
●第2節 高まる処分反対論
ところが、この事件に対しては、「懲戒処分は不当、違法だ」「寺西判事補は『積極的に政治運動』をしたわけではない」等として、憲法学者や弁護士の間で早くから処分反対論が巻き起こり、「裁判官にも表現の自由、政治活動の自由がある」「裁判官が市民的立場で発言することはよいはずだ」といった主張に発展している。1998年5月22日には、
日本弁護士連合会
の小堀 樹会長も「裁判官の行動が自由、闊達であることがむしろ独立・公正・公平な裁判の実現を保障するものとの考え方」に立つべきことを主張する声明を発表している(※注意)。
▲日本弁護士連合会(東京都千代田区・弁護士会館)
※注記
反対論の概要については、後述する。
なお、本件は、『憲法判例百選Ⅱ(第4版)』(「ジュリスト」別冊)189事件として収録されている。
●第3節 問題意識
しかし、この問題は、後でも述べるように、我が国司法システムの根幹である「裁判官のあり方」を巡る問題であり、本質的には我が国の法秩序そのものに重大な影響を与える可能性がある。よって、この問題を論じるにあたっては、そうした観点からの本質的考察を欠かすことが出来ない。
では、果たして裁判官の「自由、闊達な」政治活動の自由は、認められるべきなのであろうか。本小論では、反対派の主張を整理した上で、この問題に対する回答を提示してみたい。
※参考:
裁判所法第52条
第五十二条(政治運動等の禁止)
裁判官は、在任中、左の行為をすることができない。
一 国会若しくは地方公共団体の議会の議員となり、又は積極的に政治運動をすること。
二 最高裁判所の許可のある場合を除いて、報酬のある他の職務に従事すること。
三 商業を営み、その他金銭上の利益を目的とする業務を行うこと。
■第2章 処分反対論の根拠
●第1節 憲法上の政治活動の自由
今回の事件で噴出した処分反対論はまず、
日本国憲法
及び
裁判所法
の解釈上の問題を指摘する。
一つは、今回の寺西判事補の発言及び行動は、そもそも
裁判所法第52条第1号
に規定する「積極的な政治活動」ではない、として、処分に反対するものである。即ち、『積極的な政治活動』とは、特定政党の応援演説に出るとか、どこかの政治団体の機関紙の対談に出る等、特定の政党を積極的に支援する行動を言うのであって、今回の寺西判事補の発言はそれに該当しないない以上『積極的な政治活動』にはあたらない」というのである。
第ニに、そもそも裁判官には
基本的人権
の一つとしての「政治活動の自由」が認められてしかるべきであり(
憲法第3章
)、これを大幅に制限する
裁判所法第52条第1号
の解釈は法令違憲乃至適用違憲である、とするものである。上に紹介した日弁連の会長声明の中で、同会の小堀会長は、(1)裁判官も又「基本的人権」としての政治的権利を持ち、(内在的制約はあろうが)この権利を事実上失わせてはならない、(2)「積極的政治運動」の定義は慎重かつ厳格に解釈される必要がある、(3)国民の基本権を十分享受した裁判官こそが独立して公正・公平な裁判を実現できるというのが世界的な潮流であり、裁判官が政治的課題等についても自由に意見表明している諸外国と比較して、わが国の裁判官の行動は制約されすぎている感がある、等としている。
※注釈
本 秀紀 「裁判官の政治運動」『憲法判例百選Ⅱ(第4版)』(「ジュリスト」別冊) 有斐閣、2000年 394〜395ページ。
棟方快行 「裁判官の独立と市民的自由」『ジュリスト』1150号(1999年2月15日号) 有斐閣
●第2節 国民の司法に対する信頼
次に、処分反対派は、最高裁などが「違憲立法審査権などを持つ裁判官は外見上も中立・公正を害さないよう政治的勢力とは一線を画すべきだ」「裁判への国民の信頼維持など立法目的は正当」等としていることに対し、そうした「国民の信頼」は、裁判官が政治活動を行っても揺るがないとしている。1人の裁判官の、プライベートな場での政治活動が、そのまま司法権そのものへの不信感に転嫁されるほど国民は愚かではなく、「国民の信頼」は、適正手続が保障された法廷において、専門技術家としての優れた事実認定や法適用をする点においてなのであって、裁判官個人の政治色は問題ではないというのである(※注意)。反対論者は又、裁判官といえども市民であり、政治的に無色透明ではあり得ないことは確実である以上、最初から「中立・公正な裁判官像」等というのは存在しないのであって、故に市民的自由を認めても実質的に問題は無い、とも主張している。
※注釈
本、棟方前掲書。
これについて棟方・神戸大学教授は、「裁判官が当事者主義的構造の適性な手続のなかで、憲法・法律の純粋な解釈作業を行っていれば、それで自動的に満足され、裁判官にそれ以上の何らかの作為・不作為を命じるものではない。」と述べている。もっとも、そうといえる具体的根拠は全く明らかにはされていないし、歴史的経緯に言及がなされていないのだが。
なお、この中で本は、一般職の国家公務員の政治行為を規制した国家公務員法第102条・人事院規則14-7と裁判所法第52条を比較し、前者がより詳細な規定を置いていることから、これを以って裁判官の政治的自由を広く認めたものと解するほうが適合的である、と述べているが、基礎法学的視点を踏まえない概念法学的な反駁である。
●第3節 諸外国との比較
上記日弁連会長声明でも指摘されているが、処分反対派は、諸外国の裁判官が比較的広い市民的自由を得ていることを、その主張の一つの根拠にしている。例えば、「毎日新聞」に掲載された北海道大学法学部・木佐茂男教授の話によれば、欧州では裁判官が反核平和運動、区議会議員、環境保護運動や亡命者の生活の援助までもしているというが、例えば戦後の(西)ドイツでは、戦前のナチズム(国家社会主義運動)に司法が加担したことの反省から、「市民のため」「民主主義のため」という姿勢を明確にし、多くの裁判官が政治活動を行っているという。実際、ナチズムの後遺症が深いドイツでは、裁判官のみならず一般国民も「憲法忠誠」という形で民主主義の擁護を求められ、反民主的政党は憲法裁判所により結社禁止となり、法学の世界でも、法実証主義に代ってグスタフ・ラードブルフGustav Radbruch(ドイツ、1878年〜1949年、ワイマール期の法相)らにより再生自然法論が主張された。
※注記:
その他に、工藤達朗 「ドイツにおける裁判官の政治活動の自由」『ジュリスト』1150号(1999年2月15日号)、川岸令和 「裁判官と表現の自由ーアメリカの経験を通して考える」『ジュリスト』1150号(1999年2月15日号)を参考とした。
※参考:日弁連会長声明
寺西判事補への裁判官分限法に基づく懲戒の申立に関する会長声明
仙台地方裁判所は本年5月1日、仙台高等裁判所に対し、同地裁寺西和史判事補について裁判官分限法に基づく懲戒の申立をした。申立ての理由によれば、同判事補が本年4月18日、いわゆる組織的犯罪対策三法案に反対する集会に参加し、「多数の者が集まった会場において、仙台地方裁判所の裁判官であることを明らかにした上、『集会でパネリストとして話すつもりだったが、地裁所長に処分すると言われた。法案に反対することは禁止されていないと思う。』旨の発言をし、言外に右法案に反対する意思を明らかにして同法案に反対する運動を盛り上げ、もって、集会主催団体の主張を支持する目的で、裁判官という職名の有する影響力を利用し、多数の者が集まる集会で同主張を支持する趣旨の発言をしたものである」とし、これが「
裁判所法第52条1号
にいう『積極的に政治運動をすること』に該当し、
同法49条
にいう職務上の義務に違反した」とするものである。
憲法上の基本的人権にもとづくものとして国民に保障されている政治参加および政治的諸活動の自由は、裁判官といえどもまた当然享受し得るところである。裁判官の場合、その職権の独立と公正の維持の観点から、その権利の享受に一定の内在的制約がありうるが、政治活動の自由という基本的権利を事実上失わせるようなことがあってはならない。従って、何が「積極的政治運動」であるかについては、憲法上の権利保障を基本にして慎重かつ厳格に解釈される必要がある。
今日、国民としての基本的権利を十分に享受している裁判官こそが独立して公正・公平な裁判を実現できるという考えが世界の潮流となり、世界各国において裁判官が政治的課題等についても自由に意見表明している例が多い。それらに照らしても、わが国の裁判官の行動の自由は、あまりにも制約されすぎている感がある。今回の同判事補に対する分限裁判においてどのような判断が示されるかによっては、わが国の裁判官の行動の自由がさらに制約される方向に向かうのではないかと危惧される。
当連合会は、本件分限裁判においては適正な手続のもとに事実関係および法律論に関する個別の論点について慎重な審理を行い、裁判官の行動が自由、闊達であることがむしろ独立・公正・公平な裁判の実現を保障するものとの考え方に立って、国民が納得できる妥当な結論を出されることを求めるものである。
■第3章 「裁判」の機能と政治活動
しかし、「裁判官の政治活動」を論ずるにあたっては、その公職としての特性や職務の本質の理解を踏まえ、我が国の現実の国法秩序全体から見て慎重な判断を下さなければならない。何故ならば、「裁判」とは単に法理論の世界、観念の世界の出来事なのではなく、社会における具体的な紛争処理機関として、「法の世界」と「事実の世界」の橋渡し役として存在しているのであって、その社会的な位置付けを理解せずして「裁判官の中立性」の問題を語ることは出来ないからである。
その点、以上見てきた処分反対論は、いずれも「裁判」あるいは「法の支配」という営為の本質的・社会的機能に対する考察を欠いたまま、憲法上の人権保障規定や法文化が異なる諸外国の事例を無批判に導入し、表層的・概念法学的な反論を試みているに過ぎない、と言わなければなるまい。例えば、「国民の司法に対する信頼」について処分反対派の棟方快行・神戸大学教授は、裁判官の中立性の要請は「裁判官が当事者主義的構造の適性な手続のなかで、憲法・法律の純粋な解釈作業を行っていれば、それで自動的に満足され、裁判官にそれ以上の何らかの作為・不作為を命じるものではない。」と述べている(※注1)。もっとも、棟方教授は、なぜそうと言い切れるのかについては、単に「裁判官の独立・裁判官の中立性は、いずれも司法が法解釈機関であってその他の何者でもない、という命題の言い換えにすぎないはずである。」と述べるに留まり、法理論上の、論理的な概念操作以上の根拠を示していない。だが、この問題に対する棟方教授の視座は結局、憲法の論理的解釈(言わば、「論理の遊び」)の範囲から一歩も外に出ていない(また、出ようともしていない)がために(※注2)(※注3)、「そもそも司法権の独立・裁判官の独立・裁判官の中立性は、いずれも司法権の法解釈機関という特性に、すなわち本来的な非民主性(民主的正当化にははじめからなじまないという)に裏打ちされたもの・・・」「・・・フルタイムの『中立性』は、右にみたような裁判官の中立性とは似て非なるものである」と述べるに至り、最高裁決定がいう「国民の信頼」の意味内容を誤解している。
そこで、本章では、「裁判」の機能をその社会的文脈から改めて明らかにした上で、その紛争処理機関としての特質と限界を示し、「裁判官の中立性」が要求される実質的根拠を明らかにする。
※注釈
1:棟方前掲書、13ページ。
2:「言い換えにすぎない」というのは、自らの主張が結局「トートロジーにすぎない」と認めている、ということである。
3:それが証拠に、棟方教授は、「その都度の『国民の信頼』に拘泥せずに純粋に法解釈を貫くことこそが、裁判官の中立性の要請にかなった態度というべきである」と述べている。裁判官の判決が民主的正当性(即ち、多数決による民意の裏付け)から自由であるべきだ(「数」の論理ではなく「理性」の論理であるべきだ)という点については同意できるが、それは何も「事実の世界」と「法の世界」を二分して、紛争処理機関である裁判所や裁判官を「事実の世界」から超然たる位置に置くことと同義ではない。
また、棟方教授は、続けて「裁判官に対する『国民の信頼』なるものがありうるとすれば、それは・・・裁判官が専門技術的に優れた事実認定・法解釈のテクニックを用いて紛争を解決するという点に寄せられているのである。」と述べているが、法史学上の根拠を欠いた主張で説得力が無い。
更に教授は、最高裁決定について「法解釈は純粋な論理操作ではなく、実は政治的決断である、という法学的リアリズムの過剰な思い入れ」と評しているが、自らの主張が何等社会的視座を持たないものであることを棚に上げての最高裁批判であり(「社会あるところ法あり」と言われるように、法は社会的存在である)、そもそも批判になっていない。
●第1節 司法裁判の特色
▲1、司法裁判の特色
そもそも、「法」の目的とは「正義」と「法的安定性」の実現であると言われるが(※注1)、「司法裁判」とはその「法」を使った紛争処理手段、即ち「法的思考」による紛争処理手段であるということができる(※注2)。では「法的思考」乃至「リーガルマインド(legal mind)」とは、一体何であろうか。
それは、(1)過去に発生したある事実上の個別的な紛争(dispute)を、(2)法的権利義務関係(法的紛争)に還元・再構成し(※注4)、(3)実定法規範を大前提、事実関係を小前提としてこれを適用する法的三段論法(※注5)を行い正当化・解決する手段、と定式化することが出来る(※注6)。
そもそも、司法裁判は、過去に起きた事実上の個別的な紛争(dispute)を扱う。これは、裁判所というものが、本質的に一つの事後的紛争処理手続だからである。例えば、ある人が最近の女子高生の援助交際を問題視していたとしても、それは「問題」「事態」であっても「紛争」ではなく、また一般的な問題であっても個別的な問題ではない。だから、その人が裁判所に出訴して、「女子高生の援助構成が我が国の純風美俗を損ねることの確認判決」を求めたとしても、裁判所は門前払いをするだけである。また、ある法学部の学生が、通説とされるA学説と異端学説とされるB学説のどちらの立場に立つべきかを巡って頭を悩ませ、裁判所に「A学説とB学説のどちらが正しいかを判示」するよう求めたとしても、裁判所は同じく門前払いをするであろう。その「紛争」は、抽象的なものであって事実上の紛争ではないからである(※注3)。更に、同じく事実上の個別的な紛争を扱っていても、それが「過去」に対する正・不正の追及ではなく「現在」の秩序回復を目的としている場合は、それは行政(警察)作用であって司法作用ではない。例えば、国連安全保障理事会が認定した侵略国に対する「経済制裁」は、正確には現在の平和秩序維持を目的とした「非軍事的措置」であって、過去の侵略行為に対する非難である「制裁」ではない(※注4)。
次に、裁判所が扱うのは、当事者間に発生した紛争そのものではなくて、その法的側面(紛争を法的権利義務として理解出来る部分)だけである。これは、そうしてその事実上の紛争を法的紛争に組みかえることによって、紛争当事者・争点・結果(勝負の黒白)を限定し、紛争処理をやりやすくする必要があるからである(※注5)。例えば、ある愛猫家Aと愛犬家Bが、「犬と猫のどちらがかわいいか」を巡って口論になり、「犬がかわいい」と言張ったBに腹を立てたAがBを殴りつけ、殴られたBは打ち所が悪くて骨折してしまったとする。この時、もしAとBが近所の人に「喧嘩の仲裁」を頼んだとき、仲裁人Cはまず、その紛争の根本的原因に立ち戻って両者の善悪を判断するであろう。この例でいえば、果たしてBの主張した「犬のほうが猫よりかわいい」という命題が妥当か否か、である。もし、その命題が全く以って妥当でなく、愛猫家Aを傷つけるようなものであったとしたら、そうした暴言を吐いたBに対してAが腹を立てたことも「やむを得ないもの」とされ、Aは「御咎め無し」となるかもしれない。また、逆に、仲裁人がBの主張を正しいと思えば、正しい事を言ったBを殴ったAは「怪しからぬ奴」となってAの負けになるであろう。だが、こうしたことまで考えていては、「そもそも猫はかわいいのか」「『かわいい』とはどういう概念か」といった形で争点がどんどん増え、紛争は一向に解決しなくなってしまう。もしBが、「私が犬がかわいいといったのは、私の友人のペット研究家Dがそう言ったからである」等と主張すれば、こんどはDをその場に呼んで来て、話を聞かなければならなくなる。しかし、裁判所は、このAB間の紛争の法的側面しか審理せず、他の側面は(原則として)捨象することによって、この危険を回避している。この事例で言えば、裁判所は、両者の問題を、AのBに対する不法行為によるBの損害賠償請求権の問題として扱い、専らAがBを殴りBに損害を与えたかどうかについて判断をすることになる。そして、「猫がかわいいか犬がかわいいか」といった問題については、裁判所は何も言わないし、言うべきでは無いのである。
しかも、この時裁判所が問題を判断する際には、あくまで実定法(施行されている法律)の規定を正当化根拠とし、それに紛争で生じた事実を当てはめて判断を下す(法的三段論法)(※注6)(※注7)。例えば、上記の例で言えば、素人の仲裁人Cは、「でも私はやっぱり猫がスキで、Aさんの気持ちはよくわかる」等と言って、法律以外のことを根拠にして判断を下すかもしれない。そして、「喧嘩の仲裁」の類では、このようなことを正当化の根拠に据えることも許される。しかし、「法的思考」による紛争処理を使命とする裁判官は、自己の趣味や感情によって判決を書くことは許されず(それが許されるのであれば、我々は何も裁判所という国家機関を持つ必要が無くなるであろう)、あくまで法令(憲法、条約、法律、政令、条例等)に書いてあることを根拠にしなければならないのである。
※注釈
1:山田 晟 『法学』新版 東京大学出版会、1964年 76ページ。
そもそも、法の目的は、「法的安定性の確保」と「正義の実現」であった。これは、第一に、法は社会秩序を維持するものとして有効であるためには、それが明確で、一定の期間持続しており、かつ実際に施行されることが要求されるからであり、これが法的安定性である。例えば、「態度が悪い者は切り捨ててよろしい」という法律では内容が不明確なのでいつ処罰を受けるとも知れず、朝令暮改の法律では誰もその法律に価値を見出さなくなる。また、如何にその法律が形式的に美しかったとしても、内容的にそれが国民の規範意識と乖離していれば、その法律が守られる可能性は低い。更に、刑法があっても警察や裁判所がなければ、それは「絵に描いた餅」に過ぎない。しかしながら、法律は又、社会規範である以上一種の正義を有している。「法は最小限度の道徳」であるという言明もある。「法」と「道徳」「正義」とが一致しないものは、長続きしない場合が多い。
2:田中成明 『法理学講義』 有斐閣、1994年 315ページ〜、339ページ。
また、本間康平・田野崎昭夫・光吉利之・塩原 勉編 『社会学概論』新版 有斐閣大学双書、1988年 414ページ。
なお、小島武司編 『現代裁判法』 三嶺書房、1987年 4ページは、「裁判」の特徴として(1)紛争を対象としていること、(2)中立公平な第三者が判断を下すこと、(3)対立する当事者がルールに基づいて攻防をつくすプロセスが保障されていること、の3点を挙げ、「法に従うこと」を加えていない。
勿論、裁判にはこの他にも「権利を保護する機能」「法秩序を維持する機能」等の機能がある。
ところで、今日では、行政国家化現象や立法府の機能低下を踏まえて、司法府に限定的な政策形成機能を期待する議論がある。これがある程度実現したのが公害問題についてであり、我が国裁判所はその他の分野でも国会に対する注意喚起を何度かしている。しかし、裁判所の本質的機能は上記の法的紛争処理であり、また裁判所はそれに最適な「法原理機関」としての組織形態を採用しており、立法府におけるのと同じ意味での「民主性」があるわけでも、また政策立案機能があるわけでもないし、またそれを過度に期待してはならない。立法府の機能低下の問題は、原則として立法府の改革において解決され、司法府は一歩引いた立場からそれをサポートするのが最も適切であろう。
3:「裁判所で扱えない問題」が裁判に持ち込まれた実例として、技術士国家試験の合否判定(最高裁昭和41年2月8日判決)、警察予備隊の違憲確認(警察予備隊違憲訴訟)、地方議会の予算決議の無効確認(最高裁昭和29年2月11日判決)、即位の礼・新嘗祭違憲確認(大阪地裁平成4年11月24日判決)、戦後50年国会決議の無効確認(東京地裁平成7年7月20日判決)、学説の優劣判断を求める訴訟(東京地裁昭和23年11月16日判決)、研究の先後の評価判定を求める訴訟(東京地裁平成4年12月16日判決)、国立富山大学における単位認定(最高裁昭和52年3月15日判決)、郵便貯金の目減りを政府の経済政策の誤りとして賠償を求める訴訟(最高裁昭和57年7月15日判決)等がある。
4:警察で言えば、「過去に発生した具体的犯罪の検挙」にあたるのが「司法警察(刑事警察)」であり、「現在及び将来に向けた一般的秩序維持」にあたるのが「行政警察(警備・公安警察)」である。
5:六本佳平 『法社会学』 有斐閣、1986年 366〜367ページ。
田中成明 『転換期の日本法』 岩波書店、2000年 239ページ。
争点や当事者を限定することは、逆に無用な政治的紛争を避けることができるという利点もある。例えば、ミナミマグロ保存条約の適用解釈を巡って我が国とオーストラリア・ニュージーランドが争った事件(ミナミマグロ事件)では、豪州・NZ側は我が国を国連海洋法裁判所に提訴したが(豪州・NZ側は結局敗訴した)、その結果、この問題を巡っては、我が国のマグロ漁を批判する環境保護団体等のNGOは排除され、彼らによるセンセーショナルかつエモーショナルな反日キャンペーンが説得力を失って、我が国にとってはかえって良好な環境(落ち着いた雰囲気の中で、ANZ両国との友好関係を損ねることのないかたち)で交渉が出来、好都合であったという。
6:故に、我が国刑事訴訟法第335条・民事訴訟法第191条は、判決文に「認定された具体的事実」「適用された法規範」を記載することが要求されている。
(:田中『法理学講義』、307ページ。)
もっとも、こうした「法的三段論法」は、その正当化理由を実定法規範に依存するため、柔軟性に乏しく、個別的正義を抑圧する危険性もある。ただ、だからといって、直ちに裁判所に政策形成機能や「民主化」の役割を負わせるのは短絡的な解決方法であろう。
7:六本前掲書、349ページ・350〜351ページ。田中前掲書、307ページ〜。また、
市川正人・酒巻 匡・山本和彦 『現代の裁判』 有斐閣アルマ、1998年 11〜12ページ。
但し、既に冒頭の定義でも明らかなように、裁判は必ずしも法律問題だけを扱うのではなくて、事実認定という形で事実上の問題にも踏み込んで判断を下す(その際、事実関係が法的判断に斟酌される)。また、判決が執行されると、それは単に観念的な権利義務関係の変動だけでなく、それが強制執行されることによって「事実の世界」にも影響を及ぼすのであり、その意味で裁判所の営みは事実問題をまったく捨象しているのではない。しかしながら、事実認定はあくまで法的権利義務関係を確定する前提として行われるものであり、それに関係しない事実には裁判所が「目をつぶる」ことがある。
▲2、司法裁判の限界
だから、裁判所(法的思考)というのは、世の中の森羅万象、あらゆる問題(difference)を処理することが出来る万能の技法ではない。
例えば、「公害をどう法的に規制するか」「軍事力をどれだけ整備するか」といった将来に向けた抽象的な問題は、民主的な基盤を持つ国会が担当すべき立法政策上の問題であり、裁判所よりも国会が扱うべき問題である(※注1)。裁判官の職務は「法の発見」「法を語ること」であり、民意の集約や「法を創る」ことではないからである。裁判官は、国会議員と異なり選挙で選出されたわけではない以上民主的基盤が弱いが、そうした民主的基盤をほとんど持たない者が国会と同様の立法行為(規範の定立)を行うことは、「司法立法」として許されない(※注2)。
また、政治的・社会的・宗教的側面しかない紛争を捉えて処理することもできない。例えば、ある宗教団体において、その宗教の教義上どの本尊が正当か、といった紛争には、裁判所は関与できない(※注3)。これについて我が国
最高裁判所
は当初、「宗教上の教義を巡る紛争が含まれていても法的側面については判断する」という態度を示していたが(種徳寺事件、最判昭和55年1月11日。本門寺事件、最判昭和55年4月10日)、その後、そうした紛争はそもそも裁判所の審査の対象外であるとの態度をとるようになった(創価学会板まんだら事件、最判昭和56年4月7日)。また、
憲法第9条
と
日米安保条約
・
自衛隊法
の関係について、
最高裁判所
がいわゆる「統治行為論」を展開し、
日米安保条約
の合憲性について、「一見極めて明白に違憲無効であると認められない限りは、裁判所の司法審査権の範囲外にある」(砂川事件)としたのは、この紛争があまりにも大きな政治的側面を持っており、司法的手段だけでは問題を処理し難い、と判断したからに他ならない(※注4)。
更に、例えそれが過去に起きた、法的側面を有する紛争であったとしても、法的三段論法(判断代置方式)を用いることが出来ないものについては、裁判所の判断は及ばない。還元すれば、法律上の要件が明確でなく、司法や行政に自由裁量権があるが故に、実定法によってその裁量行為の違法・合法の判断を正当化し得ないものは、原則として「リーガルマインド」では解決することが出来ないのである(※注5)。例えば、原子力発電所の立地条件については、(原子力安全委員会等による手続上の規制はあるにしても)原則として立地そのものに法律上規制があるわけではないから、行政が適切な場所を選んで自由に設置(を許可)出来る。この時、例え周辺住民が「原発は嫌だ」といって裁判所に提訴しても、そもそもその立地について規制する大前提(実定法)が無ければ法的三段論法を行うことができず、違法・合法の判断が出来ない(※注6)。
無論、今日の裁判所には、複雑化した社会に対応して一定の政策形成機能が求められているし、また裁判官の法的三段論法の中には一定の法創造が含まれることは事実であるが、それらは裁判固有の機能ではない。実際に、我が国の裁判所はこうした問題を取り扱わない(
裁判所法第3条①
)(※注7)。当事者が多数に及び争点等を限定し難い場合(大規模訴訟)は、例外的扱いがなされて当事者・争点の限定化が行われる(民事訴訟法第268条・第269条)。
※注釈
1:田中『転換期の日本法』、240ページ。
これについてアリストテレスは、将来(未来)へ向けて行う「議会弁論」と過去へ向けて行う「法廷弁論」を区別し、現在へ向けて行う「演説弁論」とともに3種類に区分した。
| 種 類 | 時間 | 形式 | 目 的 | 対 象 |
| 議会弁論 (審議的弁論) | 未来 | 勧奨 ・ 制止 | 利益・損害 | 判定者 |
| 演説弁論 (演示的弁論) | 現在 | 称賛 ・ 非難 | 美・醜 名誉・不名誉 | 一般人 |
| 法廷弁論 | 過去 | 告訴 ・ 弁護 | 正・不正 | 判定者 |
(:アリストテレス 『弁論術』 岩波文庫、1992年)
2:市川他前掲書、12〜14ページ。
近代以前の裁判官は、法を適用する者であるのと同時に法を創造するものでもあったが、こうした法創造を裁判官の個性に委ねる方法は、モンテスキューの三権分立主義の登場によって否定され、裁判官は「法を語る」に過ぎないものとされた。
もっとも、法的三段論法をする際に、裁判官は「法解釈」と称して一種の「法創造」を行っているのであり、かならずしも裁判官が一切の法創造を禁じられているわけではない。実際、法律の世界にとって裁判官の法解釈、即ち「判例」の意義は大きいし、また裁判官は、その紛争について処理する実定法が存在しないとき(これを「法の欠缺」という)も、「条理(naturalis ratio)」「法の一般原則」あるいは「衡平と善」を考慮して判決を下さなければならない。
(:小島武司編 『裁判キーワード』新版補訂版 有斐閣、2000年 18〜19ページ。)
(:この問題についての詳細は、拙稿「
判例とは何か
」『月刊「健章旗』1999年6月号を参照のこと。)
3:小島前掲書、6〜7ページ。
4:その意味では、「板まんだら事件」と「砂川事件」における裁判所の判断回避は、(憲法学では異なるように説明されているが)本質的に同じ理由によるとも言える。
なお、「砂川事件」及びその憲法上の問題については、月刊「健章旗」
1998年8月増刊号の記事
を参照のこと。
5:この問題は、特に行政法学の分野において、「行政裁量論」として議論されている。
(:塩野 宏 『行政法Ⅰ』 有斐閣)
6:もっとも、その際行政に裁量権の濫用があったり、都市計画法や環境影響評価法に抵触する部分があった場合には、当然、その限度で違法・合法の判断を下すことは出来る。また、最近の裁判所は、こうした裁量行為についても、「適正な手続が踏まれたかどうか(例えば、伊方原発訴訟のように、原子力発電所の設置許可を巡る国の原子力委員会の審査に瑕疵が無かったか)」という観点から判断を下すようになっている(法律上、「適正な手続を踏むべきだ」ということになっていれば、それを手掛かりにして法的三段論法を用いることが出来るから)。
7:「裁判所は、日本国憲法に特別の定のある場合を除いて一切の法律上の争訟を裁判し、その他法律において特に定める権限を有する。」
もっとも、だからといって裁判所の扱っている事件全てが「訴訟事件」であるわけではなく、一部には「非訟事件」と呼ばれるものもある。「非訟事件」とは、①過去に発生した具体的紛争を前提としないもの(不在者の財産管理、後見人の選任等)や、②具体的紛争を前提としつつも、法規範の規定が一義的でないがために法的三段論法を適用できず、裁判所に大幅な司法裁量が許されているもの(離婚に伴う財産分与、扶養、遺産分割等)のことであり、その本質は司法裁判というよりも裁判所による行政作用である。その他、最高裁判所による規則制定権や人事権の行使も、憲法上例外的に認められた司法立法権、司法行政権の行使であって、裁判ではない。
(:上原敏夫・池田辰夫・山本和彦 『民事訴訟法』(第2版補訂) 有斐閣Sシリーズ、2000年 15〜17ページ。
田中『法理学講義』、338ページ〜。六本前掲書、350ページ。)
▲3、裁判以外の紛争処理手段
そこで、こうして社会構成員間の紛争を処理する手段として、司法裁判の限界を補うその他の手段が存在している(※注1)。例えば、ある紛争を最も包括的かつ最終的に処理し得る手段とは、その紛争を生じた関係を断つこと=紛争の回避(avoidance)である。図1は紛争の展開を表わしたものであるが、この図からもわかるように、そもそも多くの(広義の)紛争が、「(狭義の)紛争」状態に至る前に脱落(attrition)しており、最終的に侵害及びその原因主体が特定されて対立が顕在化しても、相手方からの反対要求(counter claiming)を受けて、(紛争継続の費用を考え)紛争を回避・終結させてしまう場合もある(※注2)。しかし、一般に、我々が紛争を生じさせるような相手と人間関係を完全に遮断することは不可能であるし、それは一方的な解決策に過ぎない。また、こうした処理策は、侵害の緊急性・重大性が小さく、あるいは紛争継続の費用を考え紛争終結のほうが有利である場合に限られるのであって、侵害が重大である場合や強い敵対感情が醸成されてしまった場合は、回避は出来なくなる。例えば、死亡轢き逃げ事故を起こしたドライバーは、被害者を現場に放置することによって紛争に巻き込まれるのを避けようとするが、これは被害者側にとっては全く選択不可能な処理手段である。
※図1 紛争の展開
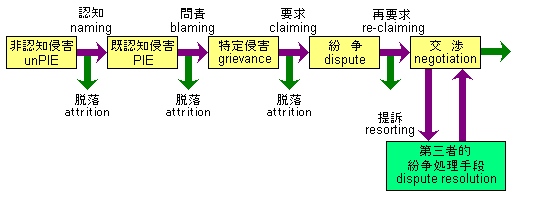
| 段 階 | 内 容 |
| 非認知侵害 UnPerceived Injurious Experience(unPIE) | 客観的には侵害が生じているが、被害者の主観にはそれが登場していない状態 →侵害を主観的に認識していない |
| 既認知侵害 Perceived Injurious Experience(PIE) | 侵害行為を認知(naming)しているが、原因主体が特定・認識されていない状態 →自己以外に責任の所在を見出していない、情報の欠如、緊急性・重大性が無い |
| 特定侵害 grievance | 問責(blaming)によって侵害行為及びその原因主体が特定された状態 →要求以外の方法で侵害を除去・中和、情報の欠如、緊急性・重大性が無い |
| 紛 争 dispute | 相手方に対して侵害の事実を知らせ、救済を要求(claiming)して対立が顕在化した状態 |
| 交 渉 negotiation | 要求(claiming)に対する反対要求(counter claiming)も行われて、紛争解決を働きかける状態 |
そこで、一般的には、まずは紛争それ自体を「事実上の問題」として処理する事実上(政治上)の処理が行われる。その典型例が、紛争当事者間による直接の交渉である。両者が紛争の存在を前提として受け入れる以上は、この交渉こそが最も基本的かつ包括的な紛争処理手段であり、両者は互譲による妥協によって、問題解決を図っていく(※注3)。多数決によるいわゆる政治的決着や、武力(軍事力)を使った暴力的決着(暴力団の介入、戦争、報復措置)(※注4)も、このカテゴリーに含まれる。実際、法的側面を全く有しない紛争(例えば、軍拡によって双方の軍事力が脅威となり、軍事的緊張関係それ自体が紛争<difference>となる場合や、愛猫家と愛犬家の「犬と猫とのペットとしての価値」を巡る紛争)の場合は、政治的手段によってこれを処理する他ない。もっとも、そうした妥協は、当事者間の合意によって成立するという意味で包括的かつ安定的であるが、他方で両者の交渉力の差が大きいときは、不公平な結果を招きかねない(※注5)。
他方、司法裁判と同じような「法的思考」を用いた第三者的紛争処理手段には、他にも(A)仲裁、審判その他の裁判的手続、及び(B)調停、周旋、仲介、審査その他の非裁判的手続がある。これら(A)(B)に該当するものを「ADR」(Alternative Dispute Resolution、代替的紛争処理手段)と呼ぶが(※注6)、厳格に言えば、(B)は「法的枠組み」ではなく、法的な判断と事実(政治)的な判断が混じった原始的なものではある。しかし、調停に代表される中間的な紛争処理手続は、①法的側面以外の争点も直接扱うことが出来、実定法や判例(先例)に拘束されないので、個別的正義を十分に斟酌した、実情に即した解決をはかることが出来る、②最終的に当事者同士の合意に達すれば、その結果は守られやすい、③法的側面が少ない(薄い)分、法律専門家でなくてもわかりやすい、④費用と時間を節約できる(また、裁判所を多く設置する必要が無くなる)、⑤当事者同士の交渉よりも円滑に進む、といった面で裁判よりも優れている面がある(※注7)。
※図2 紛争処理と「法的枠組み」
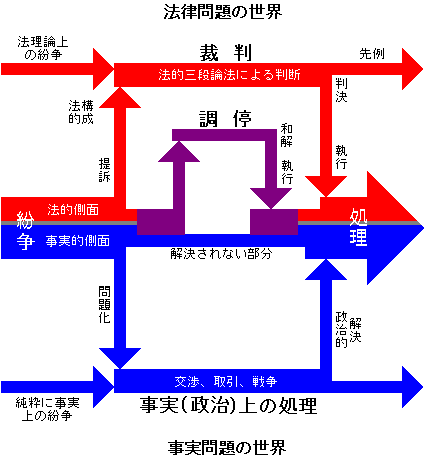
※表1 各種の平和的紛争処理手段
| 大区分 | 小区分 | 第三者 の関与 | 内 容 | 利 点 | 欠 点 | 実 例 |
| 法的 処理 手段 | 司法 裁判 | 判断者 として | 予め選任された裁判官によ る法的裁定 (judicial settlement) | 当事者の合意不要 実定法で正当化 第三者関与による透明化 | 法的側面のみ解決 時間・費用がかかる 先例拘束性あり 個別的正義を圧迫 | 国内裁判所 国際司法裁判所 国際海洋法裁判所 |
| 仲裁 裁判 | 判断者 として | 当事者がその場で選任した 裁判官による法的裁定 (arbitration) | 国際商事仲裁 国際スポーツ仲裁裁 仲裁契約(国内法※) | |||
| 準法的 処理 手続 | 調停 | 助言者 として | 調停人が客観的・中立的 立場で事実認定・法的判断 (conciliatiion) | 法的側面・事実的側面を 包括的に処理可能 (違法性だけでなく 不当性も判断可能) 先例拘束性なし 個別的正義も尊重(衡平) 時間・費用がかからず 第三者関与による透明化 | 当事者の合意が原則 却って司法裁判の制 度拡充・法化の障害 (処理の不透明性) | 家事審判、海難審判 公害等調整委員会 日蘭紛争処理条約 |
| 審査 | 助言者 として | 調停人が客観的・中立的 立場で事実認定を行う (inquiry) | 民事調停 家事調停 住民監査請求 | |||
| 仲介 | 助言者 として | 調停人が事実上の処理策 を提示する (mediation) | 中東和平交渉 古典的仲裁 喧嘩の仲裁 | |||
| 周旋 (斡旋) | 助言者 として | 調停人が当事者間の交渉 の便宜を図る (good offices) | 日露講和会議 労働委員会 弁護士会の法律相談 | |||
| 事実上 の 処理 | 交渉 | なし | 当事者間で紛争を包括的 に事実上処理するための 対話を行う(negotiation) | 紛争を包括的に処理 先例拘束性なし 時間・費用がかからず | 当事者の合意が原則 なかなか処理出来ず 必ずしも衡平でない | 日米首脳会談 日米構造協議 |
※=公示催告及ビ仲裁手続ニ関スル法律(明治23年法律第29号)
※注釈
1:市川他前掲書、6ページ。
2:市川他前掲書、6ページ。
また、和田安弘 『法と紛争の社会学』 社会思想社、1994年 102ページ以下。
それが純粋に経済的な問題であれば、「保険」によってリスクを回避することも出来る。
3:市川他前掲書、7ページ。
4:「不戦条約」、「日本国憲法」第9条がいう「国際紛争解決の手段としての戦争」とは、正にこの(A)の処理方法(政治的処理)において、戦争という手段を選択しない、ということである。蛇足ながら、故に国際法の強制執行を行う国際警察軍のような組織<図の「裁判の執行」の部分に該当>は、「国際紛争解決手段としての武力行使」をするわけではないから、我が国自衛隊も当然参加できるものと考えるべきであろう。
5:『社会学概論』、413ページ。また、和田前掲書、102ページ。
和田前掲書によれば、人々が力ではなく準則(法)による処理を選択するには、適切な環境が準備されていなければならない、という。
6:『民事訴訟法』、7ページ。六本前掲書、365ページ。市川他前掲書、8ページ。
7:六本前掲書、365ページ。表1参照。
国連憲章第6章に定められた「国際紛争の平和的処理」の規定もADRの一つである。
▲4、司法裁判のアイデンティティ
では、司法裁判(及び仲裁)とそれ以外(ADR)の違いは何であろうか。
端的に言えば、それは「司法裁判」が当事者に加えて「公平な第三者」としての裁判官を加えた「三者関係」(triad)で行われ、裁判官が「裁定」(adjudication)(当事者の同意を得る事無く、第三者が判断を下し拘束する問題解決方法)を下して問題の法的側面だけを解決する「判決」を下している点にある(※注1)。無論、裁判官の具体的な役割については、英米法の当事者主義と大陸法の職権主義との間で差はあるが、いずれの立場にせよ裁判官が「公平な第三者」として登場してくることにかわりは無い。また、一方の侵害行為による主観的な損害の填補策として市民間で適用される「民事訴訟」と、客観的な法規範違反そのものを問う「刑事訴訟」の違いもあるが、いずれの裁判でも三者関係に変わりは無い。
これに対して調停や周旋では、参加する調停人や調停委員は一応第三者ではあるが、彼の提示する紛争処理策には強制力は無く、当事者同士がそれを受諾しなければ、調停案は成立しない。ここにおける第三者の役割は、当事者同士の議論の交通整理をし、その透明性と信頼性を高め、当事者同士の自主的紛争処理を助長するというものである(※注2)。
つまり、「公平な第三者として当事者を拘束する裁定を下す」ことこそが「(司法)裁判」と「ADR」を分別する、従って「司法機関としてのアイデンティティ」となり得るものなのである。
※注釈
1:田中『法理学講義』、327ページ。六本前掲書、346ページ・366ページ。市川他前掲書、7ページ。
2:図1及び図2参照。
▲5、司法裁判の不完全性(断片性)
ここで注意すべきなのは、上記(A)〜(C)及び「司法裁判」という紛争処理方法は、再三述べているように、いずれも紛争の法的側面のみを解決するものであり、紛争の「処理(settlement乃至management)」方法に過ぎないのであって、紛争それ自体を円満に「解決(resolution)」する方法ではない、ということである(※注1)。
例えば、ある夫婦の不倫問題を考えてみよう。夫の不倫に嫌気が差した妻は、親元に戻る等として別居生活を送ることによって、事実上の婚姻関係を断ち切ることは出来る。また、妻が経済的に独立していれば、そうした事実上の離婚関係を長く継続させることが出来るかもしれない(もっとも、独立していない場合は、収入のある夫が妻の生活費を支払わなければならない。この法律上の義務を生活保持義務という)。しかし、それも、夫側が不倫について謝罪したり、あるいは不倫関係を止めるといった対応をしない限り、事実上の処理策の一つに過ぎない。また、妻が夫と法的離婚を決意して手続を踏み、更に夫とその不倫相手に不法行為責任を追及すれば、裁判所はそれを認めて夫に対し離婚及び損害賠償を命じるであろう。しかし、ここで妻が得られたのは、損害賠償で得たいくばくかの金銭と法的な離婚状態、それに「法的には自分が勝利した」とする満足感に過ぎないのであり、本来あるべき円満な夫婦生活を取り戻せたわけでも、夫の愛情を回復させたわけでもない。結婚生活が破綻していれば、裁判所にそれを認定させて判決離婚をすることが出来るが、裁判所に「愛情回復判決」を出させるわけにはいかない。裁判所は、この問題の「法的側面」という一部分に対する法的な=観念的な回答を与えただけであり、それは必然的に断片的・部分的なものにならざるを得ないのである。
故に、ある紛争について法的側面が大きければ大きいほど法的処理の有効性は増し、逆に政治的側面が大きければ大きい程、法的手段が処理策として効力を減じることになる(※表2参照)。そればかりか、場合によってはそうした紛争を無理に法的に処理しようとして、かえって紛争を一層激化させることすらある(裁判の逆機能、悪しきリーガリズム)(※注2)。例えば、上記の設例で、夫が自らの行為を反省して謝罪しようとしたところ、妻が弁護士に依頼して損害賠償訴訟を提起してきたら、どうであろうか。恐らく、夫に芽生えた謝罪の気持ちは歪み、却って問題を激化・複雑化させるのではないだろうか。実際に、1978年8月の三重県「隣人訴訟」事件(津地判昭和58年2月25日判例時報1083号125頁)では、弁護士による不用意な民事訴訟提起の勧奨が却って紛争を劇化させてしまっている(※注3)。この事件は、知り合いで近所に住む子供が自宅に遊びにきたところ、誤って隣接する溜池に転落・溺死してしまい、溺死した子供の親が遊びに来られた側(隣人)と国・三重県(公物である溜池の管理者)に対して損害賠償を請求したもので、一審の津地方裁判所は「遊びに来られた側(隣人)に注意義務がある」として500万円あまりの損害賠償を認めた。しかし、これに対して新聞等の報道機関が「隣人の好意に辛い裁き」等と書き立てた為、この事件を訴訟で処理しようとした原告に嫌がらせや脅迫まがいの非難が集中し、結果訴訟を取下げざるを得なくなってしまったのである(※注4)。
※表2 各種の紛争とその処理手段
| 種 類 | 図式的表現 | 実例 |
| (A)法的側面の大きい紛争 (司法裁判になじむ) | 法解釈上の紛争 契約上の紛争 有価証券に関する紛争 | |
| (B)法的側面・事実的側面 共に存在する紛争 (裁判・調停・交渉になじむ) | 普通の紛争 | |
| (C)事実的側面の大きい紛争 (事実的処理になじむ) | 国際紛争・武力紛争(戦争)、「政治問題の法理」 宗教的紛争(板まんだら事件) 政治的紛争(経済政策のあり方等) |
こうした傾向は、国際紛争の司法的解決の場面において更に顕著である。というのも、国際社会において、その紛争の法的側面に対し法的回答を与えるのは国際司法裁判所(その他、国際海洋法裁判所<ITLOS>や常設仲裁裁判所といった機構も存在している)であるが、その国際司法裁判所は、紛争当事国の紛争の付託合意(コンプロミー、compromis)が無ければその事件についてそもそも判断をすることさえ出来ず(紛争を扱う権限=管轄権が無い)、また例え管轄権があったとしても、その判決の履行を強制する手段を持たない(例外的に、その事件が国際の平和と安全の維持にとって脅威となるときは、国連安全保障理事会が国連憲章第94条に基づいて強制措置を発動し得る場合もあるが、実際には常任理事国の拒否権の壁もあって一度も発動されたことはない)。ひどい場合には、アイスランド漁業管轄権事件(判例国際法83事件)や北海大陸棚事件(判例国際法37事件)(※注5)の国際司法裁判所判決のように、紛争当事国に「誠実な再交渉を命じる判決」を出すこともある。これは、上に挙げた不倫問題のケースで、妻が家庭裁判所に離婚調停・審判を求めれば、家庭裁判所はそれを必ず受理して夫を法廷に呼び出し、最終的に判決が確定すれば、その履行を強制することが出来る国内司法制度と大きく異なるものである。つまり、国際社会においては、「法」の果たす役割が相対化されているのであり、国際司法裁判所が与える法的な回答には損害賠償すら含まれず(敗訴した国が任意に支払えば別だが、拒絶した場合に国際司法裁判所が履行を強制することは出来ない)、観念的な「法的な満足」を得るだけなのである(※注6)(※注7)(※注8)。
※注釈
1:六本前掲書、351ページ・366ページ。田中『転換期の日本法』、240ページ。『社会学概論』、413〜414ページ。
裁判所法第3条①は、「裁判所は、日本国憲法に特別の定のある場合を除いて一切の法律上の争訟を裁判し、その他法律において特に定める権限を有する。」としており、「法律上の争訟」でないものについては判断をしない。
「法律上の争訟でない」として判断を回避したものとして、前述した「創価学会板まんだら事件」が有名である。
2:これを「法的紛争処理の逆機能」という。
(:『社会学概論』、409ページ。)
3:市川他前掲書、228ページ。小島前掲書、31〜32ページ。小島『現代裁判法』、20ページ。
4:こうした事態に対し法務省は、「裁判を受ける権利の侵害」の疑いがあるとして異例の見解表明を行ったという。
5:田畑茂二郎・竹本正幸・松井芳郎 『判例国際法』 東信堂、2000年の事件番号による。
6:国際社会において法的紛争処理手続が相対化されているのは、基本的に国際社会が独立主権国家によって構成され、国際法や裁判所も又その独立主権国家の合意によって成立しているという事情があるが、更に言えば、国際紛争は国内紛争と比較して一層複雑であり、上記の如き「法的満足感」が得難いという側面もあろう。
7:逆にいえば、国際紛争の軍事的手段による解決も又、問題の軍事的側面にだけ回答を与えるという点では、法的処理と同様の不十分性をもっている。例えば、第2次国連ソマリア活動(UNOSOMⅡ)において、米軍を主体とする「平和執行部隊」は、国連安保理から武力行使の授権を受け、武装解除に応じないアイディード将軍派に対して軍事的攻勢をかけたが、それは失敗し、純軍事的手段を用いてのソマリア内戦解決は失敗した。
8:このように、国際法の世界においては、国際司法裁判所の判決は強制履行されることがない。そこで、国際法においては、「そもそも国際法は『法』か」という議論すら存在している。これは結局のところ、「リーガルマインドによる紛争処理」にどの程度の実効性を要求するのかにかかっている。否定論者は、国際法は強制執行が出来ない以上法ではない、つまり、国際法は法的紛争処理システムとしては有効性が低いことを根拠にしているが、紛争処理システムの有効性と強制執行制度の有無は必ずしも一致しない。現に、世界各国はこれまで日常的にはよく国際法を守ってきており、国際司法裁判所の判決が最終的には当事国間の紛争処理に役だった例も多い。逆に、国内法においても、いくら強制履行をしたとしても、表2の類型(C)のように、紛争の法的側面が政治的側面より遥かに小さければ、紛争はほとんど解決しないことになる(「統治行為論」「隣人訴訟」がそのよい例)。以上より、「国際法はやはり法である」(正確に表現すると「国際法は法だから法である」という奇妙な循環論法になる)ということが出来よう。
▲6、法的紛争処理システムの存在意義
では、なぜ法的紛争処理は不完全でありながら、今日最も重要な紛争処理手段として存在しているのであろうか。
一つの理由は、前述したように「法」には「正義」の要素が含まれるため、法的に勝利した者はあたかも自らの主張が「正義」であると認定されたかのように感じ、それに満足して紛争状態の終結に同意するからである(※注1)。しかも、ここで認定された「正義」とは、単なる当事者個人にとっての「正義」(主観的正義、即ち「権利」)ではなく、公的・社会的な観点から見ても適正である、という客観的正義(即ち「法」)なのである(※注2)。事実、我々は日常生活において、「法的に勝利した」という事実を以って、その紛争を一件落着とすることが多い。特に、国内法においては、裁判所の判決は国家機関を以って強制され、必ず判決の示した法的状態が作り出される。つまり、国内法の世界においては、「正義は勝つ」という命題が比較的素直に成立し得るのであり、それだけに法的処理の実効性は高いわけである。新聞用語でも、よく「法的手段に訴える」「法的決着がついていない」等と書かれることがあるが、これも法的処理手段の権威の高さを示したものであろう(※注3)。
また、裁判の手続そのものが、当事者にとっての一つの「説得力」になっていることも重要である。即ち、司法裁判は、あらゆる紛争処理手続の中で最も厳格な手順を踏んで判断を下しており、原告・被告双方の「言い分」を十分聞いて行われるが、そうして「言い分を聞いたこと」が、当事者をして十分な満足となる場合が多々あるのである(従って、そこでは、後述するように裁判官の中立性が極めて重要になってくる)。例えば、ある消費者が不良品による事故の損害賠償を求めるべく大企業の「お客様相談窓口」に苦情を申し出ても、企業側が相談に応じなければ問題解決には至らないが、消費者がこれを裁判に持ち込めば、「被告」「原告」という平等な形で審理が行なわれ、どんな相手(国や大企業)であっても対等な「話し合いのテーブル」に立たせることができる。英米における法の諺に「相手側からも聴くべし」「双方に耳を貸す(audi et alteram partem)」というものがあるが、この諺は正にこの「手続的正義」の重要性を示唆しているといえよう(※注4)。
更に、国際社会においても、国際司法裁判所の判決は、なるほどその履行を権力的に強制することは出来ないという意味で非力ではあるが、それはしばしば「錦の御旗」「水戸黄門の印籠」として機能し、結果として当事国間の交渉を促進する効果を有している(※注5)。例えば、上に述べたアイスランド漁業管轄権事件(判例国際法83事件)や北海大陸棚事件(判例国際法37事件)においては、結局のところ当事国間の交渉で問題解決が図られており、国際司法裁判所の「目論見」は十分機能したのである。事実、1960年代以降に我が国で発生した一連の「現代型訴訟」(公害訴訟、薬害訴訟、嫌煙権訴訟等)では、原告(被害者)側は判決を得ることすら目的とせず、単に裁判所に提訴して被告を強制的に「御白州」に引き出し、社会的な注意喚起を行い、自己の主張を十分述べることそのものが目的となっているものが多い。つまり、こうした事例では、裁判自体は和解か敗訴で終わっても、結果として原告側の目的を達成し、紛争が処理されることになるのである(※注6)。
冒頭で、「リーガルマインド」とは、・・・・・(紛争を)解決する手段であると定義したが、これは、正確には、「紛争の法的側面を観念的に解決することによって当事者間の紛争処理を促進すること」(※注7)、乃至は「法的側面を観念的に解決してあたかも生の紛争そのものが解決したように見せかけ、紛争当事者を納得させること」、と定義付けられるのではないだろうか(※注8)(※注9)。その意味では、実は司法裁判もまた畢竟、調停や周旋と同様に当事者同士の紛争処理を促進・助長する補助的手段に過ぎないのである(※注10)。
※注釈
1:六本前掲書、368ページ。
2:フランス語で「法」は「客観的権利(droit objectif)」と表現され、「権利」とは「主観的権利(droit subjectif)」と表現される。そしてまた、「権利」とはフランス語で「正義」と同義である。即ち、「法」とは「客観的正義」であり、「権利」とは「主観的正義」である。
3:六本前掲書、349ページ・351ページ。
社会学者のニクラス・ルーマンは、裁判の「正当性」を、「敗訴した当事者がもはやいかなる抗弁も許されず社会的に孤立すること」と理解している。
4:和田前掲書、166ページ・199ページ。
和田前掲書によれば、交渉が妥結するのは①準則的(法的)な考慮が働く場合と②打算的(現実的)考慮が働く場合の2種類があるが、前者は、そうした考慮が保障されるような状況下では、ある程度自動的に合意が成立するという。
5:逆にいえば、国内裁判所も、判決の履行を権力的に強制できるからといって、国際司法裁判所よりも強力な紛争処理機関であるとは当然には言えない。何故ならば、前述したように、国内裁判所といえども結局はその紛争を断片的に処理しているに過ぎないからであり、その点では国際法廷も国内法廷も同じだからである。
6:田中成明 『法の考え方と用い方』 大蔵省印刷局、1990年 279ページ〜・293ページ〜。小島『現代裁判法』、40ページ。また、図1参照。
例えば、国鉄車両の全面禁煙化を主張した嫌煙権訴訟(東京地裁昭和62年3月27日付判決)では、原告側は敗訴した一審で控訴せず、訴えを取下げているものの、裁判では散々「嫌煙権は認められない」等と主張していた国鉄は、その言葉とは裏腹に、実際にはその訴訟以降禁煙車両を増やして行った。また、新幹線運賃払戻請求事件(東京地裁昭和53年11月30日判決)では、「新幹線の運賃を(新幹線とは別ルートを走る)在来線の実測キロに基づいて算出するのは運賃法第3条に反する」として200円の不当利得返還を訴えた1人の原告の主張を裁判所が認め、これを受けて国会が運賃法の改正を行なったという。
7:田中『法の考え方と用い方』、279ページ〜。
最近の民事訴訟法改正により、新たに「弁論兼和解」という制度が法定化された。これは、法廷で審理を行う前に、法廷とは別の小部屋で当事者及び裁判官が集まり、実質的な討論や争点の絞りこみを行い、併せて和解(裁判上の和解)を試みるというものである。ここでは、正に「裁判」が「和解」を促進するための材料として働いており、両者が融合した形となっている。
(:『民事訴訟法』、125ページ。)
8:無論、こうした処理方法で全てが「解決」というわけではなく、そこから外れたところに真の被害者がいることも多い。また、こうした法律学の教義学的性格は、しばしば批判されるところである。
9:だからこそ、表2の類型(C)のような紛争は、法的処理にはなじまない。何故ならば、そうした紛争は法的に解決できる法的側面があまりにも少ないので、上述した「あたかも紛争そのものが解決したかのように処理すること」が出来ないからである。
10:和田前掲書、106ページ。また、
中坊公平 『日本人の法と正義』 日本放送協会、2001年 48〜49ページ。
何故ならば、紛争とは究極的には両当事者間のものであり、第三者によってその処理を完結することは不可能だからである。
そのことは、図1及び図2を見ればよくわかる。
中坊氏は、自身が体験した「森永ヒ素ミルク事件」において、「裁判に勝つことではなく、被害者の救済こそが目的である」と感じるようになったという。
※参考文献
芦部信喜 『憲法』新版 岩波書店、1997年
アリストテレス 『弁論術』 岩波文庫、1992年
市川正人・酒巻 匡・山本和彦 『現代の裁判』 有斐閣アルマ、1998年
今田高俊・友枝敏雄編 『社会学の基礎』 有斐閣Sシリーズ、1991年
上原敏夫・池田辰夫・山本和彦 『民事訴訟法』(第2版補訂) 有斐閣Sシリーズ、2000年
エドワード・ハレット・カー 『危機の二十年』 岩波文庫
大木雅夫 『比較法講義』 東京大学出版会、1992年
大木雅夫 『日本人の法観念』 東京大学出版会、1983年
大沢秀介 『憲法入門』 成文堂、1998年
大橋智之輔他編 『法哲学綱要』 青林書院、1990年
奥平康弘 「寺西判事補分限裁判決定をめぐって」『法律時報』72巻2号 1999年
川岸令和 「裁判官と表現の自由ーアメリカの経験を通して考える」『ジュリスト』1150号(1999年2月15日号) 有斐閣
川島武宜 『日本人の法意識』 岩波新書、1967年
喜田村洋一 「制定過程・類例から見た『裁判官の政治運動』」『ジュリスト』1150号(1999年2月15日号) 有斐閣
工藤達朗 「ドイツにおける裁判官の政治活動の自由」『ジュリスト』1150号(1999年2月15日号) 有斐閣
栗林忠夫 『現代国際法』 慶應義塾大学出版会、1999年
小島武司編 『裁判キーワード』新版補訂版 有斐閣、2000年
小島武司編 『現代裁判法』 三嶺書房、1987年
斉藤秀夫 『裁判官論』(改訂三版) 一粒社、1985年
佐藤幸治 『憲法』 青林書院
塩野 宏 『行政法Ⅰ』 有斐閣
竹下 賢・角田猛之編著 『マルチ・リーガル・カルチャー』 晃洋書房、1998年
田中成明 『転換期の日本法』 岩波書店、2000年
田中成明 『法理学講義』 有斐閣、1994年
田中成明 『法的思考とはどのようなものか』 有斐閣、1989年
田中成明 『法の考え方と用い方』 大蔵省印刷局、1990年
田中成明、竹下 賢、深田三徳、亀本 洋、平野仁彦 『法思想史』 有斐閣Sシリーズ、1988年
田畑茂二郎・竹本正幸・松井芳郎 『判例国際法』 東信堂、2000年
長尾龍一 『憲法問題入門』 ちくま新書、1997年
中坊公平 『日本人の法と正義』 日本放送協会、2001年
日弁連法務研究財団 『次世代法曹教育』 商事法務研究会、2000年
日本経済新聞社編 『司法 経済は問う』 日本経済新聞社、2000年
本間康平・田野崎昭夫・光吉利之・塩原 勉編 『社会学概論』新版 有斐閣大学双書、1988年
宮澤節生 「法科大学院論議の活性化と透明性のためにー再論」 法政策研究会『法政策学の試み・2』 信山社、2000年
棟居快行 「裁判官の独立と市民的自由」『ジュリスト』1150号(1999年2月15日号) 有斐閣
本 秀紀 「裁判官の政治運動」『憲法判例百選Ⅱ(第4版)』(「ジュリスト」別冊) 有斐閣、2000年
森 征一・岩谷十郎編『法と正義のイコノロジー』 慶應義塾大学出版会、1997年
山田 晟 『法学』新版 東京大学出版会、1964年
山本草ニ 『国際法』新版 有斐閣、1994年
六本佳平 『法社会学』 有斐閣、1986年
我妻 栄他 『新法律学辞典』新版 有斐閣、1967年
和田安弘 『法と紛争の社会学』 社会思想社、1994年
「
伊藤真の司法試験塾
」ホームページ
「
日本裁判官ネットワーク
」ホームページ
「毎日新聞」ホームページ
「産経新聞」ホームページ