北ボルネオ会社 南アフリカ会社 モザンビーク会社&ニアサ会社 フェロナルディ会社&ベナディール会社 スエズ運河地帯 王立グリーンランド貿易会社 ヤルート会社 太平洋諸島会社 鉄道附属地 天津ベルギー株式租界 中国新建集団公司 いつの頃からか、「民営化」というのが世界的にすっかり流行ってますね。日本でも試験問題で必ず出てきた「三公社五現業」なんて言葉は、すっかり死語になりました(ちなみに、三公社とは電電公社、専売公社、交通公社・・・ではないですよ。テストでそう書いて×をもらう奴がたくさんいたけど)。
「いっそのこと、政府を丸ごと民営化しちゃったら、いいんじゃない?」なんて言う人がいるかも知れませんが、いくらなんでもそこまではないでしょう。政府なら福祉とか教育とか金にならない事業もやらなきゃならないし、住民だって民間企業の裁判官に裁かれたり、民間企業のお巡りさんに捕まったりするのはイヤですもん。。。。
しかし過去には「会社統治領」が世界のあちこちに存在していました。もっとも主権はあくまで国家に属していて、会社が統治を委任されるというもので、かつては植民地支配にあたって、この方法がよく採られていました。植民地統治なら住民のための福祉なんてことはなく、ひたすら利益を上げるために収奪してくれれば良いというわけですね。
有名なところではイギリス東インド会社(1600〜1858)やフランス東インド会社(1664〜1769)よるインド支配や、オランダ東インド会社(1602〜1799)による東インド諸島(現在のインドネシア)統治など。マイナーなところではデンマーク東インド会社(1620〜1726)や、アフリカ西岸(ガーナ)の一角を支配したスウェーデン東インド会社(1650〜63)もあります。これら東インド会社は、当初は貿易独占の特許を得た貿易会社で、商船隊を派遣し商館を建てて取引していましたが、現地での貿易を独占するためには、点(港)の確保だけではなく面(後背地)の支配も不可欠。かくして現地支配者を制圧したり他国のライバル会社の貿易拠点を襲うために、強力な軍事力を擁し、植民地を確保した後は、行政権のみならず警察権や徴税権、司法権も与えられました。しかし、広大な植民地を支配するには軍事費の負担が重くのしかかるようになり、会社の経営は破綻。18世紀末から19世紀にかけて、これら東インド会社は次々と解散し、植民地の統治は国家が引き継ぐことになりました。
東インド会社のほかにも、アメリカやブラジル、ガイアナ、アフリカのガーナにおけるオランダ西インド会社(1621〜1791)や、ルイジアナやカナダ・ケベック地方のフランス西インド会社(1664〜74)、バージン諸島のデンマーク西インドおよびギニア会社(1672〜1754)、ロシア領時代のアラスカを統治した露米会社(1799〜1867)、リベリアのアメリカ植民協会(1822〜47)、ベルギー国王領コンゴのコンゴ国際協会(1876〜85)やカタンガ会社(1891〜1900)、ドイツ領東アフリカ(現在のタンザニア)のドイツ植民会社(1884〜89)、ナミビアのドイツ南西アフリカ殖民会社(1885〜89)、ドイツ領ニューギニア(現在のパプアニューギニア北部)のニューギニア商会(1884〜99)、ナイジェリア北部を統治したイギリスの王立ニジェール会社(1886〜1900)現在のケニヤ・ウガンダを統治したイギリス東アフリカ会社(1888〜94)などがありました。1670年に設立され、カナダ北部に広大な領地を持ちイヌイット(エスキモー)との毛皮交易を独占したハドソン湾会社は、1869年にイギリス政府へ領地を返上したものの、現在でもカナダ最大手の流通企業として存続しています。
これら植民地統治を代行した会社とは違ったケースが、ボルネオ島西部(現在のインドネシア領カリマンタン)のマンドールやポンテイアナック一帯を統治した蘭芳公司(1777〜1884)。広東省から移住してきた客家系中国人が組織した会社形式の共同体で、鉱山開発を行っていましたが、鉱山労働者に加え農民、商人、さらに現地のスルタンも傘下に収め、中国人4万人と先住民20万人を支配するようになりました。代表者である大唐客長は選挙で選ばれ、アジア最初の共和国だとも言われています。やがてこの地にオランダが進出し、1825年に大唐客長はオランダからカピタン(キャプテン)に任命されてその傘下に入るようになり、1884年にはオランダに武力併合されて消滅しました。
ま、あんまり昔の話を書くとキリがないので、ここでは20世紀に存在した会社統治領に限定して取り上げることにします。
【過去形】イギリス北ボルネオ会社現在のマレーシアの地図 現在ではマレーシアのサバ州

現在のサバ州の地図
北ボルネオとは、現在のマレーシアのサバ州のこと。イギリスはボルネオ一帯では、他にもラブアン島、サラワク(いずれも現:マレーシア)、ブルネイの各植民地を持っていたが、統治システムはそれぞれ違っていて、ラブアン島はシンガポールに政庁を置く海峡植民地の一部として直轄領、ブルネイはスルタンを通じた間接支配、サラワクはイギリス人の「白人王」が率いる間接支配、そしてサバはイギリス北ボルネオ会社による会社経営の植民地だった。
ボルネオ島には17世紀からオランダが、18世紀にはイギリスが進出して争っていたが、1842年の英蘭協定で北部をイギリスが、南部をオランダが支配することで合意。イギリスはまずラブアン島に拠点を築いて北ボルネオへの進出を本格化させた。1855年にはアメリカがブルネイのスルタンからボルネオ島北端のアムボン、マルヅ一帯を租借し、米華商会を設立して、中国人労働者を導入し農園を作ろうとしたが、本国からの経済的支援を受けられず、中国人労働者のほとんどが死亡して撤退。1878年に英国人アルフレッド・デントが設立した北ボルネオ会社がそれを引き継いで、81年にブルネイやスールー諸島(現:フィリピン)のスルタンから北ボルネオの租借に成功した。こうして北ボルネオは、88年にサラワク、ブルネイとともに正式なイギリスの保護領となった。
北ボルネオ会社はイギリス国王から外交を除いたあらゆる統治権が与えられ、閣議に相当するのはロンドンの本社で開かれる重役会。現地には重役会が任命してイギリス植民地大臣が承認した総督(支配人)が派遣され、総督は行政機関を率いるほか、官吏9人と民間人5人(業界団体代表が選出し、重役会の承認を経て総督が任命)からなる立法評議会の補佐によって法律を制定した。また総督は大審院長を兼任して裁判所を率いたが、裁判官の任命にも重役会の承認が必要だった。ただし先住民同士の訴訟は、先住民の慣習に基づいた土人法令によって酋長裁判所が担当した。北ボルネオ会社は警察と、巡憲隊という軍隊を擁し、国立銀行を設立して通貨を発行(シンガポールの海峡ドルと同価)したり、郵便局も経営した。
北ボルネオの主な輸出品は木材、天然ゴム、煙草、コプラで、東部のタワオでは日本人経営のゴム農園や漁業基地が栄えていた(※)。農園労働者や商人には中国人が多く、北ボルネオ会社は原住民と違ってよく働く中国人労働者を積極的に集めるようと、中国からの移住者やその家族の呼び寄せには片道乗船券を無料で支給する制度も実施していた。
※タワオで大ゴム園を経営していたのが久原農場で、後の日産コンツェルン。また明治から大正にかけては、日本から大勢の「からゆきさん」が北ボルネオへ渡っていて、『サンダカン八番娼館』の舞台・サンダカンは、当時の北ボルネオの首都。北ボルネオ会社の収入は、輸出入関税に次いで多かったのがアヘン販売税で、他に土地貸付料、森林伐採料、鉄道経営収入(現:サバ州立鉄道)、郵便収入など。毎年大幅な黒字を計上してイギリス本国の株主に配当を出していた。その一方で、教育などにはほとんど予算を割かず、1937年当時北ボルネオの学校133校のうち、公立学校はたったの17校。残りは全て私立学校で、うち67校には補助金すら支給しなかった。中国人労働者を呼び込んでアヘンを吸わせ、儲けた金は教育なんかに使えるか!というわけで、まぁ、かなり露骨な植民地式搾取ってやつですね。同じイギリス保護領でも、「白人王」ブルック一族が統治する隣りのサラワクでは、イギリス本国からの内政介入を排して先住民との融和に気を使い、議会では先住民議員が多数を占め、外国資本による搾取から先住民を保護しようとしたのとは、対称的だったようだ。
太平洋戦争が勃発すると、北ボルネオはサラワク、ブルネイとともに日本軍に占領された。戦時中に都市や農園は荒廃し、復興に多額の投資が必要となるため、1946年に北ボルネオ会社は白人王とともに統治権をイギリス政府へ返上し、北ボルネオとサラワクはイギリスの直轄植民地になった。その後1963年にマラヤ連邦と合併してマレーシア連邦になったが、歴史的な経緯から、サバ州とサラワク州はマレーシアの中で高度な自治権を持ち、現在でも入国審査は別々にやっていて、マレー半島とサバ、サラワクを行き来する場合にはパスポートが必要になっています。
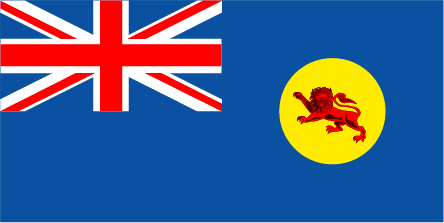
サバ州一周の旅シリーズ サバ州各地の旅行記や写真があります
新Web Siteボルネオ研究 戦前のボルネオに関していろいろ
ボルネオ歴史事典 ↑の姉妹サイト。ボルネオの歴史に関係した日本人や日系企業の説明が詳しいです
【過去形】イギリス南アフリカ会社中央アフリカ連邦時代(1953〜63)の地図昔はチャガタイ汗国とかキプチャク汗国とか、特定の個人名が国名になった国がたくさんありましたが、現代ではどうでしょう?コロンブス→コロンビアや、ボリバール→ボリビアとか、中南米には多そうです。ケニヤの初代大統領はケニヤッタでしたが、本名カマウ・エンゲンギさんが独立運動を始めたときに「ケニアの光」を意味するケニヤッタに改名したわけで、さすがに「ケニヤッタが作った国→ケニヤ」ではないですね。反政府ゲリラから政権の座についた人は、変名のまま大統領や首相になることが多く、カンボジアのポル・ポト(本名:サロト・サル)やベトナムのホー・チミン(本名:グェン・シンクン)もそうです。ホー・チミンは一時期、グェン・アイクォック(阮愛国)を名乗っていましたが、そのまま政権についていれば、ホーおじさんは「愛国おじさん」と呼ばれて、一層親しまれたかも知れません(?)。
さて、今は亡きローデシアという国も、セシル・ローズという人の名から付いた国名でした。そのセシル・ローズが作った会社がイギリス南アフリカ会社(BSAC)で、19世紀末から20世紀初めにかけて南ローデシア(→ローデシア→ジンバブエ)と北ローデシア(→ザンビア)を統治していました。
セシル・ローズは1870年に17歳でイギリス領だった南アフリカへ渡り、ダイヤモンド鉱山と金鉱を開発して巨万の富を築き、90年にはケープ植民地の首相となったが、一足先に入植していたオランダ系白人(アフリカーナ)が南ア北部で建国したトランスバール共和国やオレンジ自由国を併合しようと圧力をかける一方、さらに北へ進出するために1889年にイギリス南アフリカ会社を設立。イギリス女王から土地の所有や鉱山の開発、行政統治についての特許状をもらい、翌年200人の遠征隊と400人の護衛騎馬隊を北へ出発させた。遠征隊は先住民の酋長たちと戦ったり補助金や保護を与えると約束しながら、マタベレランドやマショナランドの鉱山開発権を獲得、両地方を併合して「ローデシア」と名づけ、さらに北のパロツェランド(現:ザンビア南部)を占領した。
しかし南アフリカ会社のスタートは思ったより順調には進まなかった。ローズはローデシアでも南アフリカのように黄金がザクザク見つかるだろうと思っていたようだが、たいした金鉱脈は見つからず、ローズ自身も95年に「イギリス系住民の保護」を名目にトランスバールへの侵攻を企てて批判を浴び、政界から引退を余儀なくされ、1902年には世を去った(※)。
※結局イギリスは1899年にトランスバールやオレンジ側から戦争を仕掛けて来るのを待って占領し、1902年に両国を併合。1910年に英連邦自治領の南アフリカ連邦が成立した。そのため南アフリカ会社は方針を転換し、農地開拓を行うことにした。遠征隊に加わった者には3000エーカー(約12平方km)の土地を与えることを約束。先住民たちに土地所有の概念がなかったことをいいことに、土地をどんどん白人に分け与え、南ローデシアでは1923年までに白人は合計3000万エーカーの土地を占拠。昔からそこに住んでいた黒人たちは、いつの間にか白人が所有する農地の中に住む「不法占拠者」にされてしまった。黒人たちは土地の所有者である白人の農場で働くか、あくまで今までどおり「自分の畑」を耕すなら白人地主に地代を払わなくてはならなくなった。これではあまりに黒人が可哀想だと、2550万エーカーの土地が原住民居住地に指定されたが、そのほとんどは農業に向かない荒地だった。南アフリカ会社はローデシアに鉄道を敷き、農作物の輸出は増えていった。行政運営は会社が任命しイギリス政府が認可した行政長官が行い、白人入植者によって選ばれた議員による顧問会議も設置された。しかし白人入植者の間では「会社が行う行政運営は利潤追求のための鉱山開発が優先されて、入植者への福祉が後回しにされている」と、責任ある政府の設立を求める声が高まっていった。一方、イギリス本国の会社の株主たちの間でも、会社が行政に加えて軍隊まで運営するため経営コストがかさみ、配当金が支払われないことに不満が噴出。何しろ30年間の会社統治で行政運営の財政赤字は800万ポンドにのぼり、商業活動での利益は消えてしまっていたわけで、「会社の業務は商業活動に徹するべきだ」との声が挙がった。
南アフリカ会社は行政権を南アフリカ連邦へ移譲することを望み、連邦政府もそのつもりで、これまでの財政赤字の補償金として683万6500ポンドを会社へ支払う意向を示していたが、1923年に南ローデシアで行われた住民投票(もちろん白人だけ)の結果は、単独での自治政府樹立が多数を占めたため、南ローデシアはイギリス政府に移譲されて自治領となり、翌24年に開発がさっぱり進まなかった北ローデシアもイギリス政府へ移譲されて直轄植民地となった。南アフリカ会社がイギリス政府から受け取った補償金は365万ポンドで、連邦政府に比べてだいぶ安く買い叩かれてしまった。
こうして南アフリカ会社は400万エーカーの土地と鉄道、鉱山だけを残して商業活動に専念することになったが、北ローデシアではなんと会社統治を離れた翌年に世界最大級の銅鉱脈が発見される。南アフリカ会社はこの時すでに独占開発権を失っており、銅鉱山は別のイギリス資本のアングロ・アメリカン社(AAC)と、アメリカ資本のローデシア・セレクション・トラスト社(RST)の手で開発が行われることになった。南アフリカ会社の懐にも鉱区使用料が入ったとはいえ、北ローデシアの統治をあと1年辛抱して続けていたら利益を独占できたのに・・・これも運命ですかね。

【過去形】モザンビーク会社&ニアサ会社葡領東アフリカの地図 Companhia de Mocanbique(モザンビーク会社領)やCompanhia do Nyassa(ニアサ会社領)があります(英語)
現在のモザンビークの地図 旧モザンビーク会社領はソファラ州とマニカ州、旧ニアサ会社領はカボデルガド州とニアサ州
モザンビークは旧ポルトガル領東アフリカ。ポルトガル植民地だったのに、1995年には英連邦に加盟してしまいました。ついでに言えば、ポルトガル本国は車は右側通行なのに、モザンビークではイギリス式に左側通行。一体なぜでしょう?
16世紀末のバスコ・ダ・ガマの航海以来、ポルトガルはアフリカ南端の喜望峰回りで積極的にインドへ進出したが、その中継地として確保したのがモザンビーク。とはいえ、沿岸部に拠点を築くだけで、内陸部は長らく放置していたが、1891年に中央部(14万平方km)の行政権をモザンビーク会社に、93年には北部(20万平方km)の行政権をニアサ会社に与えて、本格的な開発に乗り出した。この2つの会社は警察権や徴税権、通貨発行権や郵便事業権などを擁し、鉄道の建設や鉱山の開発、農場経営などを行った。ただし司法権は与えられず、会社はモザンビーク政庁へ裁判所の運営経費や宗教活動への援助を負担する義務があった。
これらの会社はポルトガルの国策会社かと思いきや、実は英仏資本の会社で、実質的にはイギリスの支配下にあった。なんだかポルトガルの植民地がイギリスに乗っ取られたような形だが、この時期はポルトガル本国すら、イギリスの強い影響下に置かれていたのだ。
1807年、ヨーロッパ大陸を席巻しつつあったナポレオン率いるフランスは、スペインと手を結んでポルトガルへ侵入した。ポルトガル国王はリスボン陥落の直前にイギリスの援助でブラジルへ逃げたが、ナポレオンの敗北後も帰国しようとせず、ブラジルへ移った貴族たちは本国の所領から地代を送金させ、ポルトガル本国はあたかもブラジルの植民地に転落したような状態になった。1820年に本国で立憲革命が起きると、ブラジルに残った王室は独立を宣言し、最大の植民地を失ったポルトガルは19世紀の前半を通じて内戦と反乱が続く。こうしてポルトガルはイギリスに借金を重ね、財政破綻状態となったポルトガルは借金のカタとして、国内の鉄道や鉱山などの利権をイギリスに与えていった。
さらにイギリスとドイツは1898年に秘密協定を結び、もしポルトガルがこれ以上の借款を申し込んできた場合は、ポルトガルの海外植民地を両国で分割することを決めた。モザンビークは南北に分割して北はドイツ、南はイギリスが獲得することとされたが、翌年イギリスは南アフリカ北部にオランダ系のブーア人が作ったオレンジ自由国、トランスヴァール共和国を併合するべくブーア戦争(南ア戦争)を起こし、ポルトガルが英軍のモザンビークでの通行を認めることと引き換えに、イギリスはポルトガル植民地の保全を約束した。こうしてポルトガルのイギリスに対する依存はますます強まった。
モザンビーク会社領の中心地・ベイラは、内陸部にあるイギリス植民地の南ローデシア(現:ジンバブエ)、北ローデシア(現:ザンビア)、ニアサランド(現:マラウイ)にとって、海への出口にあたる場所。これらの地域の農産物や鉱産物は、モザンピーク会社が建設した鉄道によってベイラ港へ運ばれ、海外へ輸出された。後にイギリスの介入は一層露骨になって、ベイラ港の港湾施設や鉄道は、モザンビーク会社からイギリス南アフリカ会社へ譲渡され、両社の間では役員の交換も行われて一体化が進んだ。またモザンビーク会社は南ローデシアやトランスヴァールで南アフリカ会社が経営する鉱山に、黒人労働者を送り込み、最盛期にはモザンビークから年間10万人近い黒人が出稼ぎに行ったという。
一方でニアサ会社領では、先住民の反乱が相次いでいたため、開発は遅々として進まなかったが、イギリスにとっては北側に隣接するドイツ領東アフリカ(現:タンザニア)の拡大を防ぐために、戦略的な意味を持っていた。この他に行政権は獲得していなかったが、イギリス資本でサトウキビ農場などを経営するサンベシア会社も広大な土地を擁し、モザンビーク会社とニアサ会社、サンベシア会社の3社で、モザンビークの半分以上の土地を所有していた。
ニアサ会社領は1929年に、モザンビーク会社領は41年にそれぞれ廃止されたが、その後もモザンビークとイギリス、南アフリカとの経済的な深い関係は続いた。75年のモザンビーク独立では社会主義政権が誕生し、南アフリカや当時のローデシア白人政権を敵にまわして経済的に困窮した時期もあったが、モザンビークの歴史を振り返ってみれば、英連邦加盟は取り立てて不思議な話ではないようですね。
外国切手の楽しみ モザンビーク会社が発行した切手の写真があります
P-R26, 50 Centavos, 1931 モザンビーク会社が発行した紙幣の写真です
【過去形】フェロナルディ会社&ベナディール会社
中世にはバルカン半島沿岸からギリシャ、黒海にかけてベネチアやジェノバが飛び地状の植民地を広げていたのに、19世紀後半のヨーロッパ列強諸国による植民地獲得戦ではすっかり出遅れてしまったイタリア。そのアフリカ進出を手助けしたのはイギリスで、当時アフリカの分割をめぐって最大のライバルだったフランスの「東西アフリカ横断植民地の獲得」を阻止するためにイタリアを利用した。こうしてイタリアはアルジェリア(フランス領)とエジプト(イギリス保護領)の間にリビアを獲得し、フランスが紅海沿岸に仏領ソマリランド(現在のジプチ)を獲得すると、周囲のエリトリアとソマリア南部をイタリアが確保した。
調子に乗ったイタリアはエチオピアも植民地にしようと、イギリスの支持を得て1894年にティグレ地方を占領したが、エチオピアのメネリク皇帝はフランスの支援で武力増強を図り、96年にアドワの戦いでついに反撃に出た。この戦争でイタリアは1万7000人の兵士のうち1万1000人が戦死し、4000人が捕虜になるという惨敗ぶりで、エチオピアから撤退し賠償金を払うはめになった。結局イタリアがエチオピアを征服したのは、ムッソリーニ時代の1936年のこと。
さて、ソマリア南部の海岸はオマーン海洋帝国や1861年にそこから分離独立したザンジバルが支配していたが、1889年にザンジバル駐在のイタリア領事のフェロナルディが、スルタンからブラバ、メルカ、モガディシュ、ワルシェイクの4港を年間16万ルピーで25年間租借する契約を結んだ。こうしてフェロナルディは外交官を辞めて91年にフェロナルディ会社を設立し、これらの地域の統治を委託されたが、経営は思わしくなかったようで、翌92年に租借料を年間12万ルピーにまけさせ、96年には資金不足で倒産してしまった。
代わってミラノで設立されたベナディール会社(Societa Commerciale Italiana del Benadir)が統治を引き継ぎ、イタリア人入植者がバナナやサトウキビの栽培を行ったが、イタリアは1905年に租借地を併合。会社から統治権を買い取って、直轄植民地のイタリア領ソマリランドになった。
戦後、イタリア領ソマリランドはイギリス領ソマリランドと合併して、ソマリアとして独立しますが、内乱続きで国家崩壊の状態になっています。
WHKMLA : History of Somalia, 1889-1918 ベナディール会社時代の切手の写真があります(英語)
【過去形】スエズ運河地帯スエズ運河地帯の英軍基地(1954年)パナマ運河地帯は最近までアメリカの租借地でしたが、スエズ運河地帯も実は1954年まで租借地だった。どこの国の租借地かといえば、国の租借地ではなくて万国海洋スエズ運河会社(Compagnie Universelle du Canal Maritime de Suez)という会社の租借地でした。
スエズ運河会社は運河の管理権を握っていたほか、延長160kmの運河の両岸一帯の行政権も獲得していた。スエズ運河会社はフランス登記の会社で、会社から派遣された総督の下で行政委員会が運河地帯の統治を行っていた。行政委員会の構成は、フランス人16人、イギリス人9人、エジプト人5人、アメリカ人とオランダ人が各1人だが、実際にはこういう経緯で、会社の44%の株式を持つイギリスが主導権を握り、総督もイギリス人。また運河地帯には1922年のエジプト独立後もイギリス軍が駐屯し続け、大規模な軍事基地と英軍中近東司令部が置かれていた。
スエズ運河地帯の租借権は、1869年の開通から99年間、つまり1968年までと規定されていたが、エジプトでは1952年の自由将校団のクーデターによって王制が倒れ、汎アラブ民族主義を掲げたナセルが54年に政権を握ると、運河地帯からの英軍の撤退を要求して実現。さらにエジプトの中立政策に反発して、アメリカやイギリスがアスワン・ハイ・ダムの建設計画(ナイル川に巨大ダムを作って砂漠を農地に変える計画)に資金を出し渋ると、ナセル大統領はスエズ運河の通行料収入でダム建設の資金を賄おうと、56年7月にスエズ運河会社の国有化を発表する。
運河の利権を突然奪われて納得がいかないイギリスとフランスは、イスラエルをけしかけて10月29日にシナイ半島を攻撃させ、11月5日には「スエズ運河の保護」を理由に英仏軍が運河地帯を占領した(第二次中東戦争またはスエズ動乱)。しかし植民地主義丸出しのやり方に、英仏は国際社会の非難を浴び、頼りにしていたアメリカからも批判されて、翌日には国連の停戦決議を受けて撤退。こうしてスエズ運河会社はエジプト政府のスエズ運河局に接収され、英仏系の会社が行政権を持つ運河地帯は消滅したのでした。
船の生活 スエズ運河の姿 船乗りさんによるスエズ運河の紹介
第二次中東戦争 スエズ動乱 スエズ動乱についてわかりやすく解説されています
【過去形】王立グリーンランド貿易会社自治政府が発足する前のグリーンランド
「キングなんとか×世ランド」ばっかり「デンマークってヨーロッパの小国なのに、なぜあんな大きなグリーンランドを領土にしてるの?」と私は子供の時から疑問に思っていましたが、調べてみると19世紀まではなかなかの大国で、ノルウェーを併合し、北海のアイスランドやグリーンランド、フェロー諸島を植民地にしていたほか、東インド会社を作ってインド(トランケバルとセランブール、アンダマン諸島、ニコバル諸島)やアフリカ(黄金海岸)に植民地を持ち、西インド会社も作ってカリブ海(現アメリカ領バージン諸島)にも植民地を持っていました。
このうち北海の3植民地は、もともとノルウェーのバイキングが入植していた土地だが、1536年にノルウェーがデンマークに併合されたのでデンマーク領になったもの。ノルウェーは1814年にデンマークから独立(ただし翌年スウェーデンが併合)するが、植民地はデンマークに「置き土産」として残されたままになった。氷だらけの大地に「グリーンランド」という皮肉なネーミングをつけたのも、ノルウェー出身のバイキングのユーモア(?)だった。
グリーンランドに最初に入植したバイキングは、ノルウェー生まれの「赤毛のエリック」という男で、子供の時に父親が殺人を犯したためアイスランドへ引っ越し、エリックもアイスランドで殺人を犯して追放された時にグリーンランドを発見。985年にアイスランドへ戻り、「緑の大地を見つけた!」と宣伝して入植者を集めた。こうしてバイキングたちはグリーンランドの南岸に村を作り、約5000人が暮らしていたが、主食となるトウモロコシの栽培はできず、牧畜をしたり北極熊の毛皮やセイウチの牙をヨーロッパに輸出して暮らしていた(※)。しかし大寒波の襲来か、はたまたヨーロッパでのペストの流行で交易船が途絶えたためか、15世紀末までにバイキングの村は全滅してしまう。
※本物の「緑の大地」はないのかと、エリックの息子・レイフはさらに探検の船を進め、ついに穀物が実る「ヴィンランド」を発見して居住地を作ったが、先住民に襲われて撤退した。ヴィンランドはカナダ東岸のニューファンドランド島だと言われており、アメリカを最初に発見したヨーロッパ人はコロンブスではなく、「赤毛のエリックの息子」が真相らしい。その後のグリーンランドではバイキングと同じ頃に、カナダから氷伝いにやって来たエスキモーたちが暮らしていたが、ヨーロッパ人が再びグリーンランドに入植するのは1721年のことで、デンマークの伝道師がグリーンランドへ渡り、エスキモーをキリスト教に改宗させ始めた。そして1774年にデンマーク政府はグリーンランドとの貿易を王立グリーンランド貿易会社に独占させることを決め、グリーンランドの統治も同社に委ねることにした。統治と言っても会社がグリーンランドでインフラ整備やエスキモーに対する教育や福祉を行ったわけではなく、あちこちに交易所を建ててエスキモーからのアザラシやセイウチ、クジラ、北極熊、キツネなどの買い付けを独占しただけだった。いわば江戸時代の北海道や樺太で、沿岸各地に番屋を建て、そこでのアイヌとの取引を特定商人に請け負わせたのと同じようなもの。これによって当時、北極海に進出していたイギリスやオランダ、アメリカの捕鯨船はグリーンランドから締め出され、デンマーク側によれば「グリーンランドのエスキモーは新たな伝染病から守られた」のだそうだ。
しかし20世紀に入ると、グリーンランドの統治を会社任せにし続けるわけにはいかなくなり、1908年に南と北で2つの議会を設置したのに続いて、1912年にはグリーンランドの行政権をデンマーク政府が回収した。デンマーク政府がグリーンランドの直接統治に乗り出したのは、グリーンランドの領有権を主張する国が続々と現れたからだった。会社統治時代のグリーンランドで会社の支配が及んでいたのは南部の沿岸だけで、北部や内陸部はまったく放置されていた。「誰も支配していないのなら、俺が支配したっていいだろ!」と言うわけで、アメリカやイギリスは自国の探検隊が到達した実績を盾に北部の領有権を主張し、ノルウェーは「赤毛のエリック」の実績を盾に沿岸部の領有権を主張、1905年までノルウェーを併合していたスウェーデンもこれに便乗した。
デンマーク政府はグリーンランドに対する直接統治を始める一方で、まずアメリカと交渉し、西インド諸島の植民地を2500万ドルでアメリカへ売却することと引き換えに、グリーンランドに対するアメリカの領有権を放棄させることに成功。イギリスとスウェーデンもアメリカに説得されて領有権を取り下げた(※)。
※アメリカは米西戦争(1898年)の後、デンマークにバージン諸島の売却を求め、デンマーク政府は1902年に売却の契約を結ぶが議会が承認せず、頓挫していた。第一次世界大戦が勃発すると、アメリカはドイツのUボートからパナマ運河を守るために、バージン諸島に海軍基地を作ろうと、領土の売却を改めて要望していた。しかし、グリーンランドは自国民(バイキング)が最初に入植したのに、デンマークに横取りされたとの思いが強いノルウェーは一歩も引かず、東岸を「赤毛のエリックランド」と命名して併合を宣言して入植地を作り、さらに当時デンマークの自治領だったアイスランドまでこれに同調した。デンマーク政府は住宅を無料支給してエスキモーをノルウェー占領地域から引き揚げさせる一方で、国際司法裁判所に提訴。1933年にグリーンランドをデンマーク領とする判決が出てようやく解決した。デンマーク政府に行政権が移った後も、王立グリーンランド貿易会社はグリーンランドでの貿易を独占していたが、1940年にナチスドイツがデンマークを占領すると、グリーンランドはアメリカが占領。グリーンランドはデンマーク本土との連絡を立たれて、会社は営業停止状態になってしまう。戦後、1953年にグリーンランドはデンマークへ返還されたが、それに先立つ1950年に会社の貿易独占権は廃止され、水産会社のロイヤル・グリーンランド社として再出発。1979年にグリーンランドにエスキモーを中心とした自治政府が発足すると、翌年ロイヤル・グリーンランド社はデンマーク政府の国営企業から、グリーンランド自治政府の公社に移管され、90年からは民営化されているが、会社の名称は相変わらずロイヤル(王立)のままだ。
現在のロイヤル・グリーンランド社は従業員3000人を抱える世界有数の漁業・水産加工会社で、日本にも「ロイヤル・グリーンランド・ジャパン」という現地法人がある。日本で消費されている甘エビの4分の1近くは、ロイヤル・グリーンランド社が供給しているそうです。
王立グリーンランド貿易会社の旗
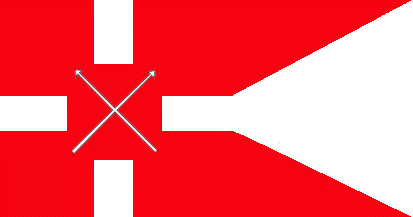
Royal Greenland ロイヤル・グリーンランド社のHP
【過去形】ヤルート会社ドイツ領だった頃の南洋群島の地図(1908年)

南太平洋の地図(1995年)
現在のマーシャル諸島の地図
ドイツの植民地だった頃のマーシャル諸島の地図。ナウルも一緒に統治(1913年)♪私のラバさん、酋長の娘〜、色は黒いが、南洋じゃ美人〜♪という歌がありましたが、その舞台になったのが太平洋のマーシャル諸島。歌が作られた頃(昭和5年)は日本の委任統治領でしたが、第一次世界大戦まではドイツ領で、ヤルート会社という商社が行政を任されていました。
マーシャル諸島へ最初にやって来た白人はスペイン人で、1686年に領有を宣言したが、メキシコとフィリピンの間にある通り道だから確保しておいたというくらいで、金や銀があるわけでもなければ香辛料が採れるわけでもないマーシャル諸島は放置され、実際には何も統治をしなかった。
しかし19世紀半ばになると、ヤシ油の原料となるコプラ(ヤシの果肉を乾燥させたもの)を求めて、イギリスやドイツの商社が相次いでマーシャル諸島へ進出(※)。中心地のヤルート島では特にドイツ系商社の活動が盛んで、1873年にゴッドフロイ商会(ゴーデフフロイ商会)が、76年にはヘルンスハイム商会が支店を開き、椰子の植樹を行ってコプラの生産に乗り出した。しかしゴッドフロイ商会は1879年に破産、代わってドイツ南洋貿易植樹会社が設立されたが事業はうまくいかず、バーンズ・フィリップ社などイギリス系商社に圧倒されるようになったため、ドイツは大酋長と条約を結んで、1885年にマーシャル諸島を保護領にした。イギリスも経済活動の門戸開放を条件に、これを認めた。
※コプラから作られるヤシ油は、石鹸やマーガリンの原料になる。帆船の時代はヨーロッパとの間は貿易風任せで1年に1往復しかできなかったが、蒸気船が実用化されるようになり、ヤシ油のようなものでも輸出商品として十分採算が合うようになった・・・ということらしい。ドイツはかつてのイギリス東インド会社をモデルにして、ヘルンスハイム商会にマーシャル諸島の統治をさせようとしたが、「資源が貧弱」だと同社が断ったために、ヘルンスハイム商会とドイツ南洋貿易植樹会社を合併させてヤルート会社を設立し、1888年からマーシャル群島の行政をヤルート会社に任せた。法律はドイツ政府から派遣された監督官が制定したが、事前にヤルート会社に諮問する仕組み。ヤルート会社は関税や営業税のほか、住民から人頭税を徴収したが、島民はコプラの物納だった。島民たちは畑でイモを栽培したり魚を捕ったりという伝統的な自給自足生活の合間に、ヤシの実を集めてコプラを作り、1年に何回かまわってくるヤルート会社の船(※)にそれを売って、日用品を購入するようになった。※ヤルート会社の船は、シドニー〜ラバウル〜ナウル〜ヤルート〜クサイ〜ポナペ〜トラック〜サイパン〜ウリアイ〜ヤップ〜パラオ〜香港というルートで、3ヵ月半かかって往復し、年に3〜4回運航されていた。ヤルート会社が行政を担当したといっても、実際に島民たちを統治していたのは昔からの酋長や大酋長だった。島民たちが売ったコプラの買い付け代金のうち半分は酋長に支払われる仕組みで、なんだか酋長が島民を搾取しているみたいだが、そのかわり会社へ納める島民の人頭税は酋長が一括して負担し、島民がカヌーの帆を作るとき酋長は費用の一部を補助し、島民が病気にかかると治療費を全額負担する義務があった。いわば政府が行うべき福祉を、酋長が個人で行うという仕組み。後にマーシャル諸島が日本の委任統治領になると、酋長や大酋長は村長や総村長に任命されて、伝統的な慣習はそのまま引き継がれたが、やがて日本があちこちの島に診療所を建てると、島民たちは頻繁に医者にかかるようになり、治療費を全額支払っている酋長が困窮。治療費の一部を島民が自己負担することに改められたとか・・・なんだか現在の日本の福祉財政難みたいですね。
日本の委任統治領だった頃の地図(クリックすると全体図に拡大します)さて、ヤルート会社によるマーシャル諸島の統治は1906年に終了し、代わってドイツはヤルート島に政庁を設置して統治することになった。そのきっかけは1905年にイギリスのバーンズ・フィリップ社の船がヤルート港に入港しようとしたところ、ヤルート会社が急に営業税を引き上げて、バーンズ・フィリップ社の商売が不可能になってしまった事件。この事件はイギリスとドイツの外交問題に発展し、ドイツ政府はイギリスに賠償金を支払ったが、「自分の利益しか考えない会社に行政を任せておけない」と、翌年ヤルート会社との契約を打ち切った。
またドイツは当時、中国の膠州湾(青島=1898年)からカロリン諸島(1899年)、マリアナ諸島(1899年)、ナウル(1888年)、サモア(1900年)、ニューギニア北東部(1884年)にかけての、太平洋の広大な地域に植民地を点在させていたが、ヤップ島を中心にそれらを海底ケーブルで結び、電信網を築こうと1904年に独蘭電信会社を設立。マーシャル諸島はじめ南洋群島は太平洋の通信拠点として重要性を持つようになっていた。
行政権を取り上げられたヤルート会社だが、会社の業績はその後も順調で、マーシャル諸島でのコプラ買い付けに加え、1906年からはイギリスの太平洋諸島会社(後述)と共同で、当時はマーシャル諸島の一部だったナウルで、リン鉱石の採掘に着手し莫大な利益を上げた。また1912年にヤップ島に西カロリーネン会社、13年にサイパン島に東カロリーネン会社を設立して土地を所得し、南洋群島全体でコプラの生産に乗り出そうとしたが、第一次世界大戦で日本軍に占領されて頓挫。マーシャル諸島はその後、日本の委任統治領となり、ヤルート会社に代わって南洋貿易の船が島々をまわってコプラを買い取るようになった。第二次世界大戦後はアメリカの信託統治を経て、1986年にマーシャル諸島共和国として独立しています。
ヤルート会社の旗
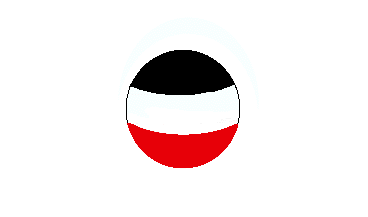
外務省ーマーシャル諸島共和国
ミクロネシアーはるかなる歩みの歳月 ドイツ統治時代や日本、アメリカ統治時代の南洋群島の写真がたくさんあります
の〜んびり人生 マーシャル諸島に在住する日本人のサイト。現在の島の写真や出来事など
Digital Micronesia--Marshalls History ドイツ統治時代や日本、アメリカ統治時代の南洋群島の資料や地図など(英語)
【過去形】太平洋諸島会社(バナバ島)太平洋の地図 Banaba島はナウルの右隣の紫色の島
バナバ島の地図 「太洋島」と呼ばれていた1936年作成の地図戦前の地図では太洋島(バナバ島)は日本のすぐ隣でした
燐鉱石は肥料の原料ですが、もとはといえば鳥の糞。大海原を横断する渡り鳥の糞が何万年にもわたって積み重なり、サンゴ礁の石灰と化合して出来たのが燐鉱石。太平洋にポツンと浮かぶような島には燐鉱石が眠っていることが多く、19世紀後半から20世紀前半にかけて、イギリスやアメリカがそれまで目もくれなかったような小さな無人島をめぐってせっせと領有合戦を繰り広げていました。日本も北大東島や沖大東島、南鳥島、委任統治領だったアンガウル島(現在はパラオ共和国)、戦前領有権を主張していた新南群島(南沙諸島=スプラトリー諸島)などで燐鉱石を採掘していました。
燐鉱石は掘り尽くしてしまえばオシマイ。採掘で島の大半が削り取られ、農業も出来ない荒地になります。もともと無人島だった場合はあとは野となれ山となれで、再び無人島に戻るケースが多いのですが、島民が住んでいた場合は後が大変です。「国民皆成金」になったと思えば燐鉱石が枯渇して国家破産状態になったナウルは有名ですが、島民たちが数十年間オイシイ思いをしてきただけまだ幸運。燐鉱石のおかげで散々な目に遭ったのが、バナバ島の島民です。
バナバ島はナウルの東にある島で、現在はキリバス領。かつてはイギリス植民地でオーシャン島、日本では大洋島と呼ばれていたこともある。島にはメラネシア系のバナバ人が数千人住んでいたが、1900年に太平洋諸島会社のアルバート・エリスというニュージーランド人が島を訪れ、酋長と999年間の租借契約を結んで燐鉱石の採掘を始めた。
太平洋諸島会社はジョン・T・アランデルというイギリス人が1890年にオーストラリアで設立した会社がルーツで、ギルバート諸島(現在のキリバス西部)を中心に、燐鉱石の採掘やコプラの生産、真珠貝の採取などを行ったが、船を一隻しか手配できなかったため、燐鉱石やコプラを集めても輸出がままならず倒産しかけていた。そこでイギリスの西太平洋諸島総督を引退したスタンモアを社長に招き、太平洋諸島会社(Pacific Islands Company )として改組。ようするに総督の天下りを迎えて政府の協力を得ようとしたわけで、ジャービス島やベーカー島、ハウランド島(いずれも現在はアメリカ領)やフェニックス諸島一帯で燐鉱石の採掘を始めたが、いずれも資源に乏しく、1899年には再び倒産の危機に瀕していた。
その頃、オーストラリアの本社で事務をしていたエリスは、事務所のドアを押さえるために使われていた石ころが気にかかり、調べてみたところ豊富なリンを含んでいることを発見。この石ころは元社長のアランデルが何年も前にナウル島で拾ってきたものだった。ナウル島は当時ドイツ領だったが、船長たちから「隣りのバナバ島も似たようなもんだよ」という話を聞き、それなら似たような石もあるかもと現地へ赴いてみたところ、大当たり。島には土というものがほとんどなく全てが燐鉱石だったのだ。
バナバ人たちはずっと水や食糧の不足に悩んでいた。いくら燐鉱石が極上の肥料になると言っても、肥料の上に種をまいたら作物は育たないわけで、島民たちは魚を捕って暮らしていた。エリスは船のボイラーを使って蒸留水を作って見せたところ、島民たちは「これからは水不足で死なずに済む」と喜び、島を年間50ポンドの租借料で999年間譲り渡す契約に同意した。
こうして島を手に入れた太平洋諸島会社は中国人労働者などを導入して燐鉱石の採掘を開始。バナバ人は会社に事務員や店員などとして雇われ、他の島から食糧を輸入して暮らすようになった。バナバ島の繁栄を見てドイツは驚き、ナウル島でも太平洋諸島会社とドイツ資本のヤルート会社(上述)が合弁で太平洋燐鉱会社(Pacific Phosphate Ltd)を作り、燐鉱石の採掘をスタート。第一次世界大戦でナウル島を占領したイギリスは合弁会社を買収して、新たにイギリス、オーストラリア、ニュージーランド政府の共同出資による英国燐鉱委員会(BPC)を設立したが、太平洋諸島会社もこの時BPCに買収されて、株主たちは大きな利益を手にした(※)。
※このほか、BPCが採掘を行った島は、インド洋のクリスマス島。太平洋戦争が勃発すると、バナバ島は日本軍が占領、バナバ人たちはナウル島やコスラエ島、タラワ島(キリバス)などへ強制的に移され、日本軍の食糧にするカボチャ作りなどで働かされた。一方日本軍は出稼ぎ労働者たちは島に残し、燐鉱石の採掘を続けて日本へ輸出しようとしたが、戦況の悪化で果たせずじまい。終戦までに日本軍は労働者たちを殺し、生き残ったのは1人だけだったという(※)。※戦後、オーストラリアで戦犯として裁かれた日本兵の供述によれば、「土民(労務者)たちは日本の敗勢を知って反抗し攻撃してきたので、命令によって殺害した」とか。戦争が終わって島民たちはバナバ島へ戻れると思ったが、イギリスは「島は日本軍に破壊されてとても住める状態じゃないから」と説明し、5000人の島民を同じくイギリス植民地だったフィジーのランビ島へ移した。実際にはバナバ島ではBPCが他の島から労働者を導入して大々的に採掘を再開し、島は「済める状態じゃない」どころか2000人の労働者で賑わっていたのだが、島民たちはバナバ島へ行くことを禁止されていたので、故郷がどうなっているのか全くわからない状況に置かれていた(※)。※島民もそれなりに「オイシイ思い」をしたナウルに比べて、バナバ人たちがここまでヒドイ目に遭ったのは、ナウルは国連の委任統治領だったから。イギリスやオーストラリア、ニュージーランドは島民の生活状況について国連へ報告書を提出する義務があり、戦後信託統治領となってからは国連の現地視察団を受け入れる義務があり、ナウル人の利益にも気を使わなければならなかった。それに対して、バナバ島は単なるイギリス植民地だったから、国際社会の監視を気にせずに好き勝手できたということ。しかし1969年にナウルが独立し、同時にBPCの鉱山を国有化してナウル人は遊び暮らしているという話を聞くと、「俺たちにも同じ待遇をしろ!」とバナバ人たちが要求するのは当然のこと。イギリスやBPCが自分たちを騙してバナバ島へ帰らせなかったことへの補償や賠償を求める裁判を起こし、独立を控えたキリバスには燐鉱石の収益基金の引き渡しを求め、それらの資金をもとにバナバ島の独立も要求した。しかし独立後のバナバ島を支えるはずだった燐鉱山は79年に操業を停止。バナバ人が手にした賠償金(英、濠、ニュージーランドの3ヵ国から1000万ドル)やBPCからの補償金、キリバスからの収益基金などは預けた運用者が持ち逃げしてパー。結局バナバ人たちは独立も金も手に入れることができず、残ったのはキリバスへの参政権だけで、フィジー領のランビ島からキリバス国会へ代表を送っている。
※もちろんフィジーでの参政権もあって、フィジー国会にはバナバ人の議員も当選している。バナバ島へは約200人の住民が戻り、長年の採掘で荒れた島の復元作業をしているが、道路や水道などのインフラや、病院、学校などの施設はBPCが撤退してから放置されて来たので荒れたまま。まずそれらの復旧に金がかかるし、農業をやるには残った燐鉱石を掘り尽くさなければならないし、燐鉱石をこれ以上掘るにも品質が悪くて採算が合わないものばかり残っているので、どうにもならない状況だ。ランビ島のバナバ人たちとバナバ島との間の通行権も保障されたが、なにせ3200kmも離れた島同士。ランビ島と帰島者との間の行き来もほとんどなくなっているという。
第32回ピースボート「地球一周の船旅」 ランビ島のバナバ人たちとの交流レポート
Abara Banaba バナバ島やフィジーへ移住させられた旧バナバ島民の様子を紹介しています(英語)
【過去形】東清鉄道附属地
【過去形】中東鉄道附属地
【過去形】南満州鉄道附属地JRが国鉄だった頃、「鉄道公安官」というのがいました。そういうタイトルの刑事ドラマもテレビでやっていたような・・・。今にして思えば、日本の国鉄は警察権を持っていたんですね。
かつての満州には、警察権はおろか鉄道付属地という鉄道会社が「絶対的かつ排他的な行政権」を持つ地域がありました。鉄道付属地を作ったのは、1896年の露清同盟密約によってロシアが設立した東清鉄道。東清鉄道はウラジオストクなどの沿海州とモスクワを結ぶシベリア鉄道の一部として建設されたため、ロシアは線路用地を自国領内と同じように支配したいと、行政権や警察権、司法権、軍隊駐留権などを確保したもの。しかし鉄道付属地の具体的な範囲は規定されていなかったために、ロシアはこれを拡大解釈して、線路用地のみならず沿線の鉱山や森林、そして主な駅の周りの市街地も鉄道付属地に指定して、東清鉄道が支配。1898年にロシアが大連、旅順などの関東州を租借すると、ハルビンから大連に至る南部線も建設されて、鉄道付属地は満州南部にも広がった。東清鉄道は1912年に中華民国が成立すると、中東鉄道または東支鉄道と呼ばれるようになった。
1904年に日露戦争が勃発すると、日本は朝鮮国境の安東(現在の丹東)と奉天を結ぶ軍用鉄道の安奉線を建設したが、安奉線も沿線に鉄道付属地を設定して支配した。しかしこれは清との条約に基づいたものではなく、日本軍が実力によって勝手に設定したもの。戦後、日本はロシアから東清鉄道のうち長春(後の新京)〜大連間とその支線を獲得し、南満州鉄道(満鉄)を設立して経営したが、安奉線と合わせてその付属地も引き継いだ。
満鉄付属地の行政運営は満鉄地方部が行い、主要駅の付属地では満鉄が住民から税金を徴収する一方で議会も設置された。また軍隊は関東軍が、警察は大連にあった関東州庁が、司法は各都市の日本領事館が担当した。東清鉄道や後の中東鉄道でも主な付属地に市議会を設置し、会社の監督の下で自治制度が敷かれていた。
中東鉄道の付属地は、ロシア革命で成立したソ連政府が「帝政ロシアが中国で獲得した租界や権益、治外法権などの特権を放棄する」と発表したため、1921〜24年にかけて中国が接収。満鉄付属地は1932年の満州国成立後も続いたが、満州国では首都・新京をはじめ主要都市の市街地の大半が満鉄付属地で満州国の行政権が及ばず、都市在住の日本人の多くは満鉄付属地に住み、満州に進出した日本企業も満鉄付属地で登記して治外法権の特権を享受し続けたため、「これではせっかく作った満州国の首を絞めかねない」と、それまで満鉄付属地の拡大を図っていた日本は一転。1937年に満鉄は付属地を満州国へ返還することになり、鉄道付属地は消滅しました。
詳しくはこちらを参照してくださいね。
満鉄の社章

P-S475a, 3 Rubles, 1917 中東鉄道の付属地で使われていた紙幣の写真です
【過去形】天津ベルギー株式租界大正8年(1919)の天津市街図 右下の隅に比国租界(ベルギー租界)があります
奥=オーストリア、意=イタリア、俄=ロシア、比=ベルギー、日=日本
法=フランス、英=ドイツ、美=アメリカ、徳=ドイツの租界戦前の中国には主要都市に租界がありました。租界とは、列強各国が治外法権に加えて行政権や警察権を持つ外人居留地のことで、日本租界、イギリス租界、フランス租界、アメリカ租界、ドイツ租界、ロシア租界・・・などなどが存在しましたが、天津にはベルギー租界もありました。あれ、ベルギーって列強なの?と思うかも知れませんが、アフリカのコンゴに広大な植民地(しかも1908年まではベルギー国王レオポルド2世の私有植民地)を持っていた、レッキとした列強の一員です。
ベルギーが中国で租界を作ろうと、最初に目をつけた場所は漢口(現在の武漢)。ベルギーは中国各地で鉄道建設の利権を持っていたが、「鉄道建設のベルギー人スタッフの居留地にするため」と称して、日本租界の東北側の土地を3万6000両で買い占め(当時の地図)、地元政府にベルギー租界の設置を認めるように要求した。清朝は「ベルギー人のスタッフは鉄道会社が借りた住宅に住めばいい」とベルギー租界の設置を拒否したが、清朝がベルギーから買い占めた土地を買い戻す際には、ベルギーは「鉄道が開通したので地価が暴騰した」と主張して、81万8000両で買い取らせ、大もうけをした。
続いてベルギーが租界を作ろうとしたのが天津。1900年に義和団の乱が起こり、北京の各国大使館が襲撃されると、列強8ヵ国(英仏米独露伊墺日)の連合軍は北京を占領するが、この時ベルギーは連合軍に加わっていなかったにもかかわらず、火事場泥棒的に天津のロシア租界南方の一角を占拠。ここをベルギー租界とするように清朝へ要求し、1902年に租界開設を認め、さらに将来の租界拡張のために予備租界も確保した。
しかしベルギー租界は天津の中心部から離れていたため、開発は一向に進まず、いつまで経っても田んぼや沼地が広がっている状態。ベルギー政府もやがて租界運営に対する興味を失って、租界返還の声も出たが、「それではベルギーの名誉に関わる」と、結局租界を「民営化」することになった。こうして1912年に天津在住のベルギー人たちによって天津ベルギー租界株式会社(Societe anonyme de la concession Belge de Tien-Tsin)が設立され、翌年ベルギー政府から租界の譲渡を受け、以後、ベルギー租界は股票租界(株式租界)と呼ばれるようになった。
租界の市役所に相当する行政機関の工部局や租界警察署を運営するのは董事会(取締役会)で、ベルギー人4人によって構成され、ベルギー政府は租界会社に対して「高度の指揮及び干渉権」を有していたが、董事長(代表取締役)は天津のベルギー領事が兼任していたため、実質的には領事館の強い監督下にあった。租界会社は住民から地税、家屋税を徴収したほか、埠頭使用税や車税(租界を通行する車から徴収)、酒造税などを取り立てたが、租界の開発は依然として進まなかったうえ、第一次世界大戦でベルギー本国がドイツ軍に占領されるなどの混乱で資金も集まらず、銀行から借りた借金の利子支払いにも窮するようになった。
このためベルギー人の間でも「租界を続けたところで何の利益はない」という声が高まり、ベルギー政府は中国へ自主的に租界を返還することを決意。1927年1月に北洋政府との間で租界返還の条約を結ぶが、折りしも北伐で北洋政府は解体してしまい、ベルギー政府は新たに中国の実権を握った国民政府と交渉するが、「北洋政府と結んだいかなる条約も無効」だと相手にされず、租界返還は頓挫。「返したくても返せない」状態が続いていたが、29年に改めて国民政府と租界返還の条約を結び、31年にようやく返還が実現。租界会社が抱えていた9万3000両の借金の返済は中国政府に肩代わりしてもらうことになったが、ベルギーは漢口の「租界予定地買い取り」では大もうけしたクセに、ちょっとセコイですね。


返還式典当日のベルギー租界工部局(左)、返還式典で式辞を読み上げるベルギー代表(右)
中国新建集団公司中国新建集団公司の管轄地分布図 (中国語)
「屯田兵」って、日本史で習いましたよね?時は明治の初め。北海道の統治を本格化させた明治政府は、ロシアの侵攻や先住民(アイヌ人)の反乱に備えて、平時には農地開拓に従事し、有事には銃を取る屯田兵を各地に入植させた・・・というわけですが、屯田兵の元祖といえば中国。古くは漢の時代(紀元前2世紀頃)から西域へ屯田兵を送り込んでいたとか。
で、その中国にはなんと現在も屯田兵が存在している。もちろん人民解放軍なわけで、新疆生産建設兵団というのがそれ。新疆では1930年代から40年代にかけて東トルキスタン共和国の独立など少数民族の反乱が続いていたが、1949年に中華人民共和国の成立と前後して人民解放軍が進駐。54年にそのうち10万5000人の兵士が国防部の管轄を離れて生産建設兵団、つまり屯田兵に組織し直された。
とりあえずこちらの一番下を参照してくださいね。
参考資料:
伊東 祐穀 『世界年鑑』 (博文社 1904)
伊東 祐穀 『世界年鑑 第7回』 (博文社 1911)
『独領南洋諸島事情』 (外務省通商局 1915)
『葡領東阿弗利加事情』 (対米船舶提供記念財団 1926)
『東支鉄道を中心とする露支勢力の消長(上・下)』 (南満州鉄道ハルビン事務所運輸課 1928)
『天津居留民団二十周年記念誌』 (天津居留民団 1930)
矢内原忠勝 『南洋群島の研究』 (岩波書店 1935)
『治外法権撤廃並満鉄附属地行政権の調整乃至委譲に対する満洲国側の準備 』 (満州国総務庁情報処 1936)
『英領北ボルネオ事情』 (南洋庁長官官房調査課 1940)
植田捷雄 『支那に於ける租界の研究』 (巌松堂書店 1941)
『南洋群島要覧. 昭和16年版』 (南洋庁 1941)
アンドレ・シーグフリード 著 ; 大住龍太郎 訳 『スエズとパナマ』 (大阪朝日新聞社 1941)
『世界地図』 (三省堂 1942)
『世界年鑑 昭和17年版』 (日本国際問題調査会 1942)
『世界年鑑 1950』 (共同通信社 1950)
『世界年鑑 1955』 (共同通信社 1955)
在ソールスベリ日本国総領事館・編 『ローデシア・ニアサランド連邦便覧』 (日本国際問題研究所 1963)
星昭、林晃史 『アフリカ現代史1』 (山川出版社 1978)
吉田昌夫 『アフリカ現代史2』 (山川出版社 1978)
北大路弘信、北大路百合子 『オセアニア現代史』 (山川出版社 1982)
A.H.デ・オリヴェイラ・マルケス 訳:金七紀男 『世界の教科書=歴史 ポルトガル第三巻』 (ほるぷ出版 1985)
天津市政協文史資料研究委員会・編 『天津租界』 (中国:天津人民出版社 1986)
費成康 『中国租界史』 (中国:上海社会科学院出版社 1991)
『天津日報専副刊』 2003年9月7日付
小川和美 「太平洋島嶼地域におけるリン鉱石採掘事業の歴史と現在」 http://www.jaipas.or.jp/
小川和美 「2001年フィジー総選挙の分析」 http://www.jaipas.or.jp/
World History at KMLA http://www.zum.de/whkmla/index.html
The World at War http://worldatwar.net/index.html
Royal Greenland A/S http://www.royalgreenland.com/main/
ABARA BANABA http://www.banaban.com/
BANABA Aspects of History http://www.janesoceania.com/kiribati_banaba_history/index.htm